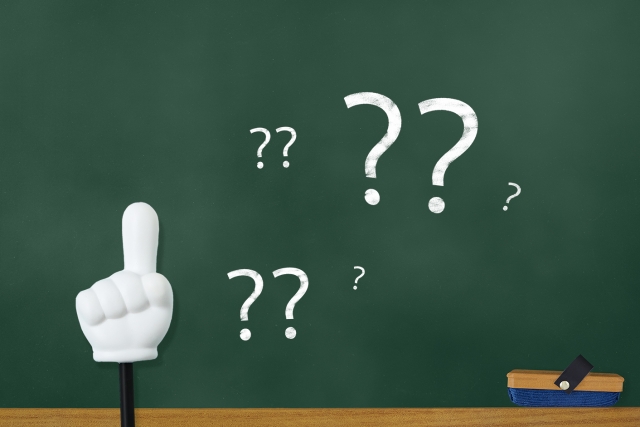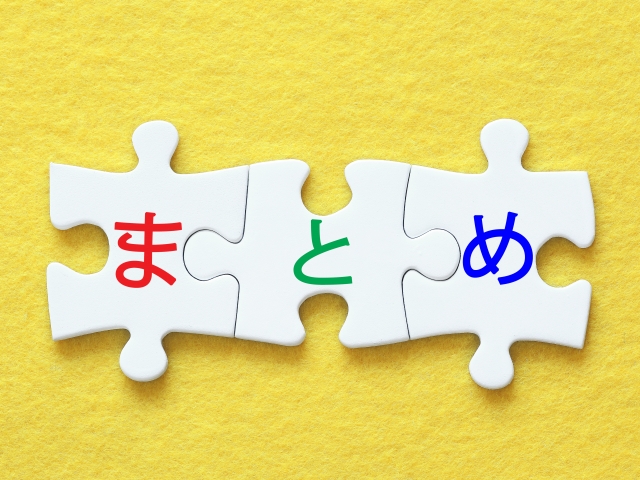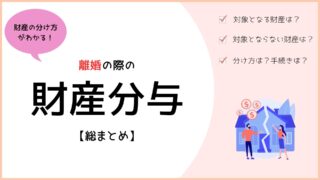
- 財産分与って何ですか?
- 財産分与の対象となる財産はどんな財産ですか?
- どういう手順、手続きで進めていけばいいですか?
- どういう方法で財産を分けるのですか?
この記事はこのような疑問、お悩みにお応えします。
離婚のときには親権、養育費、慰謝料、面会交流など、相手と話し合い取り決めなければいけないことがたくさんあります。財産分与もその中の一つです。
しかし、財産分与と一言でいっても、財産分与の対象となる財産ごとに決めるべき内容が異なり、内容も複雑で、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、財産分与とは何か、財産分与の対象となる財産、ならない財産とは何か、どういう手順、手続き進めていけばよいのか、どういう方法で財産を分けるのかについて詳しく解説していきたいと思います。
この記事を書いた人

-
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。※大変申し訳ありませんが、ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しております。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】
- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説
- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します
- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します
離婚時の財産分与とは
離婚時の財産分与とは、離婚に際して夫婦の財産を分け合うことです。財産分与には
- 清算的財産分与
- 慰謝料的財産分与
- 扶養的財産分与
の3種類があります。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦の財産を分与割合(通常2分の1)にしたがって分ける財産分与です。
文字通り、離婚のときに、それまで夫婦で築き上げてきた財産を清算するのが清算的財産分与です。実務上は、清算的財産分与により財産分与するケースが圧倒的に多いです。
たとえば、離婚のときに財産分与の対象となる「夫名義の預金100万円(妻名義のの預金0円)、夫名義の借金50万円」の財産をもっている夫婦が、夫に25万円(=(100万円-50万円)÷2)、妻に25万円、と分けるのが清算的財産分与です。なお、この分け方では夫が納得しない可能性もあるため(離婚後は夫が借金50万円の返済義務を負うため)、財産分与しないとする(夫に預金100万円をもたせたままにする)ことも可能です。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、財産分与に慰謝料の要素を含ませた財産分与です。
財産分与請求権と慰謝料請求権は別の権利ですから、本来は別々に請求できます。しかし、夫婦で合意できるのであれば、財産分与に慰謝料の要素を含ませ、慰謝料については別途請求しないとすることも可能です。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後の相手の生計維持を目的として行われる財産分与です。
扶養的財産分与は、清算としての財産分与や慰謝料の要素を加味してもなお、夫婦の一方に生活に困る事情があり、他方に扶養能力がある場合に検討される補充的な財産分与です。一定期間金銭を支払う方法が多いですが、家の利用権(使用借権、賃借権)を設定するなどの方法もあります。
財産分与の対象となる共有財産
財産分与の対象となる財産は夫婦の共有財産です。共有財産とは、
- 夫婦共有名義の財産(狭義の共有財産)
- 婚姻後に夫婦で協力して築き上げたと認められる財産(実質的共有財産)
のいずれかの財産です。
以下、共有財産になりうる主な財産をみていきましょう。
預貯金
婚姻後、別居(あるいは離婚)時までに築いた預貯金は財産分与の対象です。名義やどちらが稼いだか、収入が多いか少ないかは関係ありません。子ども名義の預貯金も、その原資によっては財産分与の対象となります。
退職金
婚姻から退職までに相当する金額が財産分与の対象です。すでに支給されている場合は財産分与の対象となりますが、まだ支給されていない場合は、支給される可能性が高いといえる場合に財産分与の対象となります。
家
共有名義の場合はもちろん、単独名義の場合でも婚姻後に購入した家は財産分与の対象となります。もっとも、オーバーローンの場合は資産価値「ゼロ」とみなし、財産分与の対象としない扱いとします。
車
婚姻後に購入した車で、車のローンを夫婦の共有財産で払っていたような場合は財産分与の対象です。家と同じく、オーバーローンの場合は財産分与の対象としませんが、車の名義やローンの支払いをどうするかきちんと話し合っておく必要があります。
生命保険
生命保険は貯蓄型と掛け捨て型に分かれますが、貯蓄型の生命保険の保険料払込期間に対応する解約返戻金が財産分与の対象となります。生命保険を解約するか否かは慎重に検討する必要があります。
学資保険
学資保険も保険料払込期間に対応する解約返戻金が財産分与の対象となります。もっとも、生命保険と同じく、学資保険を解約するかどうかは慎重に検討する必要があります。
関連記事
借金
財産分与の対象となる財産は、預貯金などのプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産>プラスの財産の場合は財産分与はしません。
関連記事
財産分与の対象とならない特有財産
一方、基本的に財産分与の対象とならないのが特有財産です。特有財産とは、
夫婦の一方が
- 婚姻前から所有していた財産
- 婚姻中に相続・贈与など、相手とは無関係に取得した財産
- 婚姻後に購入した物ではあるものの、衣服等明らかに夫婦の一方の専用品として使用されている物
のいずれかです。
もっとも、相手の寄与・貢献によって、特有財産の消滅・価値の減少を防止し、あるいは維持してきたと認められる場合には、寄与・貢献度に応じて、相当額を財産分与の対象とすることができます。
関連記事
財産分与の割合
財産分与の対象となる財産を確定できたら、次に検討すべきなのがどのような割合(分与割合)で財産を分けるかということです。
ただ、この点に関しては、実務上、特段の事情がある場合を除き、2分の1の割合で分けることがほとんどです。専業主婦であっても、基本的に分与割合は2分の1です。
2分の1の原則を修正すべき特段の事情としては、
・夫婦の一方の特別の努力や能力によって高額の資産が形成された
・家を購入する際、夫婦の一方の特有財産を頭金に充てた
・夫婦の一方が勤労、家事労働を引き受けて、他方がこれを全く行わなかった
・夫婦の一方が、他方に無断で多額の借金を背負った
場合などが考えられます。
財産分与の方法①(共有財産の把握~方法の決め方)
財産分与を行うには、まずは共有財産を把握し、最後にどのような方法で財産分与するのかを決める必要があります。ここでは共有財産の把握から財産分与の方法までの一般的な流れについて解説します。
① プラス、マイナスの共有財産をリストアップ
↓
② 証拠を集める
↓
③ 評価が必要な財産を査定に出す
↓
④ 財産分与対象額を計算する
↓
⑤ 分与割合について話し合う
↓
⑥ 基本の取得分額を計算する
↓
⑦ 未払婚姻費用があれば⑥に加算
↓
⑧ 慰謝料的要素、扶養的要素の加味を検討
↓
⑨ 財産分与の方法を決める
①プラス、マイナスの共有財産をリストアップ
まず、財産分与の対象となるプラスとマイナスの共有財産をリストアップします。同時に特有財産がないかを確認し、例外的な事情がない場合は、財産分与の対象から外します。
②証拠を集める
次に、共有財産のリストアップと同時に証拠を集めます。証拠は話し合いのときでも必要になりますし、調停→裁判と手続きを進めた場合は提出を求められます。相手に離婚(別居)を切り出す前に、証拠を集めきることが大切です。
【共有財産の主な証拠】※原本はすべてコピーをとる
・預貯金・・・・預金通帳(子供名義の通帳も含む)、残高証明書
・退職金・・・・預金通帳、残高証明書、退職金見込計算書(勤務先で発行)
・不動産・・・・売買契約書、登記事項証明書(法務局から取り寄せ)、固定資産税の納税通知書、金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)、住宅ローンの償還予定表
・車 ・・・自動車検査証(車検証)、ローンの償還予定表
・積立型保険・・保険証券、保険証書、解約返戻金証明書
・借金 ・・・通知書、明細書(金融機関、ローン会社から送付されるもの)
関連記事
③評価が必要な財産を査定に出す
①、②と並行して評価が必要な財産(不動産、車など)を査定に出します。査定の方法は財産の種類によって異なりますが、法律で定められているわけではなく、夫婦で合意できるのであれば合意した方法で査定しても問題はありません。
④財産分与対象額を計算する
①~③まで終わったら、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き「財産分与対象額」を計算します。
ここで「プラスの財産>マイナスの財産」の場合は、その差額が財産分与対象額となります。一方、「プラスの財産<マイナスの財産(債務超過)」の場合は財産分与対象額を「ゼロ(マイナスとはしない)」とし、財産分与は行わないのが通常です(※)。
※もっとも、たとえば、夫単独名義のマンション(1000万円)と夫単独名義の住宅ローン(1500万円)があり、その余の財産がないという場合、話し合いで、マンションと住宅ローンの名義を妻単独とし(※ただし、金融機関の承諾が必要)、代わりに夫が妻に対し250万円(=(1500万円-1000万円)÷2)を支払う旨の合意をすることも可能です。
⑤分与割合について話し合う
共有財産を把握し財産分与対象額を算出し、離婚準備も整えた後、相手に離婚の話し合いを切り出します。相手が隠し財産をもっている疑いがある場合は任意の開示を求め、応じない場合は弁護士に依頼すること、調停を申し立てることを検討します(※)。すべての財産の分与対象額を計算した後、相手と分与割合について話し合います。
※弁護士に依頼すれば「弁護士照会」、調停を申し立てた場合は「調査嘱託」という制度を利用できます。弁護士照会、調査嘱託についてはコチラの記事の「隠し口座の調べ方」で詳しく解説しています。
⑥基本の取得分額を計算する
分与割合について合意できたら、次の計算式で基本となる取得分額を計算します。
基本の取得分額=財産分与対象額×分与割合
財産分与対象額1200万円、夫の分与割合「3分の1」、妻の分与割合「3分の2」の場合、夫の基本の取得分額「400万円」、妻の基本の取得分額「800万円」となり、妻は夫に400万円(=800万円-400万円)の支払いを求めることができます(お金で財産分与する場合)。
⑦未払婚姻費用があれば⑥に加算
婚姻費用とは婚姻生活で生じる生活費です。別居から離婚までは婚姻関係が継続しているため、夫婦は互いに婚姻費用を分担する義務を負います。もし、夫婦の一方が婚姻費用を過当に負担していた場合は、財産分与の基本の取得分額に未払婚姻費用を加算して清算することが可能です。
具体的取得分額=基本の取得分額+未払婚姻費用額
⑧慰謝料的要素、扶養的要素の加味を検討
この記事の冒頭でも述べたとおり、財産分与に慰謝料的要素を含めることも可能です。含める場合は、あとでトラブルとならないよう、含める旨を書面にはっきり残しておきましょう(下記参照)。財産分与に扶養的要素を含まる場合も同じです。
第〇条(財産分与)
1 甲は、乙に対し、財産分与として、令和〇年〇月〇日までに、金〇〇万円を乙が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、甲が負担する。
2 甲及び乙は、前項の財産分与には、甲の乙に対する慰謝料が含まれており、乙は、甲に対し、本条とは別に、離婚原因慰謝料ないし離婚自体慰謝料を請求できないことを相互に確認する。
⑧財産分与の方法を決める
最後に、財産分与の方法を決めます。実務上、最も多く選択される方法はお金による財産分与ですが、お金で払うとしても一括か分割か、分割の場合、回数をどうするかなどを決める必要があります。分割での支払いに合意する場合は遅延損害金や過怠条項を設けることも検討しましょう。
また、不動産などの現物、家の利用権を財産分与する方法もあります。たとえば、夫単独名義の住宅ローンが残っている夫単独名義の家に、離婚後も妻と子どもが無償で住むことについて合意したり(使用借権の設定)、妻が夫に住宅ローン相当分の金銭(賃料)を払うことを条件に住むことに合意したり(賃借権の設定)することが考えられます。
財産分与の方法②(手続き)
ここでは、財産分与の取り決めを行う手続きについて解説します。
話し合う
まずは、話し合いで決めますが、相手に話し合いを切り出す前に離婚準備を整えておくべきことはすでに述べたとおりです。
話がまとまったらトラブル防止のため、離婚協議書、あるいは離婚公正証書を作って取り決めた内容をお互いが確認できる形にしておきましょう。
強制執行認諾文言付き公正証書を作っておけば、お金の未払いがあったときに、裁判を経ずに相手の財産を差し押さえる手続きをとることができます。
財産分与でお金の取り決めをした場合、財産分与のほか養育費、慰謝料の取り決めをした場合は離婚公正証書を作っておきましょう。
調停を申し立てる
一方、話し合いができない、話し合いはできても話がまとまらないという場合は離婚調停(夫婦関係調整調停(離婚))を申立てます。
調停では調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進行していきますから、夫婦だけで話し合いをするよりかは話がまとまる可能性があります。話がまとまった場合は調停調書という書面が作成され、調停が成立します。調停調書にも公正証書と同様の強制力があります。
一方、話がまとまらない場合、相手が調停に出頭しない場合などは調停不成立となります。その後は、調停に代わる審判がなされない限り、裁判で決着を図ることになります。
財産分与でよくあるQ&A
最後に、財産分与でよくある疑問にお応えします。
相手の不貞が原因で離婚しますが、財産分与する必要はありますか?
不貞などの離婚原因を作った側(有責配偶者)にも財産分与を請求できる権利はあります。財産分与はあくまで婚姻期間中に夫婦で築いた財産を清算するというものですから、離婚原因や慰謝料の問題とは別の問題として考える必要があります。
関連記事
財産分与したら税金がかかりますか?
基本的にかかりませんが、過大な財産を受け取った場合、脱税目的で離婚した場合は贈与税がかかることがあります。また、不動産を財産分与した場合は登録免許税、固定資産税・都市計画税などがかかります。
離婚後に財産分与する場合に気をつけることはありますか?
除斥期間です。除斥期間は離婚成立時から2年で、2年を経過すると財産分与請求することができません。除斥期間は時効と異なり、進行期間をリセットしたり、期間を延長することができません。
除斥期間です。離婚時から2年を経過すると請求権が消滅します。一方、離婚前に財産分与の取り決めをし、離婚後に請求する場合は除斥期間ではなく時効が適用されます。協議で取り決めをした場合は5年、調停等で取り決めをした場合は10年が時効期間です。
年金はどうやって分けますか?
年金を分けるには財産分与とは異なる手続きをとる必要があります。なお、年金分割の対象となるのは厚生年金保険料の納付実績です。国民年金保険料しか払ってこなかった方は対象外です。また、年金そのものを分割するものではありません。
共有財産を勝手に処分されそうですが、止める方法はありますか?
離婚前は民事訴訟法に基づく保全処分の申立てを裁判所に行うことが考えられます。保全処分とは、相手に支払いを求める範囲で相手の預貯金等の財産を仮に差し押さえる「仮差押え」と引き渡しを請求したい物の処分を禁じる「仮処分」があります。
保全処分を申し立てるには、財産分与を請求できる権利があることが認められる蓋然性と財産を保全する必要性を明らかにする必要があります。また、保全を求める財産の10~15%の担保(お金)を裁判所に提出する必要があります。担保は財産分与が確定した段階で戻ってきます。
まとめ
今回のまとめです。
- 財産分与とは共有財産を夫婦で分け合うこと
- 財産分与には清算的財産分与、慰謝料的財産分与、扶養的財産分与があり、清算的財産分与が主流
- 財産分与の対象となる財産は共有財産
- 分与割合は2分の1が基本
- 財産分与をスムーズに行うには、相手に離婚を切り出す前に共有財産をリストアップし、裏付けとなる証拠資料を集めておく
- 財産分与は話し合い→調停の手順で決めていく