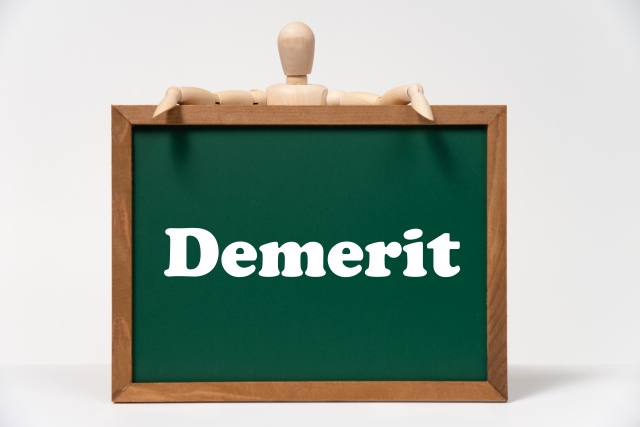- 養育費を内容証明で請求する方法を知りたい
この記事ではこのような悩みにお応えします。
相手に口頭やLINE・メールで養育費を請求しても効果がない場合に検討したい方法が、養育費の請求書面を作り、それを内容証明で相手に送る方法です。
ただ、養育費の請求書面を作ること、内容証明を使って郵便物を送るという経験が初めてで、どうやればいいかわからないという方がほとんどではないでしょうか?
そこで、今回は、内容証明や養育費の請求書面を内容証明で送るメリット・デメリットを解説した上で、養育費請求書の書き方や内容証明郵便の送り方などについて詳しく解説していきたいと思います。
この記事を書いた人

-
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】
- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説
- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します
- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します
内容証明とは
内容証明とは、いつ、どんな内容の書面を、誰から誰に送ったのかを郵便局が証明してくれる郵便制度です。内容証明という書面があるわけではなく、内容証明は「速達」などと同じように、相手に書面を送るための郵便手段の一つということになります。
郵便局に差し出した謄本(請求書面の原本の写し)は5年間保管され、差出人(内容証明を送る人)は5年間は差し出した謄本を見たり、再度証明を受けることができます。
養育費を内容証明で請求するメリット
では、養育費の請求書面を内容証明で送ることにはどんなメリットがあるのでしょうか?
相手と接触しなくていい
まず、相手と接触しなくていいことです。相手と直接会って話したり、電話やLINE・メールでやり取りして養育費を請求するには抵抗がある、という方にとってはメリットといえます。
相手に心理的な圧力をかけることができる
次に、相手に心理的な圧力をかけることができることです。内容証明による請求書面を使うことで、LINEとは異なるインパクトを相手に与えることができ、養育費の支払いを強くうながすことができます。
相手に請求の意思を確実に伝えることができる
次に、相手に養育費を請求するという意思を明確に伝えることができることです。内容証明を使えば、相手が請求書面を受け取ったことを郵便局が証明してくれますので、相手が「そんな請求された覚えはない」という言い訳ができなくなります。なお、仮に相手が開封せずに書面の内容を見なくても、書面の内容は相手に伝わったものとして扱われます。
養育費を内容証明で請求するデメリット
一方、養育費の請求書面を内容証明で送ることには次のデメリットがあります。
書面の内容に強制力がない
まず、公正証書などと異なり、内容証明の請求書面には強制力がないことです。つまり、相手に請求を無視されたとしても、相手が内容証明の書面を受け取ったことを理由に相手の財産を差し押さえたりすることはできません。
関連記事
払わない気持ちを固めさせてしまう
次に、相手の反感を買う可能性があることです。相手としたら、書面で養育費を請求されることは気持ちのいいものではなく、送ったことによって相手がもともともっていた養育費を払わないという気持ちをさらに固めさせてしまうおそれがあります。
財産を使われる・隠される、行方をくらまされる
次に、相手に財産を使われたり、隠されたり、あるいは行方をくらまされたりする可能性があることです。公正証書などの債務名義がある場合、養育費を払わなければ、あなたから強制執行の手続きをとられる可能性があることは相手もわかっています。相手に内容証明を送ることで強制執行の現実味を感じさせ、相手を上記の行動へとうながしてしまう可能性があります。

未払いの期間、これまでの経緯・相手の対応、相手の性格、離婚前の相手との関係性などによっては、いきなり強制執行を申し立てることも検討しなければいけません。
続きを見るには・・・
大変申し訳ありませんが、ここから先は有料コンテンツとなっています。お手数ではありますが、ご購読ご希望の方は以下の「この記事を購入」をタップしていただき、ご購入手続きをお願いいたします。
【コンテンツご購入のメリット】
・契約書面作成のプロである行政書士が直接執筆
・できる限り簡単な言葉で養育費請求書の作り方を詳しく解説
・初めての方でも専門家に頼らず作成にチャレンジできる
・養育費請求書のサンプルを無料でダウンロードできる
【有料コンテンツの目次】
4 養育費請求書の書き方【サンプルあり】
4-1 ①標題
4-2 ②日付
4-3 ③相手の住所・郵便番号、氏名
4-4 ➃あなたの住所・郵便番号、氏名
4-5 ⑤~⑦本文
4-6 請求書面のQ&A
4-6-1 手書きで書いてもいいですか?
4-6-2 差出人の住所は書かなければいけませんか?
4-6-3 相手からの書面を自宅以外の場所で受け取る方法はありますか?
5 相手の住所の調べ方
6 養育費の内容証明の送り方
6-1 必要なものを準備する
6-1-1 ①原本1部
6-1-2 ②謄本2部
6-1-3 ③お金
6-2 郵便局で請求書面を送る
6-3 配達されたことを確認する
7 内容証明を送った後の対応
7-1 相手から減額請求されたとき
7-2 相手の反応がないとき
7-1-1 履行勧告・履行命令
7-1-2 強制執行