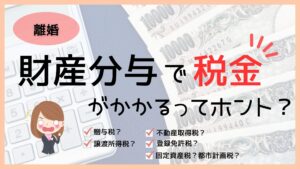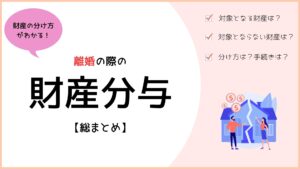- 離婚後に財産分与を請求することはできますか?
- 離婚後に財産分与を請求する場合の期限はありますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
財産分与などの離婚の諸条件は離婚前に取り決めておくことが理想ですが、様々な事情により、離婚だけ成立させ、離婚後に取り決めようとした、あるいはそもそも離婚前に取り決めることができなかったなどという場合もあると思います。そこで、今回は、離婚後に相手に財産分与を請求することの可否や請求する場合の注意点・手順などについて詳しく解説していきたいと思います。
この記事を書いた人

-
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】
- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説
- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します
- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します
離婚後に財産分与を請求できる?
まず、離婚後に財産分与を請求できるかですが、離婚時に財産分与の取り決めをしていなかった場合でも請求することは可能です。
もっとも、離婚時に財産分与の取り決めをしていなかった場合でも、離婚協議書などの合意書に清算条項(※)が設けられている場合、その内容によっては財産分与を請求できない可能性があります。
離婚時に、相手と離婚協議書などの書面を取り交わしている場合は、書面に清算条項がもうけられていないか、清算条項によって財産分与を請求することが遮断されていないか一度確認してみる必要があります。
一方、離婚時に財産分与の取り決めをしている場合(財産分与の請求をしている場合)は、その取り決めにしたがって離婚後に財産分与を請求することができます。なお、この請求権には、後ほど解説する除斥期間ではなく時効が適用されます。
財産分与に適用されるのは除斥期間
離婚後にはじめて財産分与の請求を行う場合にも、請求期限が設けられていることに注意が必要です。離婚後はじめて行う財産分与の請求期限には除斥期間が適用され、のちほど述べる例外を除いて、離婚時から2年を経過した後は当然に財産分与を請求できなくなってしまいます。除斥期間と時効とは異なる制度です。なお、離婚慰謝料の請求期限には除斥期間ではなく時効が適用されます。
【財産分与の請求期限に適用される制度の違い】
・離婚後にはじめて請求する場合→除斥期間が適用される
・離婚時に請求していた場合 →時効(消滅時効)が適用される
関連記事
財産分与の除斥期間と時効との違い
では、除斥期間と時効(消滅時効)はどのような点に違いがあるのか解説します。
援用が必要かどうか
まず、除斥期間では援用が不要なのに対して、時効では援用が必要という点です。
援用とは、時効期間が経過することによって利益を受ける人(お金の支払義務を負う人)が相手に対して、「時効期間が経過してあなたの権利が消滅したため、あなたの請求には応じられません」と意思表示することです。
時効の場合、期間が経過しただけでは相手の権利は消滅せず、この援用を行ってはじめて権利が消滅します。一方、除斥期間では期間の経過とともに当然に権利が消滅します。
更新や完成猶予が可能かどうか
次に、除斥期間では更新や完成猶予ができないのに対して、時効では可能という点です。
更新とは、経過した時効期間をリセットすることです。完成猶予とは、時効の完成を一定期間引き延ばすことです。時効では相手に債務の存在を承認させるなどして時効期間を更新することができます。
一方、除斥期間では期間をリセットしたり、引き延ばすことができません。離婚時から2年が経過すれば、当然に財産分与の権利が消滅してしまいます。
財産分与に時効が適用される場合
離婚後にはじめて財産分与の請求をする場合は除斥期間が適用されますが、離婚時に財産分与の取り決めをしていて離婚後に財産分与を請求する場合は時効が適用されます。
協議で離婚した場合は離婚時から5年で時効が完成し、相手の援用によって財産分与の請求権が消滅します。調停、審判、判決で離婚した場合は、調停の場合は調停成立時、審判、判決の場合は確定時から10年で時効が完成します。
除斥期間が経過した後も請求できるケース
除斥期間が経過した後は財産分与を請求できなくなるのが基本ですが、次のケースでは除斥期間が経過した後でも財産分与を請求することができます。
相手が任意に応じる場合
まず、相手があなたの財産分与の請求に任意に応じる場合です。
除斥期間は、いつ権利行使されるかわからないという相手の不安定な状態を短期間で終わらせるために設けられた制度ですので、相手がその利益を放棄し、請求に応じるのであれば請求できると考えてよいでしょう。
合意内容が無効、財産隠しされた場合
次に、離婚後2年以内に財産分与の合意をしたもののその合意が無効とされた場合や相手が財産隠ししていたことが発覚した場合です。
前者については除斥期間が経過した後も財産分与を請求できると判断された裁判例(東京高裁平成3年3月14日)があります。また、相手の財産隠しが証明できるのであれば、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得に基づく返還請求も可能です。
離婚後に財産分与を請求する手順
離婚後にはじめて財産分与を請求する場合の手順は次のとおりです。
①話し合い
まず、相手とコンタクトがとれ、話し合いができる状態であれば話し合いを試みてもよいでしょう。話し合いで解決したいものの、話がまとまらない場合は弁護士に依頼することも検討しましょう。
話がまとまった場合は合意書(財産分与契約書)を作成します。合意書に強制力をもたせておきたい場合は合意書をベースとして公正証書を作ることもできます。以下の関連記事は財産分与契約書にも応用できますので、参考にしてみてください。
なお、財産分与の対象となる財産は共有財産が基本ですとなりますから、話し合いの前提として何が夫婦にとっての共有財産なのか、反対に何が特有財産なのかを整理し、それぞれを裏付ける証拠資料を集めておく必要があります。
証拠資料がなければ冷静に話し合いを進めることが難しいですし、仮に調停を申し立てた場合には提出を求められます。提出できなければ、調停であなたの主張を通すことが難しくなってしまいますので注意が必要です。
②調停
話し合いをしても話がまとまらないという場合は、相手の住所を管轄する家庭裁判所に対して財産分与請求調停を申し立てます。また、裁判所に対し、相手が勝手に財産を処分したり、隠したりしないような処分(審判前の保全処分など)を求めることもできます。
申立先の裁判所は相手の住所を管轄する家庭裁判所が基本ですし、裁判所は申立てを受けた後、相手の住所宛に書面を送る必要がありますから、調停を申し立てるには相手の住所を把握しておかなければなりません。
調停を経て話がまとまれば調停調書が作成され、調停が成立します。調停調書にも公正証書と同様の強制力があります。一方、調停が不成立に終わった場合は、自動的に審判に移行します。審判でも審判書が作成されます。審判書にも強制力があります。
離婚前に財産分与の話し合いを
ここまで解説してきたとおり、法律上離婚後にはじめて財産分与を請求することは可能です。ただ、可能な限り、財産分与を含めた離婚の諸条件については離婚前に相手と話し合い、請求の意思表示をしておくことをおすすめします。
離婚の諸条件の取り決めをする際には、まずはあなたの主張を裏付ける証拠資料を集めておかなければならないことはすでに述べたととおりですが、離婚後に集めることはほぼ不可能です。相手に財産を使われたり、隠されるなどのリスクもあります。
また、離婚前と比べて相手の話し合いに対する態度は消極的で話し合いが難航することが予想され、仮に調停を申し立てても成立までに時間がかかったり、証拠資料が十分でないためないため満足のいく合意を得られなくなる可能性もあります。
そのため、財産分与を含めた諸条件については離婚前に相手と話し合い、取り決めをしておくことが理想です。仮に、離婚の成立を先行するにしても証拠資料は離婚前に集めておき、離婚後すぐに相手と話し合いをする準備はしておく必要があります。
まとめ
今回のまとめです。
- 離婚後、はじめて財産分与を請求することも可能
- 離婚後、はじめて財産分与を請求するときは除斥期間に注意
- 除斥期間と時効は異なる
- 離婚前に財産分与の取り決めをしていて、離婚後に請求する場合は時効が適用される
- 除斥期間が経過した後でも財産分与を請求できる場合がある
- まずは話し合いで財産分与を請求してみる