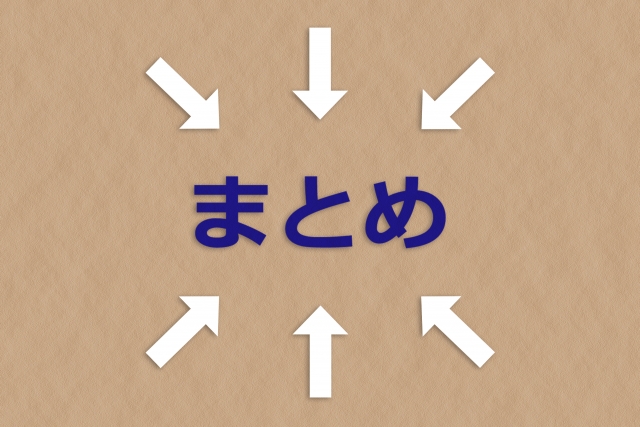- 離婚協議書に設ける清算条項とは何ですか?
- 書き方の注意点はありますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
離婚協議書のサンプルを見ると、定型で清算条項が設けられていることが多いですが、その重要性を理解しないままサンプルを丸写ししてしまう方が多く見受けられます。
ただ、清算条項は離婚後に金銭的な請求ができるか・できないか、されるか・されないか、というお金に関わる重要な条項ですから、その意味をしっかり理解しておく必要があります。
そこで、今回は、離婚協議書に設ける清算条項に関して詳しく解説していきたいと思います。
この記事を書いた人

-
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。※大変申し訳ありませんが、ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しております。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】
- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説
- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します
- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します
離婚協議書の清算条項の書き方【サンプル付き】
離婚協議書の清算条項とは、離婚問題を終局的に解決し、将来のお金のトラブルを防止するために、離婚後、離婚協議書で合意した内容以外のお金を請求しないことに合意する旨の条項のことです。
第〇条(清算条項)
甲及び乙は、本件に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目のいかんを問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。
離婚協議書に清算条項を設けることで、あなたは相手に対して慰謝料や財産分与などの金銭的な請求ができなくなります。一方で、相手からも金銭的な請求をされるリスクを避けることができます。相手にも同様のメリット、デメリットがあります。
離婚協議書の清算条項の書き方に関する注意点
先ほど示した離婚協議書の清算条項のサンプルはあくまで一般的なもので、実際には、夫婦の実情に沿った内容とする必要があります。
たとえば、離婚後の一切の請求を排除したいのであれば、
- 「本件に関し」という文言を削除する
- (「~請求しない。」)の後に、「また、甲及び乙は、本協議書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。」の文言を付け加える
などの工夫が必要です。
また、離婚の成立だけ先行させて、離婚後に慰謝料や財産分与の請求を考えているときは、そもそも離婚協議書に清算条項を設けないか、設けるとしても次のような条項を設けることが考えられます。
第〇条(清算条項)
甲及び乙は、本件に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目のいかんを問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。ただし、離婚成立後、乙は、甲に対し、別途慰謝料を請求する。
清算条項を設けても離婚後に請求できるケース
離婚協議書に清算条項を設けたとしても、錯誤(勘違い)や詐欺(騙す・騙されたこと)によって清算条項を設けたときは、慰謝料や財産分与を請求することができます。
過去には、「夫が、不倫相手を妊娠させたことを妻に隠し、妻に、清算条項を設けた離婚協議書に署名させた事案」において、妻の合意の意思表示には重要な勘違い(錯誤)があり、当該清算条項は無効だとして、離婚後、妻の元夫に対する慰謝料請求を認めた裁判例(東京地裁平成28年6月21日判決)があります。
清算条項を設けても養育費は請求できる
なお、養育費は親の子どもに対する扶養義務に基づき、子どもが親に対して請求できる権利です。そのため、仮に離婚協議書に清算条項を設けたとしても子どもの養育費の権利がなくなるわけではなく、養育費は請求できると考えられています。
清算条項を設けても年金分割は請求できる
また、離婚協議書に清算条項を設けても年金分割を請求することができます。年金分割を請求する権利は相手に対する権利ではなく厚生労働大臣等に対する権利であって、清算条項を設けたこと(当事者の合意のみ)によって権利を放棄したことにはならないからです。
まとめ
今回のまとめです。
- 離婚協議書の清算条項は、離婚後の金銭の請求をなくすための条項
- 夫婦双方にメリット・デメリットがあるため、設けるか設けないか、設ける場合は文言に細心の注意を払う
- 離婚協議書に清算条項を設けても養育費は請求できる