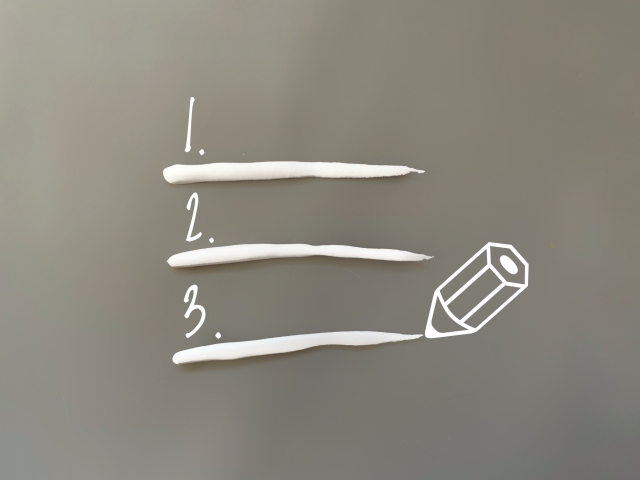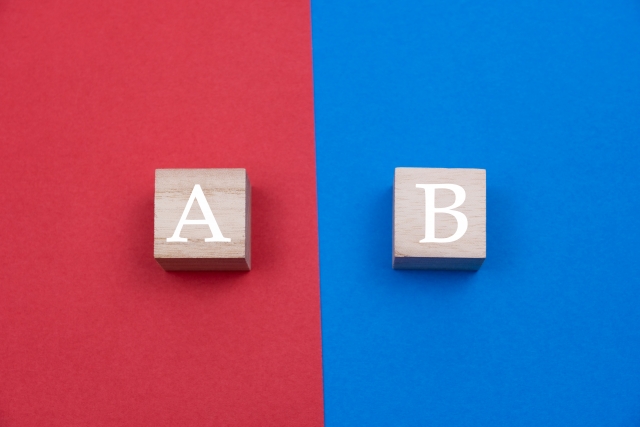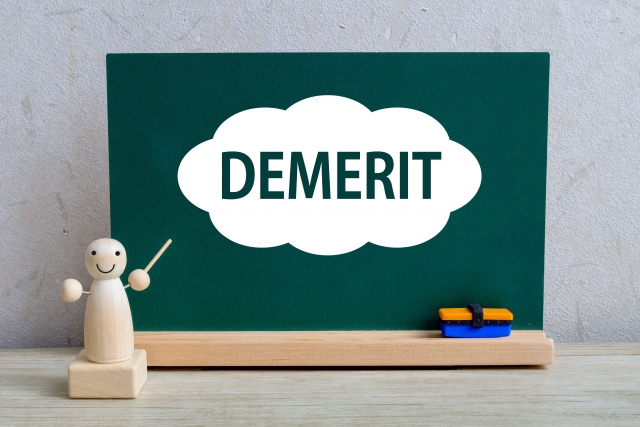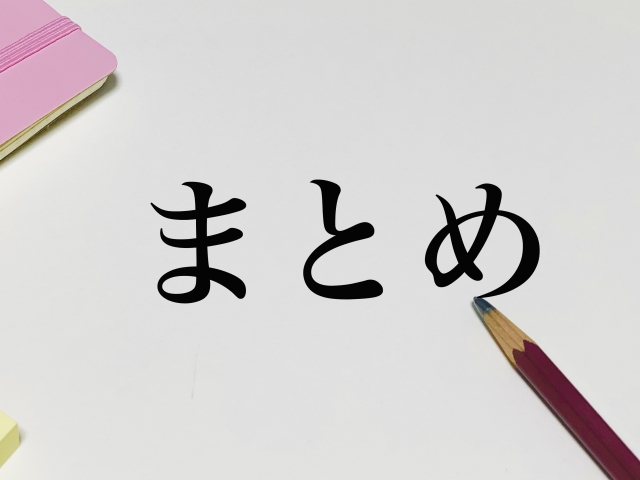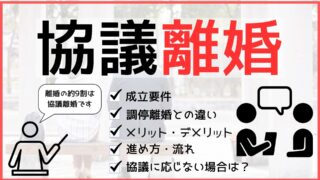
- 協議離婚って何ですか?
- どんな場合に成立しますか?
- 調停離婚との違いは何ですか?
- メリット、デメリットは何ですか?
- どのように進めたらいいですか?
この記事では、こんな疑問、悩みにお応えします。
離婚を思い立ったとき、多くの方がまずは協議による離婚を選択されることと思います。しかし、協議離婚とは何で、どのように進めていったらいいのかわからにという方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、協議離婚とは何か、離婚までどのように進めていったらいいのかなど、協議離婚にまつわる疑問、悩みについて、離婚行政書士が直接解説いたします。
この記事を書いた人

-
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】
- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説
- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します
- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します
協議離婚とは
協議離婚とは、裁判所を介さずに、夫婦の話し合いだけで離婚を成立させる離婚方法の一つです。
離婚の方法には協議離婚のほかに
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判(和解、認諾、判決)離婚
がありますが、唯一協議離婚だけが裁判所を利用しない離婚方法です。
厚生労働省が公表している「令和4年度「離婚に関する統計」の概況P3」によりますと、日本で離婚している夫婦の約9割が協議離婚による離婚を選択しているとのことです。
協議離婚の成立要件
協議離婚で離婚するには、次の要件を満たしていることが必要です。
①夫婦それぞれに離婚意思があること
②親権者について合意していること
③役所に離婚届を提出し受理されること
①夫婦それぞれに離婚意思があること
まず、役所に離婚届を提出する時点で離婚意思がなければいけません。つまり、過去に、離婚に合意していたとしても、役所に離婚届を提出する時点で離婚意思を欠く場合は、協議離婚は無効です。
また、夫婦それぞれに離婚意思があることが必要です。一方の離婚意思を欠く場合は協議離婚は無効です。また、相手の詐欺や強迫によって離婚に合意したときは協議離婚を取り消すことができます(※)。
※無効ははじめから無効ですが、取り消しは取り消されるまで有効、取り消されてはじめて無効という点で「無効」と異なります。
②親権者について合意していること
次に、子どもがいる場合は親権者について合意しておくことが必要です。
離婚届には親権者について書く欄があり、空欄のままでは役所に離婚届を受理してもらえず、協議離婚は成立しません。なお、養育費や面会交流など、親権以外の離婚条件については離婚後でも取り決めることはできますが、できる限り、離婚前に取り決めておいた方が安心です。
③役所に離婚届を提出し受理されること
次に、役所に離婚届を提出し受理されることが必要です。協議離婚独自の要件で、他の離婚方法では役所への離婚届は離婚の成立要件ではありません。
単に離婚届を提出しただけでは足りず、記載内容や必要書類に不備や漏れがないかのチェックを経た上で受理されることが必要です。不備や漏れがある場合、修正しなければ協議離婚は成立しません。
協議離婚と調停離婚との共通点・違い
協議離婚できない場合、次のステップとして調停離婚を目指すことになります。基本的に、調停の手続きを飛ばして、いきなり審判や裁判の手続きに進むことはできません(調停前置主義)。
調停でも話し合いで離婚の合意を目指したり、離婚条件の取り決めをするという点では協議離婚と共通しています。一方、調停には
- 裁判所や法律のルールを守る必要がある
- 調停委員が夫婦の間に入って話をまとめてくれる
- 調停申し立てから成立まで一定期間が必要
- 強制力のある書面が必ず作成される
- 調停成立と同時に離婚が成立する(離婚届の提出は離婚の成立要件ではない)
など、協議離婚とは異なる特徴があります。
関連記事
協議離婚のメリット
協議離婚には次のメリットがあります。
- 手間と時間がかからない
- 費用がかからない
- 話し合いから離婚まで短期間で済ませることができる
- 離婚理由を問われない
- 離婚条件を自由に決めることができる
手間と時間がかからない
まず、手間と時間がかからない(※)ことです。
協議離婚は、夫婦がお互いに離婚することに合意し、子どもがいる場合は親権者を取り決め、役所に離婚届を提出し受理されることで成立させることができます。
親権でもめない場合、親権以外に取り決めることがない場合は、夫婦それぞれが離婚届にサインさえすれば離婚を成立させることができます。
話し合いはいつでも、どこでも、どんな進め方、やり方で行っても自由です。調停や裁判と違って、誰かから話し合いの日時・場所、進め方・やり方を指定されることはありません。
※ただし、話し合いがスムーズに進むことが前提となります。
費用がかからない
次に、費用がかからないことです。
調停、裁判を起こすときは、手数料や郵便切手代など必ずかかる費用があります。一人で手続きを進めることが難しく、弁護士に依頼した場合は弁護士費用がかかります。
一方で、協議離婚で必ずかかる費用はありません。自分たちで話し合いができ、離婚協議書を作る場合も自分たちで作ることができるのであれば、費用はかかりません。
もっとも、離婚公正証書を作る場合は費用がかかります。作成の代理を行政書士などに依頼する場合は、行政書士への費用もかかります。自分たちで話し合いができず、弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかります。
話し合いから離婚まで短期間で済む
次に、話し合いから離婚まで短期間で済む可能性があることです。
先ほど述べたとおり、協議離婚の場合、話し合いの日時や場所、進め方・やり方は自由ですし、親権などの離婚条件について、夫婦で話し合い合意できるのであれば、さほど時間をかけずに離婚することができます。
ただし、相手に話し合いを切り出す前の離婚準備にはしっかりと時間をかけるべきです。準備不足のまま話し合いを切り出すとかえって手間と時間がかかり、なかなか離婚までたどり着けなかったり、話し合い不十分のまま離婚してしまう可能性があります。
離婚理由を問われない
次に、離婚理由を問われないことです。
裁判で離婚を目指すには、相手に法律上の離婚理由があることを指摘し、証拠によって証明する必要があります。また、調停では法律上の離婚理由は必要ありませんが、身勝手な離婚理由だと離婚できなかったり不利な条件で離婚しなければならない場合もあります。
一方、協議離婚ではこれといった離婚理由は問われません。「性格や価値観が合わない」、「これといった理由はないけど離婚したい」、「相手との生活が嫌になった」など、どんな理由であれ、お互いが離婚と離婚条件に合意できれば離婚できます。
離婚条件を自由に決めることができる
最後に、夫婦で合意できれば離婚条件を自由に決めることができることです。
たとえば、養育費の金額を設定するにあたって、調停、裁判では養育費算定表で示された金額に落ち着くことが多いと言われています。慰謝料についても相場と言われている「50万円~300万円」の範囲内でおさまることが多いでしょう。
一方、協議離婚の場合は、算定表や相場は金額を決めるにあたって目安にはするものの、夫婦で合意できる以上は、算定表や相場の金額にとらわれる必要はなく、自由に設定することができます。夫婦で合意できた金額=請求できる金額になります。
協議離婚のデメリット
一方、協議離婚には次のデメリットがあります。
- 相手と話し合わなければならない
- 話し合い不十分のまま離婚してしまう
- 相手が合意しなければ離婚できない
相手と話し合わなければならない
まず、相手と話し合わなければならないことです。
これから離婚という場合、夫婦関係が悪化していることがほとんどだと思います。そうした中での話し合いは精神的に大きな負担ですし、冷静に話し合うことができず話がまとまらない可能性もあります。相手によっては話し合いに応じてくれない可能性もあります。
話し合いが不十分のまま離婚してしまう
次に、話し合いが不十分のまま離婚してしまう可能性があることです。
夫婦で話し合うといっても何について話し合い、何をどう決めなければならないのかわからない、という方も多いでしょう。知識が曖昧なまま話し合いをしても、内容十分な話し合いを行ったとは言い難く、離婚後にトラブルとなるケースも散見されます。
お互いに離婚に合意しなければ離婚できない
次に、お互いに離婚に合意しなければ離婚できないことです。
すでに述べたとおり、離婚届を提出する時点で夫婦双方が離婚に合意していなければ協議離婚は成立しません。もっとも、調停離婚でも同じですから、協議離婚に特有のデメリットというわけではありません。
協議離婚のデメリットを回避するには?
このように協議離婚にはいくつかのデメリットがありますが、次の対策をとることで協議離婚のデメリットを回避できる可能性があります。
- 離婚準備を入念に行う
- 切り出し方、タイミング、場所を工夫する
- 譲歩できるところは譲歩する
- 感情的にならず、建設的な話し合いを心がける
- 第三者を間に入れる
離婚準備を入念に行う
まず、相手に離婚を切り出す前に離婚準備を入念に行うことです。
法律上は離婚前に親権だけを決めればよいことになっていますが、親権以外にも決めるべきことがある場合は離婚前に話し合いをして合意しておくことが望ましいです。
もっとも、そのためには、離婚準備の段階で、ネットや本を見たり、専門家に相談するなどしてできるだけ多く離婚の「正しい」知識を吸収し、相手と話し合うべき内容についてご自分の意見を固めておく必要があります。
相手に離婚を切り出した後よりも切り出す前の方が、内容についてじっくり検討することができます。また、少なくとも夫婦の一方に離婚の知識があれば、充実した話し合いができるようになります。
切り出し方、タイミング、場所を工夫する
次に、話し合いの切り出し方、タイミング、場所を工夫することです。
協議離婚を目指すなら、相手がきちんと話し合いに向き合ってくれなければいけません。相手が不快感を感じたり、反抗したくなりそうな切り出し方、タイミングは避けましょう。一度つまづくと、話し合い自体が難しくなる可能性がありますので注意が必要です。
話し合いの場所はカフェなどの第三者の目が届くような場所にすると、話し合いを冷静にすすめることができるかもしれません。一方、自宅は第三者の目がとどかないこと、実家は公平・冷静な話し合いができないおそれがあることからおすすめできません。
譲歩できるところは譲歩する
次に、譲歩できるところは譲歩することです。
たとえば、当初の養育費の金額を相場より高めに設定する代わりに、学資金・入学一時金等の特別な出費は請求しない、面会交流を認めるが直接の面会は認めず、当分の間、間接交流のみ認める、などです。
話し合いではお互いに譲れない部分も出てくるかと思いますし、絶対に譲れない部分は最初から譲るべきではありません。ただ、あまりに自分の主張に固執しすぎると協議離婚を成立させることが難しくなってしまいます。
協議離婚を目指すのであれば、最終的には一定程度譲歩したり、相手が飲んでくれそうな条件を提示するなどの対応も必要となります。まずは、相手に話し合いを切り出す前に、どの部分が譲れてどの部分は譲れないのかを整理しておくことが大切です。
感情的にならず、建設的な話し合いを心がける
次に、感情的にならず、建設的な話し合いを心がけることです。
感情的になって、これまでため込んできた不満を相手にぶつけたり、相手の話に聞く耳をもたず自分の主張ばかりしていると、相手もこれに対抗しようという気になって同じような態度をとられてしまう可能性が高いです。
離婚に向けた話し合いは、あくまで親権や養育費などの離婚条件に関する話し合いだと割り切り、先の「離婚準備」で準備してきたことを一つずつ着実に実行していくことが求められます。
また、話し合いでは相手の意見にも耳を傾け、意見が共通している部分と違う部分をお互いに確認し合い、違う部分はどうすれば合意できるのかアイデアを出し合うなどして建設的に話し合いを進めていくことが求められます。
お子さんがいる場合は相手から養育費を受け取ったり、面会交流を実施したりと、離婚後も関係が続くことがあるかもしれません。お子さんのことを考えると、離婚前から最低限の礼節を伴った対応は必要といえそうです。
第三者を間に入れる
次に、第三者を間に入れることです。
第三者を間に入れることで相手と話し合わなければならないことによる精神的な負担が緩和され、話し合いに向けてお互いに前向きな気持ちになることは間違いないでしょう。また、感情的にならず冷静に話し合いができることも期待できます。
ただし、誰を間に入れるかは慎重に検討した方がいいでしょう。不適切な人を間に入れるとかえって話がこじれ、協議離婚することが難しくなってしまう可能性があります。一番の適任者は弁護士ですが、高額な費用がかかることがネックとなります。
協議離婚の進め方・流れ
それでは、ここからは、離婚を決心してから協議離婚を成立させるまでの流れを解説していきたいと思います。
①離婚準備を進める【6カ月~1年?】
↓
②相手に離婚を切り出す
↓
③話し合いをする 【数か月~1年?】→別居or調停?
↓
④書面を作成する
↓
⑤役所に離婚届を提出する
①離婚準備を進める
まず、先ほども述べたとおり、離婚を決心したら離婚準備を進めましょう。
協議離婚するといっても、ただ単に離婚に合意し、離婚届にサインして役所に提出すればいいわけではありません。相手が離婚に合意してくれる保障はありませんから、なぜ離婚したいと思っているのか、あらかじめあなた自身の意見を固めておく必要があります。
また、離婚した後安心した生活を送るためには、お金(収入)や離婚後の住まい、子どもの生活ことなどについて、離婚する前から準備を進めておく必要があります。
離婚後は新しい生活に慣れることが精一杯で、様々なことに気を回す余裕などありません。ある程度余裕のある離婚前に準備しておくことをおすすめします(ただし、DVを受けているなど、直ちに避難する必要がある場合は、身の安全を確保することが最優先です)。
離婚準備の期間は人によりますが、多くの方がある程度の期間を必要とするはずです。まずは、離婚準備で必要なことをリストアップし、離婚準備が終わるまでにどれくらいの期間が必要か計算してみましょう。
②相手に離婚を切り出す
離婚準備が終盤に差しかかってきたら、相手に離婚を切り出すタイミングなどを考えます。
この段階までくるとゴール(離婚成立日)が薄っすらと見えてきますので、まずはいつ離婚したいのかゴールを設定しましょう。お子さんがいる場合は、お子さんの転園・転校のタイミングのことも考えておく必要があります。
ただし、離婚を切り出したとしてもすぐに離婚できるわけではありません。話し合い(③)や書面作成(④)が思い通りに進まず予想外に時間がかかってしまうことも予想されます。
③や④にかかる期間は相手対応しだいというところは否めず、あなたがコントロールすることができませんので、期間に余裕をもって切り出した方がよいでしょう。
話し合いをスムーズに進めるためには、タイミングのほかにも、切り出し方、切り出す場所、話し合いの間に入ってもらう人など、様々なことを検討する必要があります。
③話し合いをする
相手に離婚を切り出した後は話し合いをします。
まずは、離婚したいこと、離婚意思が固いこと、離婚したい理由を相手に伝えることに専念します。養育費や財産分与などの離婚条件についてはおいおい話し合っていけばいいです。
しばらく様子をみて、相手が話し合いに応じてくれる場合は離婚条件に関する話し合いを進めます。まずは、あらかじめ考えてきたあなたの意見(離婚条件)を相手に伝え、相手の意見にも耳を傾けながら調整します。
相手にとって寝耳に水の話だった場合は相手の対応までに時間がかかる場合があります。すぐに結論を求めたり、数回で話し合いを終わらせようとしないことが大事です。
相手が話し合いに応じない、離婚に合意しない、離婚条件について話がまとまらない・意見が折り合わないという場合は、別居して冷却期間を設けてみるか、調停を申し立てることを検討します。
④書面を作成する
話し合いで離婚と離婚条件について合意できたら合意内容を書面にまとめます。
協議離婚するにあたって必ず書面を作らなければならないわけではありませんが、作っておけば離婚後に言った・言わないのトラブルに発展することを防ぐことができるでしょう。
合意内容をまとめる書面は、基本的には
- 離婚協議書(合意書)
- 離婚公正証書
のいずれかです。
相手が公正証書の条項に強制執行認諾文言(※)を盛り込むことに同意すれば、離婚公正証書に強制力が付与されます。養育費などの金銭を分割で請求していく旨の合意をしたときは、未払いを防止する観点から離婚公正証書を作っておいた方が安心です。
※「もし、養育費などの金銭の支払を怠ったときは、自分の給与などの財産に対して差押えの手続きをとられてもかまわない」という強制執行の手続きをとられることに同意する旨の文言。相手が同意することで、裁判の手続きを経なくても強制執行の手続きをとることが可能になります。
⑤役所に離婚届を提出する
書面を作った後は、役所に離婚届を提出します。
離婚届を提出する人は夫婦のどちらでもかまいませんが、離婚の効力が発生することによって利益を受ける人、親権について取り決めをしたときは、離婚届の親権者に関する書き換えを防ぐ意味でも親権者となる人が提出した方がよいでしょう。
離婚届には証人2名のサインが必要ですが、証人は夫婦以外の18歳以上の人であれば誰でもなることができます。夫婦それぞれから一人ずつ出す必要はなく、夫婦の一方が二人の証人にサインをお願いしても問題はありません。
離婚協議に応じない、進まない場合の対処法
相手が離婚協議に応じない、離婚協議が思い通りに進まないのには何かしらの原因があります。原因ごとに対応が異なりますから、まずは原因が何なのか考えてみる必要があります。
どう対応しても埒が明かない場合(明きそうにない場合)は
- 別居する
- 離婚調停を申し立てる
- 弁護士に交渉を依頼する
ことなどで対応する必要があります。
協議離婚で困った場合に頼れる専門家
協議離婚は夫婦だけで進めることができますが、困ったときは専門家に相談、依頼してみるのも一つの方法です。
弁護士
まず、多くの方が離婚の専門家として思い浮かぶのが弁護士ではないでしょうか?
弁護士には、相手との話し合いから書面の作成まで、すべてを任せることができます。また、法律のプロ中のプロであるため、難しい法律問題に直面している場合は、弁護士に依頼すべきでしょう。
もっとも、最大のネックは多額の費用がかかることです。法テラスの制度を利用することができれば少しは負担軽減につながりますが、所得制限等があり、誰でも利用できるわけではありません。
弁護士に依頼する前に費用を負担してまで得られるリターンがあるかどうかはしっかり検討しておく必要がありそうです。
行政書士
次に、行政書士に相談、依頼することも考えられます。
法律上、行政書士は弁護士のように依頼者の代わりに相手と話し合うことはできませんが、依頼者の代わりに離婚協議書を作ったり、離婚公正証書の作成手続きをとることは可能です。
相手との話し合いはご自分で行っていただく必要があるため、行政書士に依頼できるのはあくまで相手との話し合いができることが前提となります。
一方、話し合いができるのであれば行政書士に相談、依頼することを検討してみてもよいでしょう。行政書士からアドバイスを受けながら離婚協議書などの書面を作っていくことができます。
関連記事
まとめ
今回のまとめです。
- 協議離婚は、裁判所を介さずに、夫婦の話し合いで離婚する離婚方法の一つ
- 離婚と離婚条件に合意し、離婚届が受理されれば協議離婚が成立する
- 協議離婚と他の離婚方法との一番の違いは裁判所を利用するかどうか
- 協議離婚にはメリットもあればデメリットもある
- 協議離婚のデメリットを回避する工夫をして、協議離婚を目指すことができる
- 協議離婚を目指すなら、まずは離婚準備が重要
- 離婚協議に応じない、進まないときは専門家に相談、依頼するのも一つの方法