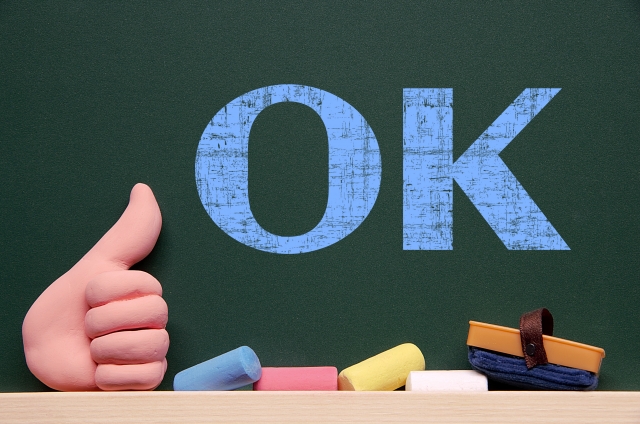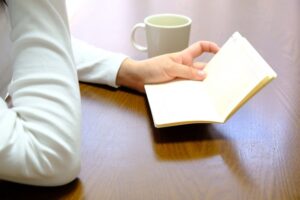- 離婚後に養育費を請求することはできますか?
- 離婚前に養育費を放棄していた場合は請求できますか?
- 過去の養育費を払ってもらうことはできますか?
- 養育費は時効にかかりますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
子どもがいて離婚する場合は、できる限り、離婚前に養育費などの離婚条件について取り決めておくことが理想です。
しかし、あえて離婚を先行させ、離婚後に養育費について話し合うことにした方、あるいは養育費は請求しないことにしていたものの、離婚後に請求する必要が出てきた方など、様々な事情を抱えている方も多いと思います。
そこで、今回は、離婚後に養育費を請求できるのか、離婚前に養育費を放棄していたときでも請求できるのか、過去の養育費は請求できるのか、といったことについて解説していきたいと思います。
この記事を書いた人

-
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】
- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説
- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します
- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します
離婚後も養育費の請求は可能?
結論から申し上げると、離婚後も養育費を請求することは可能です。養育費は親の子どもに対する扶養義務を根拠に親が負担しなければならない費用で、扶養義務は離婚したからといって免除されるわけではないからです。
離婚前に養育費に関する具体的な取り決めをしていなかったとしても、子どもが一人の大人として自立して生活してけるまでの間は、離婚から何年経過していても養育費を請求することができます。
離婚前に養育費を放棄していたら?
では、離婚前に「養育費はいらない」といって請求を放棄していたものの、離婚後に養育費を請求したいとなった場合に養育費を請求することはできるのでしょうか?
この点、まず、相手が養育費を払うことに合意するのであれば払ってもらうことは可能です。一方、相手が合意しない場合はまずは調停を申し立てて調停で話し合うことになりますが、調停では、養育費を請求しない合意をしたときの状況と離婚後の状況とを照らし合わせて夫婦双方が予測できなかった「事情の変化」があったと認められれば請求が認められる可能性があります。
たとえば、
- 養育費を請求しない合意をしていたところ、離婚のとき無職だった父親がその後就職した(大阪家庭裁判所審判平成元年9月21日)
- 離婚のときは自分の収入だけでできると思い養育費を請求していなかったところ、離婚後に会社の倒産によって失業した
といったケースです。
なお、養育費に含まれる子どもの扶養料を親が勝手に放棄することはできませんから、離婚前に養育費を放棄していたとしても、子どもの扶養料分のお金は相手に請求することができます。
離婚後に養育費を請求する手順
離婚後に養育費を請求する手順は基本的には離婚前と同じです。
①請求内容を考える
→請求内容:金額、請求期間、毎月の支払期限、支払方法 など
↓
②話し合い → 合意 → ③公正証書の作成
↓
不合意
↓
④調停の申立て
すなわち、相手に話し合いを切り出す前に、養育費算定表を使うなどして相手に請求したい金額のほか、請求期間や毎月の支払期限、支払方法(受け取り方)を考えておきます(①)。
あなたの考えがまとまったら相手に話し合いを切り出し(②)、話がまとまったら相手の合意を得た上で公正証書を作成します(③)。相手に直接話し合いを切り出すことに抵抗があるという方は、文面に注意しつつLINEや手紙などで切り出してみてもよいでしょう。手紙などの書面を送るときは、相手が住んでいる場所を把握していく必要もあります。
もっとも、LINEや手紙などで切り出したとしても、最終的には相手との話し合いが必要になります。相手と直接話し合う自信がない場合は弁護士など適切な第三者に間に入ってもらうことも検討しましょう。相手が話し合いに応じない、話がまとまらないという場合は養育費請求調停を申し立てて調停での解決を目指します(④)。
過去の養育費を払わせることはできる?
離婚後に養育費を請求する場合、たとえば次のように、将来ではなく過去の養育費を払ってもらえないか疑問に思われる方もいます。相手に過去の養育費を払ってもらえるかどうかは、離婚時に養育費の取り決めをしていたかどうかで考え方が異なります。
【令和4年2月1日】・・離婚(養育費請求なし)
↓
【令和5年2月1日】・・養育費請求
Q 令和4年2月1日~令和5年2月1日までの1年分の養育費は請求できる?
離婚時に養育費の取り決めあり
まず、離婚のときに離婚協議書や公正証書、調停調書などに養育費の取り決めを盛り込んでいる場合は過去の養育費を請求することは可能です。養育費の未払いが続いているときは、これまでの経緯や相手の反応を予測して適切な対応をとる必要があります。
離婚時に養育費の取り決めなし
一方、離婚のときに取り決めをしていなかった場合は、相手が過去の養育費を払うことに合意すれば払ってもらうことは可能です。金額などについて話し合い、公正証書を作っておきましょう。
一方、相手が合意しない場合は調停を申し立てて調停で話し合っていくことになりますが、裁判所は相手に過去の養育費を払わせることには消極的です。
養育費を受け取らなくても生活できたとみられる可能性があること、請求期間によっては、莫大な金額となり、相手にとって過大な負担になりうることなどが理由です。
相手の合意が得られない場合は、請求した時点以降の養育費の支払いしか認められない可能性が高いため、養育費が必要と感じたときははやめに調停を申し立てることが大切です。
離婚後の養育費と時効
「養育費の時効は5年」などと見たり聞いたりしたことがある方もおられるかもしれませんが、養育費に時効が関係するのはあくまで、離婚のときに養育費の取り決めをしていた場合です。
協議離婚で養育費の取り決めをしていたときは、請求期限が到来した日の翌日から5年で時効が完成します。調停以降の手続きで養育費の取り決めをしていたときは、請求期限が到来した日の翌日から10年で時効が完成します。また、請求期限が到来した養育費を10年間請求せずにそのまま放置しておくと、養育費を請求する権利そのものが時効で消滅してしまいます。
一方、離婚のときに養育費の取り決めをしていなかった場合はそもそも養育費を請求する権利が発生していませんので時効は関係ありません。冒頭で述べたように、子どもが一人前の大人になるまでは養育費を請求することができます。もっとも、先ほど述べたとおり、過去の養育費は相手が支払いに合意しない限り払わせることが難しいと考えられますので、養育費が必要と感じた時点ではやめに調停を申し立てるなどして請求しておくことが大切です。
まとめ
今回のまとめです。
- 離婚後でも養育費を請求することはできる
- まずは話し合い、話し合いが難しいときは調停で請求する
- 相手が合意すれば過去の養育費を払ってもらえるが、調停で払わせることは難しい
- 離婚前に養育費の取り決めをしていなかった場合は時効は気にしなくていい