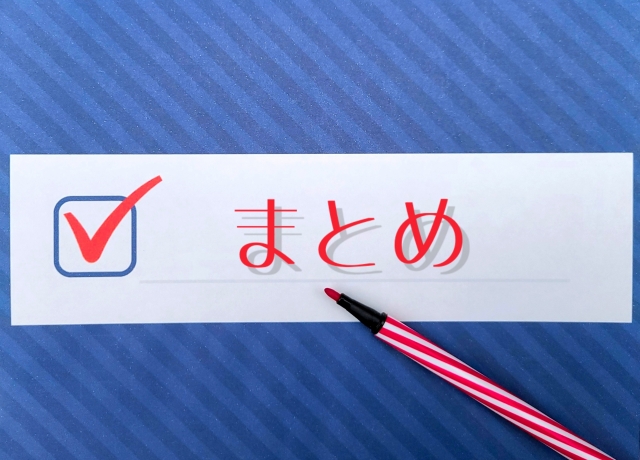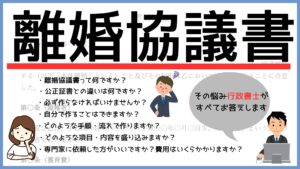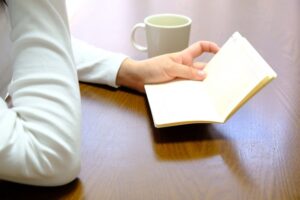- 相手の養育費の減額請求に応じた方がいいケースとはどんなケースですか?
- 反対に、応じてはいけないケースとはどんなケースですか?
- 養育費の減額請求に応じる場合、どのような手順を踏めばいいですか?
この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えします。
一度養育費について取り決めをしたとしても、相手(以下、養育費の支払義務を負う人という意味で「義務者」といいます。対して、養育費の受け取る権利のある人を「権利者」といいます。)から養育費の減額請求を受けることがあります。ただ、減額請求に応じるべきかどうか、応じるとしていくら応じるべきか判断に迷う方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、養育費の減額請求に応じるか否かの基準をご紹介した上で、相手の減額請求が認められやすいケース、反対に認められにくいケース、減額請求されたときの対処法などについて解説していきたいと思います。
この記事を書いた人

-
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】
- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説
- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します
- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します
養育費の減額請求に応じるか否かの基準
養育費の減額請求に応じる否かの基準は次のとおりです。
① 養育費の取り決めをした後に「事情の変更」が生じたこと
② 事情の変更が重要な事情の変更といえること
③ 取り決めをしたとき、当事者が事情の変更を予測することができなかったこと
④ 事情の変更が生じたことについて当事者に責任がないといえること
今の養育費の条件について取り決めるときに、権利者も義務者も予測することができた事情がある場合は、その事情を踏まえて今の養育費の条件を決めたはずですから、事情の変更は取り決めをした後に生じたものでなければいけませんし、生じた事情は権利者も義務者も予測することができなかった事情でなければいけません(①、③参照)。
また、さほど重要でない事情や義務者の身勝手な理由による養育費の減額を認めてしまうと、権利者や子どもの権利を害することになりかねません。したがって、変更が生じた事情は重要な事情である必要がありますし、事情の変更が生じたことについて義務者に責任がないことが必要となります(②、④参照)。
養育費の減額(免除)請求が認められやすい事情の変更
では、どんな事情の変更が生じれば養育費の減額(免除)請求が認められてしまうのでしょうか?ここからは養育費の減額請求が認められやすい重要な「事情の変更」をご紹介していきます。なお、重要な事情の変更が生じたとしても先ほどの基準をすべてクリアしなければ減額請求は認められません。
義務者の再婚
まず、義務者の再婚です。
単に再婚しただけでは減額請求は認められませんが、
- 義務者の再婚相手が子育て、病気、怪我などの理由でやむを得ず働けない
- 義務者が再婚相手との間に子どもをもうけた
- 義務者が再婚相手の子どもと養子縁組した
という場合は減額請求が認められる可能性があります。
権利者の再婚
次に、権利者の再婚です。
子どもと再婚相手が養子縁組した場合は再婚相手が子どもに対して第一次的な扶養義務を負うという考え方があり、義務者の養育費の支払義務が免除される可能性があります。また、養子縁組しない場合も、再婚相手が子どもの養育を引き受けている実態が認められる場合には養育費の減免請求が認められる可能性があります。
義務者の収入減
次に、義務者の収入減です。
会社の倒産、会社経営の悪化・人員整理などによる解雇などによって失職、転職し収入が減った、大病、大怪我などによって休職し収入が減ったという場合は減額請求が認められる可能性が高いです。
権利者の収入増
次に、権利者の収入増です。
養育費の金額を決めるにあたっては権利者と義務者の収入も考慮されます。就職、転職などによって養育費を取り決めたときより権利者の収入が増えれば、その分義務者が払う養育費は減額される可能性があります。
養育費の減額(免除)請求が認められにくい事情の変更
一方、養育費の減額(免除)請求が認められにくい事情の変更は次のとおりです。
義務者の再婚相手が働いている、働ける
まず、義務者の再婚相手が働いて収入を得ている場合や、今現在働いていていなくても働くことに支障がない場合(潜在的稼働能力がある場合)は減額請求は認められにくいです。
義務者・権利者の再婚
次に、単に義務者、あるいは権利者が再婚したというだけでは養育費の減額(免除)請求は認められません。ただし、先ほど述べたとおり、事情によっては減額(免除)請求が認められる可能性があります。
義務者の勝手な都合
次に、ギャンブルなどによる浪費で養育費に充てるお金がない、自己都合による退職・転職で収入が減ったなど、義務者の勝手な都合による養育費の減額請求は認められない可能性が高いです。また、義務者が自己破産しても養育費の支払義務は免除されません。
子どもに会えない
次に、義務者が子どもに会えないことを理由に養育費を払わないとすることも認められません。面会交流と養育費は子どものためのものですので、両者を交換条件としてはいけません。
養育費の減額請求されたときの対処法
ここからは義務者から養育費の減額請求されたときの対処法を解説します。
①話し合いをする
まずは、話し合いをすることです。
相手の話に耳を傾け、相手が養育費の減額請求する理由を聞きましょう。相手の話を聞かず一方的に請求を拒否すると、勝手に減額されたり、支払いを打ち切られてしまう可能性があります。
仮にそうなった場合、強制執行の手続きをとらなければならなかったり、相手の調停の手続きを踏んだりと、手間と時間をとられてしまう可能性がありますので、慎重な対応が求められます。
相手の話を聞き、減額の理由が上の基準をクリアする場合は、いくら減額するのかについて話し合います。いくら減額するのかはケースにより異なりますので、以下、ケースごとに解説します(※)。一方、基準をクリアしない場合は「あなたの理由は上の基準を満たさない」といって請求を拒否しましょう。
※権利者、義務者の年収が変われば異なる結論となることもあります。
義務者が再婚/再婚相手は無職/義務者と再婚相手との間の子ども1人(0歳)/の場合
このケースでは養育費の減額請求に応じなければならない可能性が高いでしょう。また、子どもの年齢からすると再婚相手の潜在的稼働能力(働こうと思えば働くことができる能力)はなく、養育費の算定表上、再婚相手は0歳~14歳の子どもと同じ扱いとなります。仮に、権利者と義務者との間の子ども(3歳)が1人だったという場合、減額前は「(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)」の算定表を使って養育費の目安としていたところ、減額後は「(表6)養育費・子3人表(第1子、第2子及び第3子0歳~14歳)」の算定表から割り出される養育費の3分の1まで減額される可能性があります。
義務者が再婚/再婚相手に収入あり/義務者と再婚相手との間の子ども1人(0歳)/の場合
この場合も養育費の減額請求には応じなければならないかもしれません。もっとも、上のケースとは異なり、再婚相手には収入があるため、再婚相手を0歳~14歳の子どもと同じ扱いとすることは相当ではありません。仮に、算定表上の子どもの数を再婚相手分1人減らしたとすると、減額後は「(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」の算定表を使い、養育費は2分の1までにしか減額されないため、上のケースよりも減額幅は小さくなるか、再婚相手の収入しだいでは減額に応じなくてもよくなるかもしれません。
権利者が再婚/再婚相手に収入あり/権利者に(義務者との間の)子どもあり/の場合
先ほど述べたとおり、子どもと再婚相手とが養子縁組をしている場合は、再婚相手が子どもに対して第一次的な扶養義務を負いますので、基本的には義務者に対して養育費を請求することができなくなります。一方、養子縁組しない場合は、これまでどおり権利者と義務者だけが子どもに対して扶養義務を負いますので、権利者と義務者の年収だけで減額後の養育費を考えることになります。減額後の養育費を考えるにあたって再婚相手の収入は考慮しません。
②公正証書を作成・変更する
減額する養育費の金額について合意できた場合は合意内容を書面に取りまとめ、公正証書を作成する手続きをとりましょう。全国どこの公証役場でも手続きをとれますが、代理で任せない限り、最終的には二人とも公証役場へ足を運ぶ必要があります。
すでに公正証書を作っている場合は新しい公正証書を作り、その公正証書で前の公正証書の内容を変更する手続きをとります。この場合も全国どこの公証役場でも手続きがとれます。なお、公正証書を作成・変更するには、相手の同意が必要です。
③調停を申し立てる
一方、そもそも話し合いができない、話がまとまらないという場合は義務者から養育費請求(減額)調停を申立てられることが考えられます。
減額調停では、調停委員が当事者の間に入って話をまとめてくれますので、話し合いがスムーズに進む可能性があります。また、裁判所から相手に資料の提示を促してもらったり、調査嘱託をかけて相手の収入等を調査してもらうこともできます。
調停や審判では、より厳格に冒頭で述べた基準を満たすかどうかが判断されます。減額請求を拒否する場合は、調停委員に基準を満たさないことを裏付ける事実関係を主張、立証していくことが求められます。
なお、調停が不成立となった場合は、自動的に「審判」という手続に移行します。審判では、これまでの経過を踏まえて、裁判官が養育費の減額請求を認めるか否か、認めるとしていくら減額するかを判断します。
養育費の支払いを一方的に打ち切られたら?
相手が養育費を減額してくれないか話をもちかけてくるならまだしも、はじめから、あるいは話し合いの途中から、養育費の支払いを打ち切ってくることも考えられます。その場合は、まだ前の取り決めの効力が残ったままですので、前の取り決めの内容を請求し続けることができますが、相手が養育費の支払いに応じないときは次の対応をとることも検討しなければいけません。
公正証書を作っている場合
すでに公正証書を作っている場合は相手の財産を差し押さえる手続き(強制執行)をとることを検討します。
調停で話し合ったことがある場合
調停で養育費について話し合ったことがある場合は裁判所に履行勧告、履行命令を出してもらうことができます。また、公正証書と同じく、強制執行の手続きをとることもできます。
口約束で終わらせている場合
口約束で終わらせてしまい公正証書を作っていない、調停の手続きをとっていないというときは、内容証明で養育費の支払いを請求し、それでも応じない場合は養育費請求調停、あるいは審判を申し立てることを検討します。
まとめ
今回のまとめです。
- 養育費の減額請求は一定の場合に限って認められる
- 養育費の減額請求を受けたら、話し合い→調停の流れで取り決める
- 養育費の支払いを打ち切られたら現状に応じた対応をする