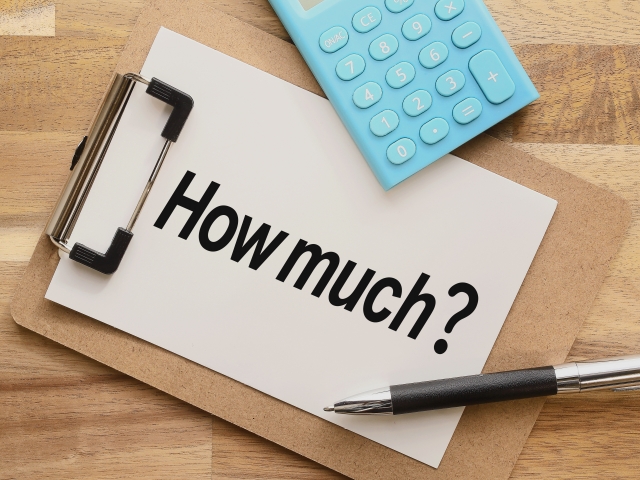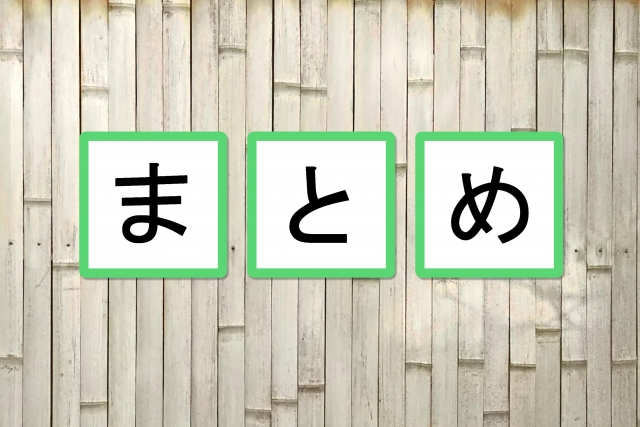- 離婚の弁護士費用ってどのくらいかかりますか?
- 弁護士費用の相場はいくらですか?
- 費用を安くするコツはありますか?
- 払えない場合は、依頼を諦めるしかありませんか?
この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えします。
これから離婚するにあたって話し合いは避けては通れない道です。しかし、そもそも相手が話し合いに応じてくれない、感情がぶつかりあって冷静に話し合うことができない、相手と一対一で話し合う自信がない。こうした問題に直面する方も少なくありません。
そこで、頼りになる専門家が弁護士ではないでしょうか?弁護士は離婚の専門家の中でも唯一、依頼者の代わりに相手と交渉したり、調停や裁判の手続きを行える権限をもっています。
もっとも、最大のネックは弁護士費用です。弁護士費用が高いという漠然としたイメージはもっていても、具体的にいくらかかるのかわからず、弁護士に依頼することを躊躇されている方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、法律事務所での勤務経験がある筆者が、離婚の弁護士費用の内訳や相場、弁護士費用を少しでも安くする方法、弁護士費用を払えない場合の対処法などにについて詳しく解説していきたいと思います。
この記事を書いた人

-
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。※大変申し訳ありませんが、ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しております。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】
- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説
- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します
- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します
離婚の弁護士費用の内訳
まず、離婚の弁護士費用は次の内訳から構成されてことを知っておく必要があります。なお、内訳や内訳ごとの費用は各法律事務所によって異なります。相談の際や契約前にしっかり確認しておくことが大切です。
- 法律相談料
- 着手金
- 成功報酬金
- 日当費
- 実費
法律相談料【無料~】
法律相談料は弁護士に依頼する前に、弁護士に法律相談した際にかかる費用です。
近年は「無料」で対応する法律事務所も増えていますが、回数や1回あたりの法律相談の時間に制限が設けられていることが多いため、弁護事務所のホームページなどで確認が必要です。一方、「有料」の場合は30分~1時間あたり「5,500円~11,000円(税込)」が相場です。弁護士に正式に依頼した後は、相談の都度、法律相談料が発生することはありません。
着手金【11万円~】
着手金は、弁護士に依頼した(弁護士事務所と委任契約を取り交わした)後、弁護士が弁護活動に着手するために必要な費用です。
弁護士に依頼しても着手金を払わないと弁護活動を始めてくれないことが多く、弁護活動の成果の善し悪しに関わらず返金されない点にも注意が必要です。着手金は一括払いが基本ですが、中には分割での支払いにも対応してくれる事務所もあります。
金額は協議離婚→調停離婚→裁判離婚と進むにつれ高くなります。協議離婚の着手金は「11万円~22万円(税込)」、調停離婚の着手金は「22万円~33万円(税込)」、裁判離婚の着手金は「33万円~44万円(税込)」が相場です。
たとえば、協議から依頼したものの協議離婚が成立せず調停も依頼した、調停から依頼したものの調停離婚が成立せず裁判も依頼したという場合は、着手金の差額を請求されることがあります。
成功報酬金【成果による】
成功報酬金は、弁護活動の成果に応じて発生する費用です。
成功報酬金は
- 基礎(固定)報酬金
- 追加報酬金
の2階建てとされているのが一般的です。
基礎(固定)報酬金は、たとえば、「離婚できたら○○万円」、「離婚を阻止できたら○○万円」などと固定の報酬金が設定されており、費用は「11万円~33万円(税込)」が相場です。
一方、追加報酬金は、金銭に関する離婚条件(※)については「得られた利益(額)の○○%」と設定され、「10%前後」が相場です。金銭に関わらない離婚条件(※)については「○○万円」と固定の金額が設定され、費用は「11万円~22万円(税込)」が相場です。
※金銭に関する離婚条件:婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与 など
金銭に関わらない離婚条件:親権、面会交流、年金分割
日当費【弁護活動による】
日当費は、弁護士が事務所外で弁護活動を行った際に発生する費用です。
日当費は、弁護士の半日拘束で「○○万円」、1日拘束で「○○万円」と固定の金額が設定されることが多く、半日拘束は「3万3,000円~5万5,000円(税込)」、1日拘束は「5万5,000円~11万円(税込)」が相場です。弁護士が事務所外で行う活動の回数が多く、活動の時間が長くなればなるほど日当費は高くなります。
実費【弁護活動による】
実費は、たとえば、
- 相手や裁判所に文書を発送するための郵送費(切手代)
- 弁護士が話し合いの場や裁判所に行く際にかかる交通費
- 調停の申立て、訴訟提起の際に必要な収入印紙代、郵便切手代
など、弁護活動によって実際にかかった費用です。
【離婚方法別】離婚の弁護士費用の相場
次に、離婚の弁護士費用の相場を、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つのケースにわけてみていきましょう。なお、弁護士費用は依頼する法律事務所や、弁護活動の成果、弁護活動の内容などによって大きく変動します。以下で提示する金額は「成功報酬金」は加味されていませんので、あくまで目安としてお考えください。
協議離婚の場合【22万円~66万円】
協議離婚の場合は「22万円~66万円(税込)」が相場です。
先ほど述べたとおり、3つの離婚方法の中では着手金が安い上、弁護士が事務所外で活動する必要がないことが多く、日当費や実費を安く抑えることができる分、トータルの弁護士費用を安く抑えることができます。
もっとも、慰謝料などのお金に関して合意し、かつ、その金額が大きい場合などは成功報酬金が高くなり、トータルの弁護士費用も高くなる可能性があります。
調停離婚の場合【44万円~88万円】
次に、調停離婚の場合は「44万円~88万円(税込)」が相場です。
着手金は協議離婚よりも高くなります。裁判所(調停)での活動が必要となるため、日当費・実費がかかります。調停が1回で終わることは少なく、弁護士が調停に出席する回数が多くなればなるほど、日当費、実費が高くなります。事務所によっては日当費は着手金に含まれていることもありますが、着手金が高額に設定されている可能性がありますし、事務所外での活動回数が一定数を超えると費用を請求されます。
裁判離婚の場合【77万円~】
次に、裁判離婚の場合は「77万円~(税込)」が相場です。
裁判離婚は3つの離婚方法の中で最も紛争性、専門性が高い手続きですから、着手金は一番高くなります。また、裁判の回数が多くなればなるほど弁護士が裁判に出廷する回数が多くなり、日当費、実費も高くなります。調停と同様に、日当費は着手金に含まれていることもありますが、着手金が高額に設定されている可能性がありますし、事務所外での活動回数が一定数を超えると費用を請求されます。
離婚の弁護士費用を安くするコツ
ご想像のとおり、「弁護士費用は高い」、「安くはない」ということはおわかりいただけたかと思います。しかし、本来弁護士に依頼すべきなのに、弁護士費用が高いという理由だけで依頼を諦めて欲しくはありません。そこで、以下では、離婚の弁護士費用を少しでも安く抑えるコツをご紹介していきたいと思います。
複数の法律事務所の費用を比較検討する
まず、可能な限り、複数の法律事務所で(無料)法律相談し、費用を比較検討してみることです。
まずは、ネット上で、気になる法律事務所を複数ピックアップし、ホームページに書かれてある情報をもとに費用を比較検討してみましょう。検討するうちに、どこの事務所が弁護士費用が安くて、どこの事務所が高いのかがみえてくるかもしれません。
ただし、ホームページのみでは正確な情報を入手することはできません。さらに詳細な情報を入手するには、法律事務所に法律相談を申し込み、弁護士や事務所の担当者に気になることを直接尋ねることが一番です。
自分と相性のあった弁護士、事務所を選ぶため、弁護士費用が安い事務所を選ぶためには、できる限り複数の法律事務所を訪ね相談してみることをおすすめします。
相手に離婚を切り出す前に弁護士に依頼する
次に、相手に離婚を切り出す前に弁護士に依頼することです。
「【離婚方法別】離婚の弁護士費用の相場」でもご紹介したように、離婚の弁護士費用は協議離婚→調停離婚→裁判離婚と進むにつれて高くなります。
相手に離婚を切り出したものの、相手が話し合いに応じてくれない、話がこじれて話し合いが思うように進まなくなったという場合は調停、裁判での離婚を検討する必要がありますが、その段階で弁護士に依頼しても費用が高くなります。
弁護士費用を出し惜しみして弁護士への依頼が遅れると、結局は高い費用を払わざるを得なくなる目に遭うかもしれません。離婚を思い立ったら、相手に離婚を切り出す前に弁護士に相談、依頼することが大切です。
法テラスを利用する
最後に、法テラス(日本司法支援センター)を利用することです。
法テラスは「誰もが、いつでも、どこでも、弁護士などの法律の専門家によるサービスを受けることができるように」との理念のもとに平成18年に設立された公的機関です。
法テラスの援助制度には「法律相談援助」と「代理援助」があります。法律相談援助では、1回30分の法律相談を3回まで無料で受けることができます。代理援助では、弁護士が依頼者の代わりに相手と交渉したり、調停や裁判の手続きを代行してくれ、弁護士費用を法テラスがいったん立て替え、後日、分割で法テラスに返済していくものです。生活保護受給の方には返済の猶予、免除制度も用意されています。ただし、援助制度を利用するには資力が一定以下などの一定の利用条件をクリアすることが必要です。
援助制度を利用する方法は法テラスに直接申し込むか、法テラスに対応している事務所(弁護士)に依頼するかです。無料法律相談の際に法テラスに対応しているかどうか尋ねてみるとよいでしょう。
参照:法テラス
離婚の弁護士費用の注意点
離婚の弁護士費用に関する注意点は次のとおりです。
費用によって支払うタイミングが異なる
まず、費用によって支払うタイミングが異なることです。
- 法律相談料 → 依頼前、相談後
- 着手金 → 依頼直後
- 報酬金 → 弁護活動終了後
- 日当費 → 弁護活動終了後
- 実 費 → 弁護活動終了後
となります。
弁護士に依頼した後は、まずは着手金を請求され、弁護活動終了後に報酬金、日当費、実費の合計を請求されるのが基本です。あるいは、はじめに着手金を支払い、弁護活動終了後に着手金と報酬金・日当費・実費の合計額とを精算し、あまった金額は返還され、足りなかった金額は追加で請求する形をとる事務所もあります。
離婚の弁護士費用は自己負担
次に、弁護士費用は原則自己負担(※)としましょう。
自分で弁護士に依頼すると決めた以上は、自己負担が原則です。相手のせいで離婚することになったからといって、自分で依頼した弁護士の費用を相手に負担させることは原則できません。
なお、離婚裁判を提起し、かつ、判決に至る場合は、相手に損害額の1割程度を払うよう請求することはできますが、そもそも離婚裁判を提起すること自体稀ですし、仮に提起してもそこからさらに判決に至ることは稀です。
また、相手との交渉で請求する方法もありますが、実際に払ってもらえるのは、不倫やDV事案など相手の有責性が大きい場合、相手が積極的に離婚を望んでいる場合などのケースに限定されます。
※弁護士費用は個人の財産から支出した方が安心です。夫婦の共有財産から支出すると、あとでもめる原因にもなりかねませんので注意が必要です。
安い=いい弁護士、法律事務所とは限らない
最後に、弁護士費用が安い=いい弁護士、法律事務所とは限らないということです。
弁護士選びで最も重要視すべきポイントは、どれだけ弁護士が離婚問題に精通しているのかという「専門性」と、弁護士との話しやすさ、つまり「相性」です。
その専門性・相性と弁護士費用との間には相関関係はありません。つまり、弁護士費用が安く、専門性が低く、相性が悪い弁護士もいれば、多少弁護士費用は高くても、専門性があり、相性の合う弁護士もいるということです。
どれほど専門性があるのか相性が合うのかは、実際に会って話してみないとわからないこともあります。弁護士を探す際は弁護士費用だけに目を奪われず、専門性や相性にも着目していただければと思います。
行政書士への依頼も検討を
離婚の専門家は弁護士以外にも行政書士(※)がいます。行政書士は弁護士と異なり、依頼者の代わりに相手と交渉したり、裁判の手続きを行うことはできませんが、依頼者からよく話をうかがった上で夫婦が希望される内容の離婚協議書や離婚公正証書の原案を作ることができます。
行政書士に依頼するには、夫婦で話し合いができることが前提となりますが、逆にいえば、夫婦で話し合いができるのであれば弁護士ではなく行政書士に依頼することを検討されてもいいかもしれません。弁護士と同じく費用は発生しますが、弁護士ほど費用はかからないため、依頼のハードルは低いのではないかと思います。
※司法書士、税理士の中にも離婚分野を取り扱っている方がおられますが、行政書士に比べて割合は少ないです
まとめ
今回のまとめです。
- 弁護士費用は法律相談料、着手金、成功報酬金、日当費、実費から構成されます
- 離婚の弁護士費用は協議→調停→裁判と進むにつれ高くなります
- 弁護士費用を安く抑えるには「複数の事務所に相談する」、「相手に離婚を切り出す前に弁護士に依頼する」、「法テラスを利用する」ことが考えられます
- 弁護士を選ぶ際は費用だけではなく専門性や相性にも着目してください
- 夫婦で話し合えるなら行政書士への依頼も検討してみましょう