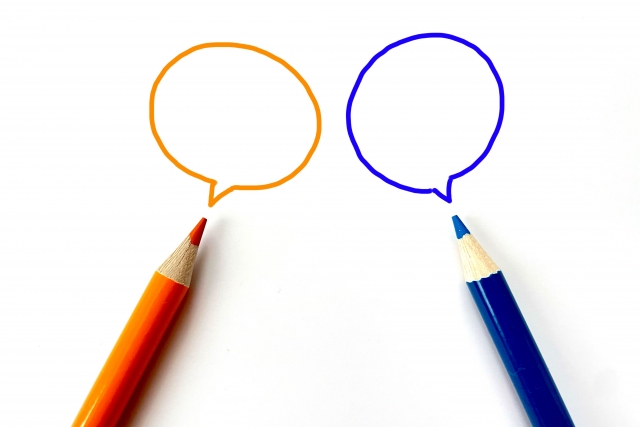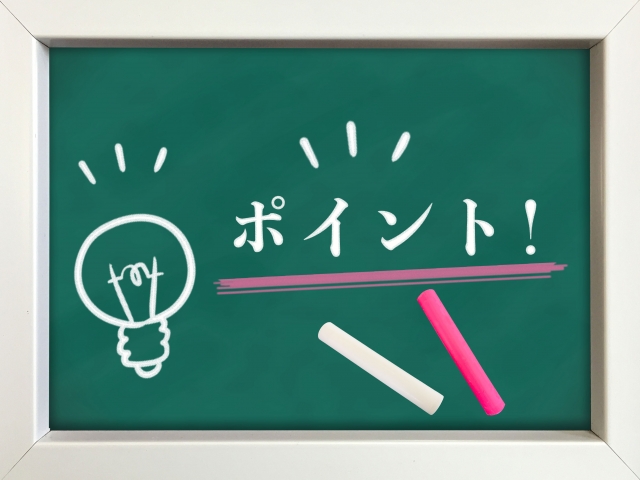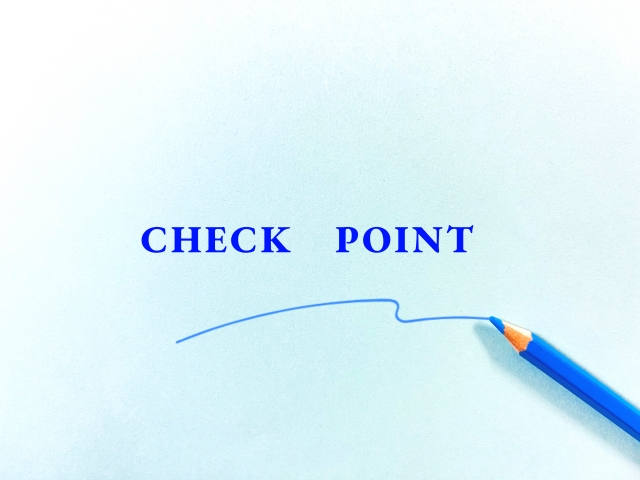- 親権とはどんな権利ですか?
- 何歳まで有効ですか?
- 離婚するときの決め方がわかりません
この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えします。
今現在、離婚後は父母のいずれかを親権者と決めなければならない単独親権の法制度がとられています。そのため、父母それぞれが親権を奪われまいと対立し、離婚成立まで時間がかかってしまうケースも多く見受けられます。
一方で、2024年(令和6年)の法改正により、2026年(令和8年)5月までの政府が定めた日以降は、離婚後でも共同親権を選択できるようになります。これにより、上記のような対立も少しは減るのではないかとも考えられています。
今回は、こうした親権にかかわる知識を一挙に解説していきたいと思います。関連記事とあわせてお読みいただければ、親権に関する必要な知識を身につけることができますので、ぜひ最後までお読みいただき今後の参考にしていただければと思います。
この記事を書いた人

-
※ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しています。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025年11月30日示談書不倫慰謝料請求を内容証明でする方法
- 2025年11月28日示談書不倫慰謝料の時効は何年?
- 2025年11月28日示談書不倫相手の住所の調べ方
- 2025年11月27日示談書不倫相手との話し合いを進めるためのコツは?
親権とは
親権とは、親が未成年者(18歳未満の子)の子育てや教育を行ったり、子どもの財産を管理する権利義務をいいます。
親権と聞くと「親が子どもをしつける権利」というイメージをもたれる方も多いと思います。しかし、親権は、あくまで子どもの利益を守るために行使されなければならないものなのです。
親権は「身上監護権」と「財産管理権」から成る
親権は身上監護権と財産管理権から構成されます。
身上監護権
身上監護権とは、子どもの身の回りの世話をし教育する権利義務のことです。身上監護権は
- 監護教育権:子どもと一緒に住み、子どもを見守り教育していく権利義務
- 居所指定権:子どもをどこに住ませ、生活させるかを決める権利
- 職業許可権:子どもが職業に就く際に許可する権利
の3つから構成されます。
なお、かつては「懲戒権」も身上監護権の一つでしたが、虐待を正当化する口実に使われる可能性があるとの非難を受け、2022年(令和4年)に削除されています。
財産管理権
一方、財産管理権とは、子どもの財産を管理したり、親が子どもの代理人となる権利義務のことです。財産管理権は、
- 包括的な財産管理権 :子ども名義の口座を開設する、お祝い金やお年玉を貯金する など
- 法律行為に関する同意権:子どもが不用品を売却する、賃貸アパートを借りる際などに同意する など
- 身分行為の代理権 :進学、結婚、改姓の際に子どもに代わって手続きする など
の3つから構成されます。
親権は何歳まで?
親権をもてるのは子どもが未成年者の間まで、つまり、子どもが17歳のときまでです。
かつては20歳未満の子どもが未成年者とされていましたが、先ほど述べたとおり、今は18歳未満の子どもが未成年者とされています。なお、養育費の請求期限について決められていません。子どもが未成年者でなくなったからといって、養育費を請求できなくなるわけではありません。
親権と監護権との違い
監護権は先ほどの身上監護権のことで、親権の一部です。法律上は、親権から監護権を分離して、一方の親が親権を、一方の親が監護権をもつことが認められています。
親権から監護権を分離した場合は、監護権をもつ親が子どもの世話や教育をし、親権をもつ親は面会交流を通じて子どもとの交流を図っていくことになります。監護権をもつ親は他方に養育費を請求できます。
親権の決め方①~話し合い
親権のみならず養育費、面会交流などの離婚条件については、まずは夫婦で話し合うことからスタートです。
ただ、話し合いを円滑に、有利に進めていくためには、相手に話し合いを切り出す前の事前準備が大切です。事前準備が十分でないまま相手に話し合いを切り出すと、話し合いが長期化して離婚までに時間がかかったり、曖昧な離婚条件のまま離婚してしまい離婚後にトラブルとなる可能性があるため注意が必要です。
なお、今現在は、離婚前に夫婦のいずれかを親権者と決めなければ離婚できないことになっています(単独親権)。しかし、今後は離婚後でも共同親権も選択できるようになります。また、離婚前に親権者を決めなくても離婚できるようになります。詳しくは下の共同親権の記事でご確認ください。
親権の話し合いでの参考事項
相手に離婚を切り出した後、親権でもめずに話し合うには、次のことを頭に入れておくとよいかもしれません。
母親が親権をもつことが多い
まず、親権は母親がもつ(取る)ことが多いということです。
厚生労働省の調査結果によると、離婚した夫婦の約8割以上の夫婦では母親が親権をもっていることがわかっています。また、裁判所の調査結果でも、調停離婚した夫婦の約9割以上の夫婦では母親が親権を取っていることがわかっています。
仮に、妻が親権をもつことに反対して調停まで手続きを進めたとしても結局は妻が親権を取ることが多い、ということを頭に入れながら、話し合いで離婚を成立させるのか調停以降で離婚を成立させるのか、どちらが得策なのか考えた方がよいかもしれません。
面会交流を実施する
次に、面会交流を実施する(認める)ことです。
相手(特に、夫)が親権に固執しているのは、あなたに親権をもっていかれることで「子どもと会えない」などと考えているからかもしれません。しかし、面会交流を実施することでこうした不安が少しは解消され、親権でもめずに済むかもしれません。
相手に対する不満や怒りの感情から「親権は渡さない」、「面会交流も認めない」という気持ちになることもわかります。ただ、子どもに関わることだけは、個人的な感情はいったん横に置いておき、子どもの立場に立って決めていくという心構えでいることが大切です。
お金をきちんと払うことに合意する
次に、養育費や未払いの婚姻費用、慰謝料などのお金きちんと払うことに合意することです。
お金を払わないなら面会交流は認めないなどと、お金と面会交流を交換条件にすることはできませんが、それでもやはり親権をもつ相手がお金と面会交流とを交換条件にしたくなる気持ちも理解できなくもありません。
もし、相手に面会交流を認めて欲しいと思うのであれば、できる限り相手の希望に沿う形でお金を払っていくことに合意し、公正証書の作成にも協力して相手が抱いているお金の未払いに対する不安を少しでも解消することが大切です。
親権をわけることができる
次に、長男の親権は夫がもち、長女の親権は妻がもつ、というように親権をわけることができることです。
もっとも、兄弟姉妹は一緒に育てる方がいいという考え方もありますので(兄弟姉妹不分離の原則)、親権でもめているからといって安易に親権をわける方法を選択しない方がよいでしょう。
仮に、親権をわける場合でも、自分が親権者とならなかった子どもに対しては扶養義務が残るため、養育費の支払いはどうするのか、親と子、離れて暮らす子ども交流をどう図っていくかもきちんと決めておく必要があります。
親権と監護権をわけることができる
次に、親権は夫がもち、監護権は妻がもつ、というように親権と監護権をわけることができることです。
もっとも、親権と監護権をわけることにはデメリットもあり、デメリットをよく把握しないまま安易にわけてしまうと将来トラブルとなる可能性があります。
親権と監護権をわけるのは、どうしても親権で決着をつけることができない最終手段と考え、仮にわけることを検討する場合でもデメリットをよく把握しておくことが大切です。
親権者を変更することに合意できる
次に、将来親権者を変更することについてあらかじめ合意ができることです。
もっとも、実際には夫婦の合意だけで親権者を変更することはできず、家庭裁判所に対して親権者変更の調停を申し立て、家庭裁判所に親権者を変更することを認めてもらう必要があります。
親権者を変更することについて調停が必要であるにもかかわらずあらかじめ夫婦で合意しておくのは、調停のときに一つの考慮事情としてくんでもらい親権者変更を認めてもらいやすくするためです。
親権の決め方②~調停など
そもそも、夫婦で話し合うことができない、話し合っても話がまとまらない、という場合は離婚調停を申し立てることも検討する必要があります。ここでは調停以降、どのような手続きで進んでいくのかについて解説します。
調停
調停は、調停委員という第三者が夫婦の間に入り話をまとめていく、一定のルールに従って手続きを進めていく必要がある、という点が話し合い(協議)と大きく異なります。
調停以降の手続きでは、あとで述べる「親権を決めるときに考慮される事情」をいかに調停委員や裁判官にアピールできるかが、親権を獲得する上で重要になります。
関連記事
裁判など
相手が調停に出席しない場合、出席はするものの親権などについて合意できない場合は調停不成立となって離婚は成立しません。もちろん、親権についても何も決まっていません。
調停不成立となった場合は「再度話し合う(再協議する)」、「調停に代わる審判に移行する」、「離婚裁判を提起する」の3つの選択肢があります。都合のよい方法を選択しましょう。
親権を決めるときに考慮される事情
調停以降の手続きに進むということは親権でもめているというケースも少なくないでしょう。ここでは、仮に、調停以降の手続きに進んだ場合に、裁判所がどのような事情を考慮して親権者を決めるのか、その考慮事情について解説していきます。
現在の監護状況、監護実績
まず、今現在どちらの親が子どもと生活しているか、これまで主にどちらの親が子どもと触れ合ってきたかです。
今の生活環境を急に変えることは子どもにとって大きな負担となりますから、今の生活環境を維持した方が子どものためになります。また、子どもとの触れ合いが多い親の方が子どもからの信頼も厚く、子どもとの精神的な結びつきが強い傾向にあります。離婚を機にこうした親と離れ離れにすることは子どもにとって一番よくないことであるため、現在の監護状況や監護実績は最も重要視されます。
母性優先の原則
母性優先の原則とは、原則として母性のある親に親権をもたせるべきとの考えです。
かつては「母子」優先の原則と言われていましたが、父親でも母親的な役割を果たせることから「母性」優先の原則と言われるようになっています。乳幼児について母親が有利ですが、乳幼児以外の子どもについてはどちらに母性があるかをみられます。
離婚後の生活環境
次に、子どもが安心して生活できる環境が整っているかどうかです。
特に、子どもが幼い間は子どもを一人で見るのは体力的にも精神的にも難しいでしょう。そのため、周囲にどれだけ頼れる人がいるか、頼れる環境が整っているかをみられます。
心身の健康状態
次に、親の心身の健康状態です。
子育てしていくには親自身が心身ともに健康でなければいけません。病気がち、精神障害をかかえている、酒や薬物、ギャンブル依存症、浪費癖といった事情はマイナス要素として働いてしまいます。
経済力
次に、経済力です。
子育てしていくにはお金がかかりますから、経済力も考慮事情の一つです。ただ、今現在経済力がなくても、これから経済力を身につけていくことはできますし、養育費や公的支援で経済力を補うこともできますので、それほど重要視されるわけではありません。
子どもの意向
次に、子どもの意向です。
子どもが15歳以上の場合、審判では子どもの意見を聞かなければならず、調停でも子どもの意向を十分考慮する必要があるとされています。また、子どもが10歳前後であれば子どもの意向を確認するとされており、子どもの意向が結果に反映される可能性があります。
面会交流への寛容性
次に、親権者となる親(監護親)が、非監護親の面会交流を拒否せず、条件面でも柔軟な姿勢を示しているかどうかです。
面会交流は子どもの健全な成長のためにも重要なイベントと考えられていますので、面会交流に寛容であることは、親権者としての適格性の評価にもいい影響を及ぼすことがあります。
兄弟姉妹の不分離の原則
兄弟姉妹の不分離の原則とは、子どもが複数いる場合は、原則として子どもは同じ親の元で生活するべきという考え方です。
兄弟・姉妹間の仲がいい場合、離婚を機に兄弟姉妹を離れ離れにしてしまうと子どもに悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。そのため、調停以降の手続きでは、親権をわけることはあま
親権をもたない親と子どもとの関係
話し合いや調停などの結果、親権をもたないことになった親(非監護親)と子どもとの関係は離婚後も継続します。離婚したからといって法的な親子関係が途切れるわけではなく、非監護親には以下の権利・義務が発生します。
面会交流ができる
まず、非監護親には子どもと面会交流ができる権利があります。
親権をもつ親(監護親)は、原則として、面会交流を拒否することができません。親権について話し合うときは、面会交流についてもセットで話し合う必要があります。面会交流を実施することで合意する場合は、面会交流のルールについても話し合いましょう。
養育費を払う必要がある
一方、非監護親は監護親に対して養育費を支払う義務があります。
一般的に、父親が非監護親となることが多く、母親よりも父親の方が収入が多いため、養育費は父親が払うものとイメージされがちですが、父親が監護親となる場合は、収入の多い少ないにかかわらず母親も養育費を負担しなければいけません。
親権者は変更できる
離婚のときに決めた親権者を、その後変更することが法律で認められています。もっとも、親の合意だけで変更できるとなると、子どもを混乱させ、子どもに悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
そのため、親権者を変更するには必ず家庭裁判所に対して親権者変更の調停(または審判)を申し立てる必要があります。そして、裁判所が親権者を変更することが子どものためになると判断したときに限って親権者を変更できることになっています。
親権を喪失・停止する制度もある
親権者変更ほかに、親権者の親権を喪失・停止させる制度も設けられています。親権の喪失とは親権者から親権を奪うこと、親権の停止とは期間を定めて親権者から親権を奪うことです。
親権を喪失させる場合も停止させる場合も、親権者に虐待や悪意の遺棄など、親権者としてふさわしくない事情があったことが必要です。また、手続としては、家庭裁判所に対して審判を申し立てる必要があります。
親権に関するQ&A
最後に、親権でよくある疑問・質問にお答えします。
専業主婦でも親権をもてますか?
もちろん可能です。過去の統計をみると、母親が親権をもつケースが圧倒的に多いことがわかります。経済力がないことを心配される方も多いですが、経済力は親権を決める上での重要視されません。今からでも経済力を身につけていくことができますし、養育費や児童手当などの公的なお金である程度の不足分はカバーすることができるからです。
父親でも親権をもつことはできますか?
まず、相手との話し合いで合意できれば可能です。親権でもめて調停以降の手続きに進むと難しくなりますが、それでもまったく不可能というわけではありません。監護実績を積んでおく、離婚した後の生活環境を整えおく、相手が不利となる事情の証拠を集めておくなど、あらかじめ対策をとっておくことが必要です。
相手の不倫で離婚しますが、親権をもてますか?
相手が不倫したからといって、必ず親権をもてるわけではありません。不倫は児童虐待と異なり親の問題であって、子どもには直接的には関係のないことです。相手の不倫が原因で離婚することになったとしても、それだけで相手が子どもの親権者となる資格がないと断定できないことも考えられます。
母性優先の原則とは何ですか?
母性優先の原則とは、子ども、特に乳幼児(0歳~5歳前後)については、母性によるきめ細かな子育てが不可欠であることから、特段の事情がない限り、母性が認められる親に親権をもたせるべきとする考え方です。かつては「母子」優先の原則と言われていましたが、父親でも母親のような役割を果たすことは十分可能であることから、「母性」優先の原則と言われることがあります。
離婚後の子どもの苗字、戸籍はどうなりますか?
離婚したから、親権をもったからといって子どもの苗字が変わるわけではありません。また、子どもの戸籍が相手を筆頭者とする戸籍に入っている場合、子どもの戸籍も相手の戸籍に入ったままとなります。子どもの戸籍をあなたの戸籍に入れるには、家庭裁判所から苗字変更の許可を受けた上で、役所に入籍届を行う必要があります。
妊娠中に離婚した場合の親権はどうなりますか?
妊娠中に離婚し、離婚後に生まれてきたお子さんの親権は母親がもちます(※)。父親が親権を希望する場合は、母親との話し合いだけで父親に親権を渡すことができますが、母親が同意しない場合は、父親が親権者の変更調停を申し立てて調停以降の手続きで決める必要があります。
※婚姻中の戸籍の筆頭者が父親の場合、離婚後、300日以内に生まれた子どもの戸籍は父親の戸籍に入ります(苗字は父親の苗字となります)。離婚時に母親の戸籍は相手(父親)の戸籍から抜けるため、何も手続きしなければ、母親の戸籍と離婚後に生まれてきた子どもの戸籍は別々となります(苗字も別々のままです)。子どもの戸籍を母親の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所から子どもの苗字の変更について許可を得た上で、役所に入籍届をする必要があります。
親権を放棄することはできますか?
原則、親権を放棄することはできません。しかし、家庭裁判所に親権辞任の申立てを行い、裁判官が親権を放棄することについてやむを得ない事由があると認め、裁判官から親権を放棄することについて許可を得ることができれば放棄することが可能です。