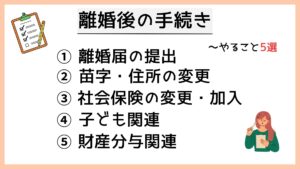- 離婚・別居後の住まいをどこにするか悩んでいます・・
この記事ではこのような悩みにお応えします。
お金の準備と同時並行で進めていかなければいけないことが離婚・別居後の住まいの確保です。離婚・別居後の住まいはあなたと子どもの生活の基本となります。離婚・別居後の住まいをどこにするかによって、今後のあなたの仕事やあなたと子どもの生活のことなどが決まってくるでしょう。
そこで、今回は、離婚・別居後の住まいとなりうる候補地をご紹介するとともに、それぞれのメリット、デメリットもあわせて解説していきたいと思います。今後の、離婚・別居後の住まい探しの参考にしていただければ幸いです。
この記事を書いた人

-
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。※大変申し訳ありませんが、ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しております。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】
- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説
- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します
- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します
離婚・別居後の住まい~今の家
まず、一番目の候補地は今の家です。
今の家に住み続ける最大のメリットは、今の生活パターン・環境を変える必要がないことでしょう。今の家から出ていくとなると、一から新しい住まいに慣れ、住む場所によっては生活環境や人間関係にも慣れていく必要があります。
特に、子どもがいる場合は、これまでの生活環境、人間関係を変えることは子どもにとって負担が大きく、年齢によっては体調や精神面に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
子どもと一緒に暮らす予定がある場合は、まずはこれまでどおりの生活を続けていくことができないか検討した方がよいでしょう。引っ越しの必要がなく、引っ越し費用がかからないことも今の家に住み続けるメリットといえます。
一方、今の家が賃貸の場合も持ち家の場合も、そもそも今の家に住み続けることができるかどうか検討する必要があります。
たとえば、賃貸で、賃貸借契約上の名義(借主)が夫で、妻が今の家に住み続けることを希望する場合は、名義を夫から妻に変更することについて貸主の承諾を得る必要があります。ただ、そもそも妻に家賃を払い続けるだけの経済力がない場合や保証人を立てることができない場合は、貸主の承諾を得ることができない場合もあります。
また、持ち家で、家と住宅ローンの名義が夫で、妻と子どもが家に住み続けることを希望する場合は、誰が住宅ローンを払っていくかを検討する必要があります。この場合、妻が住宅ローンを払うのが通常だと思いますが、夫と妻の合意だけでは住宅ローンの名義を変えることができません。名義を変更するには住宅ローン会社と話し合った上で承諾を得る必要があります。
もっとも、妻に住宅ローンを払い続けるだけの経済力がない場合はローン会社から承諾を得ることは難しく、かといって、夫に住宅ローンを払うよう求めることもできず、結局は今の家から出ていく選択をせざるをえない場合も考えられます。また、仮に、名義変更の承諾が得られたとしても、家賃や住宅ローン、維持費、固定資産税などの費用がかかることも念頭に置いておく必要があるでしょう。
【メリット】
・今の生活パターン、環境を変える必要がない
・転職、転園・転校の必要がない
・子どもへの影響を最小限に抑えられる
・引っ越しの必要がない、費用がかからない
【デメリット】
・今の家に住み続けることができない場合がある
・家賃、住宅ローン等を負担する必要がある
離婚・別居後の住まい~実家
次の候補地は実家です。
賃貸住宅に住む場合に比べて初期費用を安く抑えることができますし、諸手続きが不要です。ある程度家にお金を入れる必要があるにしても、家賃やガス・水道光熱費がかからず、食事や子どもの面倒を親にみてもらうことができ、安心して仕事ができる点も大きなメリットです。
親の負担などを考えると長期間住むことには向いていないかもしれませんが、次の住まいを見つけるまでの「仮の住まい」として実家を選択することもありだと思います。
一方、親の意見や体調、実家の間取りや広さしだいでは住むことができないかもしれません。仮に住むとしても自分たちに合った間取りや広さではなく、ストレスを感じるかもしれません。実家の場所によっては子どもの転園・転校を考えなければなりません。相手に離婚後の住まいを知られたくない場合は、実家は離婚後の住まいの候補からは外さなければならないでしょう。
また、児童扶養手当の金額を算定する上で、親などの同居する人の所得も合算されるため、同居しない場合に比べて受け取る金額が低くなる可能性があることにも注意が必要です。親と同居していると子どもを世話できる人がいると判断され、保育園への入園を待たされることもあります。
さらに、親だからといって必ずしも受け入れてくれるとは限りません。同居後にささいなことで親と喧嘩してしまうこともあります。一方、親が過保護になったり、自分たちの生活や教育に過度に干渉してくることも考えられます。
【メリット】
・初期費用を安く抑えることができる
・諸手続きが不要
・親に子ども、食事の面倒をみてもらえる
・子どもがいても安心して仕事できる
・家賃、水道光熱費などがかからない
・生活費を抑えることができる
【デメリット】
・親と仲が悪い場合は住めない
・親が心から受け入れてくれない可能性がある
・親に経済的、精神的、体力的な負担がかかる
・実家によっては住めない、ストレスを感じることがある
・相手に住まいを知られたくない場合は住めない
・児童扶養手当が少なくなる
・保育園への入園を待たされることがある
・生活全般や教育について過度な干渉を受ける可能性がある
関連記事
離婚・別居後の住まい~賃貸住宅
実家に住むことが難しい場合は、アパートなどの賃貸住宅も候補地の一つです。
賃貸住宅であれば、あなたや子どもに合った住まいを自由に選ぶことができます。離婚を機に環境や人間関係を変えたい、心機一転したいという場合は選択肢の一つといえます。
実家に住むことができないとしても、実家の近くのアパートを賃貸できれば、親のサポートを受けることもできます。また、費用はかかりますが、一度住んでみて違和感を感じる場合は、他の場所へ引っ越ししやすいのも賃貸住宅のメリットといえます。
一方、賃貸住宅によっては敷金・礼金などのまとまった初期費用が必要となる場合があります(※)。家賃や維持管理費を払い続けなければなりませんので、一定の収入がない場合や保証人を立てることができない場合は借りることができないこともあります。
家賃や水道光熱費などの固定費が家計を圧迫し、離婚後の生活が立ち行かなってしまう可能性があることにも注意が必要です。
【メリット】
・住む場所を自由に決めることができる
・今までと異なった環境、人間関係で生活できる
・新しい環境で心機一転できる
・実家の近くに住めば、親のサポートを受けることができる
・転居しやすい
【デメリット】
・多額の初期費用がかかる可能性がある
・一定の収入、保証人がなければ借りることが難しい
・家賃を払い続ける必要がある
・家賃などの固定費が家計を圧迫する可能性がある
※初期費用が不要な物件もありますが、家賃が高く設定されている、違約金が設定されている、退去時に高額な費用を請求されることなどに注意が必要です。
家賃保証会社を利用できる物件を利用してみる
親が高齢、無職などの理由で保証人を立てることが難しい場合は家賃保証会社を利用できる物件を探してみるのも一つの方法です。敷金が安い場合がある、家賃を滞納しても親等に迷惑がかからない、収入が低くても審査に通れば住むことができる、という点がメリットです。
一方、保証料(初回時(契約時):月家賃の50~100%、更新時(1~2年ごと):1~2万円)を払う必要があります。また、年収等の審査を通る必要があります。貸主によっては家賃保証会社に加えて連帯保証人を要求されることもありますので、利用条件をよくチェックしておきましょう。
自治体の公的支援制度を活用する
その他、自治体の公的支援制度を活用するのも一つの方法です。自治体の家賃に関する主な公的支援制度には、
- ひとり親家庭住宅助成:一定の月に数か月分の助成金がまとめて振り込まれる(最長6年)
- 住宅支援資金貸付:貸付金(月額上限4万円)を無利子で借りることができる(最長1年)
※貸付日から1年以内に就職し、その後1年間継続して就業した場合などは返済免除
があります。
いずれもひとり親であること、一定の所得以下であることなどが条件です。ひとり親家庭住宅助成については、お住いの役所のHPで制度が設けられているか確認しましょう。住宅支援資金貸付については、各都道府県の社会福祉協議会にお問い合わせください。
離婚・別居後の住まい~公的住宅・施設
同じ賃貸住宅でも都道府県や市区町村が管理している公営住宅も候補地の一つです。ひとり親世帯を優先的に入居させてくれる自治体もありますので、まずはこれからお住いになる自治体に問い合わせてみるとよいでしょう(※)。
公営住宅に住む最大のメリットは、民間の賃貸住宅と比べて家賃が安いことです。実際の家賃は自治体が前年度の所得等を参考にして決定します。更新料はかかりません。敷金・礼金は自治体によってかかる場合もありますが、「家賃の〇か月分」と設定されていることが多いため金額自体が安いですし、家賃の滞納等がなければ退去時に返還されます。
一方、必ず入居できるわけではありません。入居するには、所得が一定基準以下などの入居条件をクリアする必要があります。条件をクリアしても、応募者が多数にのぼる場合は抽選となることもあります。応募(入居)時期が決まっていることがあり、いつでも入居できるというわけではありません。
また、自治会がしっかりしていて、棟ごとに役員が割り振られることが多いのも公営住宅の特徴です。ひとり親家庭を理由に断ることはできません。民間のアパートなどと異なり管理会社が入っていないため、草刈りや溝の清掃なども定期的に行われます。これらが面倒に感じる方は公営住宅への入居は向いていないかもしれません。
【メリット】
・家賃、敷金・礼金が安い
・更新料がかからない
・ひとり親世帯などが優先的に入居できる
【デメリット】
・入所条件をクリアする必要がある
・抽選で入居できないことがある
・応募(入居)時期が決まっていることがある
・役員が回ってくる
・草刈りや溝の清掃などがある
※DVを受けているなど非難の緊急性が高い場合は、離婚前(別居中)でも入居できることがあります。詳しくは自治体に問い合わせてみましょう。
※母子生活支援施設
公的な住まいとしては公営住宅のほか母子生活支援施設があります。母子生活支援施設は、児童福祉法38条に基づき、母子が社会的、経済的に自立できるようサポートするために設けられている施設です。入所の理由としてはDVが一番多いですが、その他の理由でもサポートが必要と認められれば入所できます。入所後は、職員に相談し、サポートを受けながら、自立できるまで独立した居室で生活を送ることができます。窓口はお住いの福祉事務所です。どんな施設か気になる方、入所を希望される方は一度相談してみてはいかがでしょうか。
参照:母子生活支援施設 | 内閣府男女共同参画局
離婚・別居後の住まい~社宅
民間の賃貸住宅、公営住宅のほか社宅という手もあります。会社勤めの方は現在勤めている会社が社宅制度を採用していないか確認してみましょう。これから就職・転職される方は、あえて社宅制度を採用している会社に勤めるのも選択肢の一つです。
社宅には主に「社有社宅」と「借り上げ社宅」があります。社有社宅は会社が所有している物件を従業員に賃貸する社宅です。一方、借り上げ社宅は会社が賃貸物件の一室(あるいは全部)を借り、それをさらに従業員に賃貸する社宅です。
どちらの社宅でも初期費用・更新料が不要で、家賃が安く設定されていることから、生活費の負担軽減になる点が最大のメリットです。会社に一定額以上の家賃を払っている場合、給与から家賃が天引きされている場合は所得税などの節税にもつながります。物件探しや諸手続きが不要なのもメリットといえます。
一方、あらかじめ会社が所有または借りている物件に住むことになる、すなわち、あなたや子どもに合った物件を自由に選ぶことができません。社有社宅の場合は他の従業員も住んでいるため、仕事とプライベートとを分けづらいことにも注意が必要です。会社の従業員であることが社宅に住み続ける条件であるため、社宅に住むことで退職・転職しづらくなるという点もデメリットかもしれません。
【メリット】
・初期費用、更新料が不要
・家賃が安い
・節税になることも
・諸手続きが不要
【デメリット】
・物件を自由に選べない
・仕事とプライベートとの区別がない(社有社宅の場合)
・退職、転職しづらい
まとめ
今回のまとめです。
- 離婚・別居後の住まいの確保はお金の準備と同じくらい大切
- 離婚・別居を思い立ったら住まいも検討しましょう
- 離婚後の住まいのメリット、デメリットも踏まえて賢い選択を