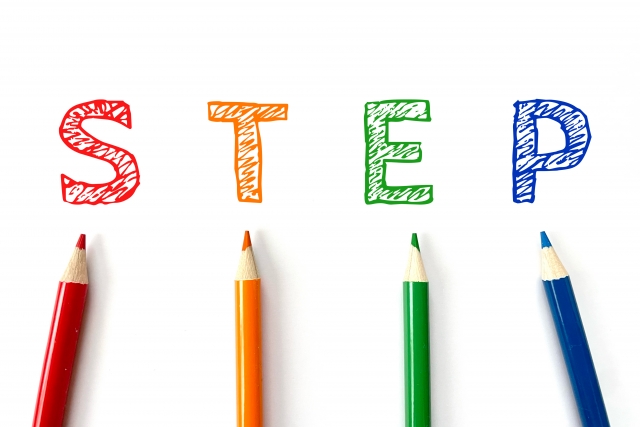- 相手の親権を喪失させることはできますか?
- 親権を喪失させるにはどんな手続きが必要ですか?
- 親権の喪失と停止の違いは何ですか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
離婚のときに、相手が親権をもつことに合意した、調停や裁判で相手が親権をもつことになった、という場合でも、やはり親権をもつことを諦めきれずにこのような疑問、悩みを抱く方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、相手の親権を失わせる親権喪失や親権を喪失させるための条件・手続き、親権喪失と親権停止との違いなどについて詳しく解説していきたいと思います。
この記事を書いた人

-
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】
- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説
- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します
- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します
親権喪失とは
親権喪失とは、文字通り、(期間を定めずに)親権者の親権を失わせることをいいます。
親権を喪失させることができる場合
親権者の親権を喪失させることができるのは次の場合です。ただし、2年以内に次にあげる事由が消滅する見込みがあるときは、親権を喪失させることができないこともあります。
虐待、悪意の遺棄が行われた
一つ目に、親権者が子どもに虐待や悪意の遺棄を行った場合です。
ここでいう虐待とは、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待のことを指しています。
身体的虐待:殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける など
心理的虐待:子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、他の兄弟姉妹とは著しく差別的な扱いをする など
性的虐待 :性的暴行、性的行為の強要・示唆、性器や性交を見せる など
次に、悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに、親権者の義務である子どもへの監護、養育、教育の義務を怠ることをいいます。いわゆる「ネグレクト」と言われるものがこれにあたります。
ネグレクト:食事を与えない、お風呂に入れない、汚れた衣服を着替えさせない、汚物を処理しない、学校に行かせない など
親権の行使が著しく困難又は不適当
二つ目に、親権者が親権を行使することが著しく困難又は不適当な場合です。
親権を行使することが著しく困難な場合とは、重度の精神病や薬物・アルコール中毒に罹患したなど、精神的、身体的な故障により、適切に親権を行使することが困難に近い状況のことをいいます。
親権を行使することが著しく不適当な場合とは、子どもへ虐待や悪意の遺棄を行うなど、親権の行使の方法が適切さを欠くような場合や親権者に親権を行使させることが子どもの健全な成長のために著しく不適当な場合をいいます。
なお、最高裁判所が公表している「親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況ー令和5年1月~12月-(以下「概況」といいます。)」によると、全国各地の家庭裁判所で親権喪失・停止が認められた理由の内訳(件数)は次のとおりです。
| 身体的虐待 | 性的虐待 | ネグレクト | 心理的虐待 | その他 | |
| 親権喪失 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 |
| 親権停止 | 23 | 2 | 39 | 26 | 19 |
親権を喪失させる方法
親権者の親権を喪失させるには、家庭裁判所に対して親権喪失の審判を申し立てる必要があります。
先ほどの「概況」によりますと、全国の家庭裁判所に対して親権喪失の審判が申し立てられた件数の推移は次のとおりです。親権停止の審判の申立て件数よりかは少ないのが現状です。
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
| 109 | 121 | 104 | 81 | 81 |
申立てできる人(申立人)
・・・子ども本人、一方の親、子どもの親族、未成年後見人、未成年後見監督人、児童相談所長、検察官
申立て先の裁判所
・・・子どもの住所地を管轄する裁判所
申し立てに必要なもの ※裁判所に要確認
□ 申立書
□ 子どもの戸籍謄本
□ 申立人の戸籍謄本
□ 相手方の戸籍謄本
(子どもと同一戸籍の場合は不要)
□ 審判を求める理由を示す資料
□ 収入印紙(代)
□ 郵便切手代
裁判所に申し立てが受理されると、裁判所から申立人に審問期日(裁判所で話を聴くための日時)が通知されます。申立人は審問期日に出頭し、裁判官の質問に答えるなどして対応します。一方相手にも反論の機会が与えられます。
場合によっては、家庭裁判所調査官の調査が入り、その結果を踏まえてさらに裁判官が当事者から話を聴くなどしていきます。なお、概況によると、令和5年度の親権喪失の審判の期間は次のとおりとなっています。
| 1月以内 | 1月超 2月 | 2月超 3月 | 3月超 4月 | 4月超 5月 | 5月超 6月 | 6月超 |
| 3 | 5 | 4 | 18 | 6 | 10 | 33 |
全体の約3割5分が6月を超える期間を要しています。
審判前の保全処分
このように、親権を喪失させるか否かの審判が確定するまでには一定の期間を要しますが、その間、子どもが親権者から虐待を受けるようなことがあってはなりません。
そこで、ただちに親権者の親権を停止させる必要性・緊急性が認められるときは、審判の申立てとともに審判前の保全処分の申し立てを行います。
保全処分の申立てが認められると、審判の結果が出るまでの間、親権者の親権が停止され、裁判所が親権を代わりに行使する者(職務執行者)を選びます。申立人が職務執行者に選ばれることもあります。
なお、保全処分の申立てが却下された場合は、申立人は、その告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に不服を申し立てる(即時抗告する)ことができます。
一方、保全処分の申立てが認められた場合は、相手も不服を申し立てることができます。この場合は保全処分の執行停止の申立てもあわせて行われます。
親権喪失の審判が確定した後はどうなる?
家庭裁判所での手続きを経て、最終的に裁判官が親権を喪失させるかどうかの審判をくだします。ただし、審判に不服がある場合は、審判の結果を知った日から起算して14日以内に不服を申し立てることができます。不服が申し立てられた場合は審判の効力は失われ、審理は高等裁判所に引き継がれます。一方、14日以内に不服が申し立てられなかった場合は審判が確定します。ここでは審判が確定した後に生じる効果について解説していきます。
親権者は親権を失う
まず、当然ですが、親権者は親権を失います。
すなわち、親権者は子どもと一緒に住んだり、子どもの財産を管理することができなくなります。ただ、親権を失ったからといって法律上の親子関係でなくなるわけではありませんから、法律上の親子関係であるがゆえに発生する
- 子の親の財産に対する相続権
- 親、子同士の扶養義務
- 未成年者の子の婚姻や特別養子縁組の同意権
は失いません。
婚姻中で共同親権だった場合
婚姻中で、父母が共同して親権を行使していたものの、父親が親権を喪失したという場合は、母親が単独親権者となります。一方、父母双方が親権を喪失した場合は、親権を行使する人がいませんから未成年後見人を選任する手続きが開始されます。未成年後見人とは、親権者がいない場合に、代わりに子どもの身の回りの世話をしたり、財産を管理したりする人のことです。
離婚後、単独親権だった場合①
離婚した後、親権をもたない親が親権をもつことを望む場合は、家庭裁判所に対して親権者変更の調停(または審判)を申し立てる必要があります。親権者喪失の審判が確定しても、親権をもたない親に自動的に親権が移るわけではないことに注意が必要です。
離婚後、単独親権だった場合②
一方、離婚した後、親権者になる人がいない場合は、家庭裁判所が未成年者後見人を選任する手続きをとります。未成年後見人には、児童相談所長、弁護士などの個人のみならず、社会福祉法人などの法人も選任されることがあります。また、未成年後見人は複数選任されることがあります。親権を喪失した親は未成年後見人に選任されません。
親権喪失しても親権が復活する?
このように、親権喪失の審判が確定すると親権者は親権を失いますが、実は、その親権者に親権が復活することがあります。それが、親権を喪失させる旨の審判が取り消された場合です。
法律には次のいずれかの場合に、親権を喪失させる旨の審判が取り消されることがあると規定されています。親権を喪失させる旨の審判を取り消すには、本人(親権喪失前の親権者)またはその親族が、家庭裁判所に対して取消しの請求を行う必要があります。
・虐待又は悪意の遺棄を行うおそれが消滅したとき
・親権の行使が著しく困難又は不適当と認められる事情が消滅したとき
親権停止とは
ここまで親権喪失について解説してきましたが、ここでは親権停止について簡単に解説します。
親権停止とは、一定期間(2年を超えない範囲で家庭裁判所が定める期間)、親権者の親権を停止させることです。
親権喪失が期間を定めずに親権者から親権を奪うという厳しい法制度であることから、親権喪失に代わる緩やかな法制度として2011年の法改正により新設されたのが親権停止です。
親権喪失では親権を喪失させる旨の審判が取り消されない限り親権は復活しませんが、親権停止では一定期間が経過した後は親権者に親権が復活する点が大きな違いです(もっとも、親権停止にも審判の取り消しの制度があります)。
親権を停止したい場合も、親権喪失と同じく、家庭裁判所に対して親権停止の審判を申し立てる必要があります。
まとめ
今回のまとめです。
- 親権喪失は期間を定めずに親権者の親権を失わせること
- 親権停止は期間を定めて親権者の親権を停止すること
- 虐待など一定の事由がある場合のみ親権を喪失、停止させることができる
- 親権を喪失させたい場合、停止させたい場合は家庭裁判所に対して審判の申立てをする必要がある
- 相手の親権を喪失させ、自分に親権を移したい場合は親権者変更の調停(または審判)を申し立てる必要がある