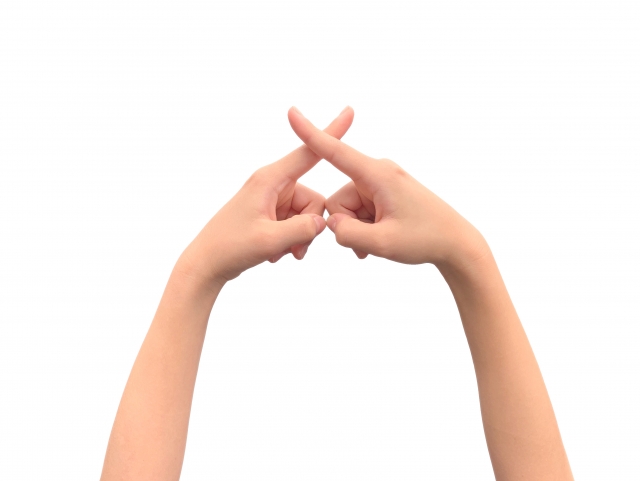- 面会交流は拒否できますか?
- どんなケースで拒否できますか?
- 拒否できないケースとはどんなケースですか?
- 面会交流の負担を減らす方法はありますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
面会交流を認めると離婚後も相手との関係が継続されることから、離婚を機に二度と相手と関わりたくないという場合、面会交流を拒否したいと考える方も多いのではないでしょうか?
今回は、そもそも面会交流を拒否できるのか、拒否できるケース・できないケースとはどんなケースか、一方的に拒否し続けるとどうなってしまうか解説するとともに、面会交流の負担を少しでも軽くする方法もあわせてご紹介します。
この記事を書いた人

-
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。※大変申し訳ありませんが、ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しております。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】
- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説
- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します
- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します
原則、面会交流は拒否できない
まず、原則として、面会交流は拒否できません。
これは、面会交流が子どもと離れて暮らす親(非監護親)の権利だけでなく、子どもの健やかな成長のためにも重要と考えられているからです。
子どもは面会交流を通じて監護親と非監護親の双方から愛情を受けているという安心感や充足感を得ることができます。そして、そのことが子どもの自己肯定感を育み、子どもの健やかな成長につなげることができると考えられています。
面会交流が子どものためにならない場合を除き、親の都合で面会交流を拒否したり、面会交流を行わないと取り決めることは子どもにとって望ましいことではありません。
面会交流を拒否した場合のリスク
では、非監護親から面会交流の申し出があったにも関わらず面会交流を拒否した、あるいは拒否し続けたという場合、どういうリスクがあるののでしょうか?
養育費を払ってもらえない
まず、養育費を払ってもらえないことが考えられます。
確かに、面会交流ができないからといって養育費を払わなくていいということにはなりません。ただ、現実問題として、非監護親が「面会交流させてくれないなら養育費を払わない」という気持ちになることもわからないでもありません。非監護親に養育費をきちんと払ってもらうには、面会交流を実施して非監護親の子どもに対する愛情・関心を保ち続けておくことが大切とも言われています。
調停を申し立てられる
次に、調停(離婚調停、面会交流調停)を申し立てられる可能性があることです。
調停では様々なルールにしたがって手続きを進めていく必要があります。期日は平日を指定されます。家事や育児の合間、仕事の休みをとって裁判所に行く必要があります。調停は1回や2回で終わることは少なく、成立までに長くて1年以上かかることもあります。調停が成立すると、後ほど述べる履行勧告や間接強制を受ける可能性があります。
参照:離婚調停(夫婦関係調整調停(離婚)) | 面会交流調停
履行勧告を受ける
次に、調停で面会交流の取り決めをした場合は履行勧告を受ける可能性があることです。
履行勧告とは、家庭裁判所が非監護親からの申し出を受けて、調停(または審判)で定められた面会交流の実施状況を調査し、きちんと実施されていないと認めたときは、監護親に対してきちんと実施するよう勧告する制度です。なお、履行勧告に強制力はないため、勧履行勧告に従わなかったからといって何か制裁を科されるわけではありません。
再調停を申し立てられる
次に、再調停を申し立てられる可能性があることです。
裁判所は、面会交流のルールについて、監護親と非監護親が話し合って決めていく方が望ましいという考えています。そのため、一度目の調停では大まかなルールのみ定められることが多いです。もっとも、こうした大まかなルールでは間接強制ができないため、履行勧告を受けてもなお面会交流を拒否する場合は再調停を申し立てられ、再調停の中で細かなルールを定められてしまう可能性があります。
間接強制を受ける
次に、間接強制を受ける可能性があることです。
間接強制とは「面会交流を拒否する場合、1回につき●万円(5万円~10万円程度が相場)を支払え。」という裁判所からの命令です。心理的なプレッシャーをかけることで、間接的に面会交流を実現させることを目的としています。制裁金を払わなくても強制的に面会交流が実現されるわけではありませんが、ゆくゆくは給与などの財産を差し押さえられる可能性はあります。
慰謝料請求される
次に、面会交流を拒否され続けたことによって精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求される可能性があることです。
もっとも、非監護親が慰謝料請求できるのは、面会交流のルールを詳細に取り決めており、監護親の義務が明確で、かつ、監護親が面会交流を積極的に妨害している、長期間に渡り面会交流を拒否し続けているなど、違法性の程度が強いと認められる場合です。
慰謝料の相場は「0円~100万円」と言われていますが、過去には500万円の支払を命じた裁判例(静岡地方裁判所平成11年12月21日)もあります。特に、
・ 長期間、拒否し続けている
・ 拒否の理由が不当
・ 嘘をついて拒否し続けていた
とういような悪質なケースの場合は慰謝料が高額となりやすいため注意が必要です。
親権者変更調停を申し立てられる
最後に、非監護親から家庭裁判所に対し親権者変更調停を申し立てられる可能性があることです。
親権者変更の調停を申し立てられたからといってただちに親権者が変更されるわけではありませんが、面会交流を拒否し続けたことをきっかけに親権者としての不適格性を指摘され、親権者を変更されてしまう可能性がないとはいえません。実際に、面会交流を拒否し続けた結果、親権者を変更されてしまった裁判例(福岡家庭裁判所平成26年12月4日)もありますので注意が必要です。
面会交流を拒否できないケース
次のようなケースでは、面会交流を拒否することはできません。
養育費を払ってもらっていない
まず、養育費を払ってもらっていないという場合です。
養育費や面会交流は子どものためにありますから、養育費を払うなら面会交流を認める、払わないなら面会交流を認めないというように、養育費と面会交流を交換条件としてはいけません。
非監護親が原因で離婚した
次に、非監護親の浮気等が原因で離婚したという場合です。
離婚原因が何であれ、子どもにとって非監護親は一人の親であることは変わりありませんので、DV等の一定の例外を除いては、面会交流を拒否すべきではありません。
関連記事
非監護親の親族に会わせたくない
次に、非監護親の親族に会わせたくないという場合です。
非監護親の親族には子どもと面会交流する権利はないと考えられています。非監護親の親族に会わせたくない場合は、あらかじめ非監護親にその旨をしっかり伝え、書面を取り交わしておくなどの対応が必要です。
再婚したから
次に、あなたが再婚したという場合です。
あなたが再婚したとしても非監護親と子どもとの親子関係は続きますから、基本的には面会交流を拒否することはできません。一方的に拒否するのではなく、再婚を機にこれまでのルールを見直してみるとよいでしょう。
面会交流を拒否できるケース
一方、次のケースでは面会交流を拒否できる可能性があります。
子どもが虐待を受けるおそれがある
まず、面会交流のときに子どもが虐待を受けるおそれがある場合です。
過去に子どもが虐待を受けていたことがある場合はもちろん、非監護親に粗暴歴があったり、あなたに対するDV歴がある場合などは、面会交流のときに子どもへ危害を加えるおそれがあり、面会交流を拒否することができます。
あなたがDVを受けていた
次に、過去にあなたが非監護親からDVを受けていた場合です。
DV歴のある非監護親は、面会交流のときに子どもにも暴力を振るう可能性があります。また、子どもの目の前でのDVは児童虐待(心理的虐待)の一種で、子どもに恐怖心を植え付けており、子ども自身が面会交流を拒否する可能性が高いです。
子どもが面会を拒否している
次に、子どもが面会交流を拒否している場合です。
子どもが面会交流を拒否している場合は、年齢、発育の程度、拒否する理由ないし背景その他の事情によって、拒否できる場合があると考えられています。もっとも、あなたに同調しているだけかもしれませんので、子どもの本心を慎重に見極める必要があります。
連れ去りのおそれがある
次に、連れ去りのおそれがある場合です。
過去に連れ去られたことがある、非監護親が普段から子どもの連れ去りをほのめかしている、などの事情がある場合は面会交流を拒否できる可能性があります。
子どもが危険に巻き込まれるおそれがある
次に、子どもが何らかの危険に巻き込まれるおそれがある場合です。
特に、非監護親が中毒症状、情緒不安定、精神不安定、素行不良という場合は注意が必要です。前科を多数もちあわせていることだけでは面会交流を拒否する理由にはなりませんが、考慮事情にはなります。
無理な条件を突きつけられている
次に、無理な条件を突きつけられている場合です。
たとえば、子どもと毎日会いたいと要求される、(お互い遠方に住んでいるにもかかわらず)子どもを相手のもとに連れて来ること、その際の交通費を負担することを要求される、一度取り決めた面会交流のルールに従わない場合などです。
協議中、調停中
最後に、離婚に向けて協議中、調停中、面会交流の調停中という場合です。
この場合は、面会交流を実施するか否かをはっきりさせていない段階ですから、拒否しても特段問題はありません。
面会交流の負担を減らす方法
あなたが面会交流を拒否したいと考えているのは面会交流を負担に感じているからかもしれません。一方、面会交流の負担を軽くする方法を知っていれば、面会交流の実施に向けて前向きな気持ちになれるかもしれません。そこで、以下では、面会交流の負担を少しでも軽くする方法についてご紹介していきたいと思います。
第三者機関を利用してみる
まず、第三者機関を利用してみることです。
第三者機関とは、監護親と非監護親だけでは面会交流を実施することが困難な場合に、第三者が間に入って、面会交流を円滑に実施できるよう支援してくれる機関です。支援の形態は付き添い型、受け渡し型、連絡調整型などがあります。
援助機関は都道府県庁の傘下にある公的機関から、NPO法人などの民間の機関まであります。まずは、お住まいの自治体のホームページなどで利用できる機関はないか調べておきましょう。
面会以外の方法で交流させる
次に、面会以外の方法で交流すること、すなわち、間接交流を実施することです。
間接交流には、負担が少ないものから順に、
- 非監護親が手紙、プレゼントを贈る
- 監護親が非監護親に写真や動画などを送る
- SNSやLINEでメールのやり取りをする
- zoom、Skypeなどで電話する
方法などがあります。
いずれも直接会う必要がないため、子どもはもちろん監護親の負担軽減にもつながります。はじめ間接交流を試してみて、負担がなくなってきたら面会に切り替える、面会と併用することも検討してみてもよいでしょう。
まとめ
今回のまとめです。
- 原則、面会交流は拒否できない
- 正当な理由なく拒否した場合は様々なリスクを受けるおそれがある
- 拒否する前に面会交流の負担を減らす方法を考えてみよう