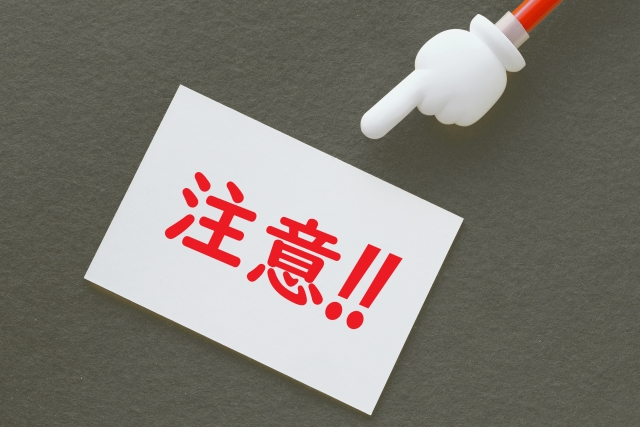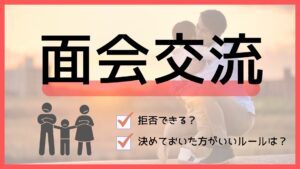- 面会交流の第三者機関って何ですか?
- どこに、どんな機関がありますか?
- どんな支援を受けることができますか?
- 利用するにはどんな手順を踏めばいいですか?
- 注意点はありますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
もし、面会交流することに負担を感じている場合に検討していただきたいことが、面会交流の第三者機関を利用することです。第三者機関を利用すれば、今まで感じていた面会交流の負担を大きく軽減させることができるかもしれません。
そこで、今回は、面会交流の第三者機関について簡単に解説した上で、第三者機関を利用した場合の利用できる支援内容、利用するまでの手順、利用上の注意点について解説していきたいと思います。
この記事を書いた人

-
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。※大変申し訳ありませんが、ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しております。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】
- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説
- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します
- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します
面会交流の第三者機関とは
面会交流の第三者機関とは、子どもと一緒に暮らす親(監護親)と子どもと離れて暮らす親(非監護親)同士で面会交流を実施することが難しい場合に、面会交流をスムーズに実施できるよう、当事者の間に入って面会交流を支援してくれる機関です。
第三者機関の種類
面会交流の第三者機関には自治体が運営主体となっている機関と民間の機関が運営主体となっている機関があります。
自治体による第三者機関(第三者支援事業)は厚生労働省の母子家庭等就業支援・自立支援事業の一環として行われているもので、利用条件を満たせば無料で利用できるのが特徴です。
2019年(令和元年)現在、千葉県、東京都、富山県、静岡市、浜松市、明石市、高松市、北九州市、大分県、熊本市の10つの自治体が支援事業を実施しています。
一方、民間の第三者機関は、有料ではあるものの自治体のような厳格な利用条件がないのが特徴です。どこに、どんな機関があるかお知りになりたい方は、法務省が公表している「面会交流支援団体等の一覧」でご確認ください。
第三者機関の支援内容
第三者機関の主な支援内容は
- 付き添い型
- 受け渡し型
- 連絡(日程)調整型
の3種類です。
なお、第三者機関が提供する支援内容や具体的な支援の方法は第三者機関によって異なります。第三者機関を利用するにあたっては、どんな支援内容を実施しているのか、どんな支援を受けることができるのか、よく確認しておくことが大切です。
付き添い型
付き添い型は、第三者機関の支援員が非監護親と子どもとの面会交流の場に付き添うものです。付き添い型には次の受け渡し型、連絡(日程)調整型の支援も含まれていることもあります。
付き添い型は、たとえば、
・非監護親が面会時に子どもに暴力を振るったり、連れ去ったりしないか心配
・非監護親がルールをきちんと守って面会してくれるか心配
など、監護親が非監護親に不信感を抱いている場合に利用するメリットがあります。
費用は3種類の支援の中で最も高額となります。
受け渡し型
受け渡し型は、面会交流の日時・場所の調整とともに、支援員が受け渡し場所において、子どもの受け渡しをするものです。付き添いまでは行いません。
受け渡し型は、たとえば、
・受け渡し時にお互いに顔を合わせたくない
・DV、モラハラ、浮気・不倫されていた
・子どもが単独で(付添人なしに)非監護親と過ごすことができる年齢に達している
などという場合に利用するメリットがあります。
費用は付き添い型の次に高額となります。
連絡調整型
連絡調整型は、親同士が相互に連絡を取り合うことが難しい場合に、代わりに支援員が双方と連絡を取り合って面会交流の日時、場所等を調整するものです。付き添い、子の受け渡しは行いません。
連絡調整型は、相手と直接の連絡は取りたくないものの、
・子どもが単独で非監護親との待ち合わせ場所まで行くことができ、かつ、非監護親と一定時間過ごすことができる
という場合は利用するメリットがあります。
費用は3つの型の中では一番低額となります。
第三者機関を利用するまでの手順
面会交流の第三者機関を利用して面会交流を実施するまでの流れは次のとおりです(※ご利用機関や状況により異なります)。
① 第三者機関を探す
↓
② 面会交流のルールを考える
↓
③ 相手に話し合いを切り出す
↓
➃ 書面を作成する
↓
⑤ 支援申し込み&事前面談
↓
⑥ 契約(支援決定)
↓
面会交流実施
①第三者機関を探す
まずは、お住いの近くに自治体の第三者機関がないか、ない場合は民間の第三者機関がないか探してみましょう。
第三者機関によって方針、特徴が異なり、独自のルールを定めていますので、事前にホームページを見たり、直接問い合わせするなどして、どんな方針、特徴があるのか、ルールが定められているのか情報収集しておきましょう。
お住いの近くに第三者機関がなく、遠方の第三者機関を利用せざるをえない場合もあります。子どもへの負担、費用のことも考えながら、第三者機関を利用するか否か、利用するとしてどの第三者機関を利用するか考えておきます。
②面会交流のルールを考える
①と並行して、面会交流のルールについても考えておきます。
面会交流のルールとは、たとえば、
・面会交流の頻度(回数)
・面会交流の日時
・利用する第三者機関
・利用する援助の内容
・費用の負担方法
などです。
もっとも、面会交流の頻度は月1回までなどと、あらかじめ第三者機関からルールを指定されている場合はそれにしたがう必要があります。また、第三者機関によっては、支援を受けるにあたって必ず決めておかなければならないルールが指定されていることもあります。ホームページなどでよく確認しておきましょう。
※どの第三者機関を利用するにあたっても「面会交流の実施すること」、「利用する援助内容」、「費用の負担方法」の合意は必須です。よく相手とよく話し合って決めておく必要があります。
③相手に話し合いを切り出す
次に、離婚する場合は離婚の準備が、別居する場合は別居の準備が終わってから相手に話し合いを切り出すのが基本です。
相手に話し合いを切り出す前は面会交流のことはもちろん、それ以外にも様々な準備が必要です。準備不足のまま話し合いを切り出すと話し合いが不十分なまま離婚、別居してしまい、のちのち後悔することにもなりかねませんので注意が必要です。
相手に話し合いを切り出した後は離婚・別居と親権、養育費、婚姻費用、面会交流などの諸条件について話し合い合意を目指します。相手が話し合いに応じず話し合いができない、あるいは話がまとまらない場合は調停を申立て、調停で合意を目指すこともできます。
➃書面を作成する
次に、話し合いで話がまとまったときは合意内容を書面にまとめます。
別居の場合は別居合意書か面会交流契約書、離婚の場合は離婚協議書か離婚公正証書を作成します。一方、調停の場合は調停調書という書面が作成され、謄本を裁判所から取り寄せる必要があります。
第三者機関を利用するにあたっては面会交流を実施することについて合意していることが条件で、第三者機関の中には合意内容を盛り込んだ書面の提出を利用条件としているところもありますので注意が必要です。
⑤支援申込み&事前面談
次に、③・④と並行して、あるいは④の後に第三者機関に連絡を入れ、支援を申し込みます。
ほとんどの第三者機関で、援助開始前に、夫婦それぞれが事前面談を受けることを利用の条件としています。事前面談には費用(3,000円~1万1000円程度)がかかる場合がありますが、夫婦各自で負担します。
合意書面が手元にある場合は事前面談の際にもっていきましょう。事前面談の後に書面を作成したときは、速やかに第三者機関へ提出しましょう。
⑥契約(支援決定)
最後に、第三者機関が、提出された書類や夫婦それぞれから聴き取った内容から、利用条件をクリアしており、支援することが相当と判断した場合は、父・母・第三者機関の3者間で契約を締結します。
利用期間は第三者機関にもよりますが1年とすることが多いです(当事者の合意があれば更新も可能)。契約締結後は合意内容や第三者機関の指示にしたがって面会交流を実施します。
面会交流の第三者機関を利用する際の注意点
最後に、面会交流の第三者機関を利用するときの注意点について解説します。
条件やルールに従う必要がある
まず、第三者機関を利用するには条件やルールにしたがう必要があることです。
自治体の支援を受けるには条件をクリアする必要があります。民間の機関の支援を受けるには、機関独自のルールに従う必要があります。夫婦で第三者機関を利用することに合意できても、条件やルールにしたがえない場合は支援を受けることはできません。
利用するには費用がかかる
次に、民間の第三者機関を利用するには費用がかかることです。
次のとおり、支援の内容や利用する機関によって費用が異なりますので、事前に確認しておきましょう。また、どのように費用を負担するかも話し合って決めておく必要があります。
・付き添い型:15,000円前後~25,000円前後
・受け渡し型:10,000円前後~15,000円前後
・連絡調整型:10,000円未満(3,000円程度)
利用期間に制限がある
最後に、ほとんどの第三者機関で利用期間に制限が設けられていることです。
第三者機関による支援は、最終的には支援に頼ることなく親だけで面会交流を実施できるようになることを目標としていますから、いつまでも第三者機関を利用できるわけではありません。利用期間は何年か、利用期間に制限が設けられている場合、更新は可能かなど、利用する前にしっかりチェックしておきましょう。
まとめ
今回のまとめです。
- 面会交流の第三者機関とは面会交流の実施をサポートしてくれる機関
- 第三者機関には自治体が母体の機関と民間が運営する機関がある
- 主な支援内容は「付き添い型」、「受け渡し型」、「連絡調整型」にわけられる
- 第三者機関を利用するにあたっては、夫婦で面会交流の実施、利用する援助内容、費用負担に関する合意が必要
- 第三者機関を利用するときの注意点にも注意する