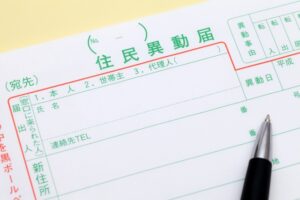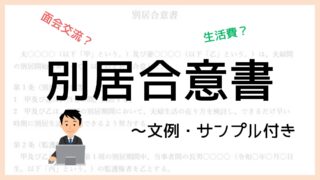
- 別居合意書って何ですか?
- 作った方がいいですか?
- どういう手順で作ればいいですか?
- どんな内容を盛り込むべきですか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
別居するとき相手と書面を取り交わしましょう、といってもいまいちピンとこない方も多いかもしれません。夫婦関係がこじれた場合、一刻もはやく別居したいと考える方は多いはずです。
しかし、一定の場合を除き、別居前にきちんと取り決めをしておかないと、別居後の生活に困り別居したことに後悔してしまうことにもなりかねません。別居合意書は、別居後の生活を安心して送るためのツールの一つといえます。
今回は、この別居合意書とは何か、作るメリットは何か、どういう手順で作ればよいのか、どんな内容を盛り込めばいいのかについて詳しく解説していきたいと思います。
この記事を書いた人

-
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】
- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説
- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します
- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します
別居合意書とは
別居合意書とは別居するにあたって夫婦で話し合って取り決めておくべき項目・内容(ルール)を取りまとめた書面です。別居合意書は契約書の一種ですから、書面を取り交わした後は、夫婦は書面に書かれたルールを守って生活していかなければいけません。別居合意書ではなく、別居時合意書、別居契約書、婚姻費用分担に関する合意書(契約書)などという標題をつけることもできます。
別居合意書をおすすめする理由
後述する「別居合意書を作らない方がよいケース」を除き、別居合意書を作っておくことをおすすめします。理由は次のとおりです。
夫婦で話し合うようになれる
まず、夫婦で別居中のルールについて話し合うようになれることです。
DVを受けているなど一定の例外を除いて、別居するにあたっては夫婦で別居中のルールについてきちんと話し合い、取り決めておくべきです。きちんとルールを取り決めておかなければ、お金を受け取る側はお金の不安、子どもと離れて暮らす側は子どもとの交流についての不安を抱えたまま別居することになってしまいます。
別居するということは夫婦関係があまりよくなく、まともに話し合える状況ではないかもしれませんが、だからこそ別居する前にきちんと話し合っておくべきともいえます。別居合意書を作るにあたっては夫婦の話し合いが必要ですから、別居合意書を作ることになれば夫婦できちんと向き合って話し合えるようになれることが期待できます。
トラブルを防止できる
次に、言った・言わないのトラブルを防止できることです。
仮に、別居中のルールについて話し合えたとしても、何をどう話し合って決めたかなど、一から十まで事細かに記憶しておくことなど無理があります。口約束だけに終わらせてしまうと、お互いに記憶が曖昧になり後で言った・言わないのトラブルとなる可能性があります。
別居合意書に盛り込む項目の中には婚姻費用などをはじめ、別居後の生活に直結するものもあります。それらを口約束だけに終わらせてしまうと、相手にきちんとルールを守らせることができず別居後の生活に困ってしまいます。別居後の生活を安心して送るためにも、別居合意書を作っておく意義があります。
別居の経緯・理由を共有できる
次に、なぜ別居することになってしまったのか、夫婦で別居の経緯・理由を共有できることです。
少しでも修復の可能性を残して別居するときは、夫婦でこれまでの夫婦生活を振り返り、何が原因で別居することになってしまったのかきちんと話し合っておくべきです。その上で、別居期間中に改善して欲しいことを確認し合い、別居合意書にもその旨を書いておけば、別居期間をより有意義に過ごすことができるはずです。
もし、不倫など、相手に一方的な原因があるときにも別居前に相手に原因があることを指摘し、相手に認めさせてその旨を別居合意書に書いておけば、万が一離婚となったときでも別居合意書を交渉の武器として使うことができます。また、不倫などの違法行為に対する歯止めにもなる可能性があります。
別居合意書を作らない方がよいケース
一方で、別居合意書を作らない方がいいケースもあります。別居合意書を作らない方がいいケースとは次のケースです。
離婚の意思が固い場合
まず、離婚の意思が固い場合です。
別居合意書を作るのはわずかでも修復の可能性があって別居する場合です。修復目的で離婚する場合は、お互いにこれまでの関係を見つめ直したり、相手に反省を促すことができます。万が一離婚することになった場合のことを考えて、別居合意書に盛り込む内容を工夫することもできます。
一方、離婚の意思が固い場合はお互いにこれまでの関係を見つめ直したり、相手に反省を促すことは意味がありません。離婚の意思が固い場合は、別居するかどうかは別にして早急に離婚の準備を進め、準備が整った段階で相手に離婚を切り出すべきです。離婚の意思が固いにもかかわらず別居合意書を作ると、修復の気持ちがあるのでは?と思われてしまう可能性があります。
相手が別居に合意しない場合
次に、相手が別居に合意しない場合です。
有効な別居合意書を完成させるには、相手の協力(サインなど)が不可欠です。しかし、相手が別居に合意しない場合は相手の協力を得られず有効な別居合意書を作ることができません。
なお、DVなど緊急性の高い場合を除き、相手が別居に合意しないからといって相手に無断で別居することは極力避けた方が無難です。相手に無断で別居することは、相手の反感を買うばかりか、夫婦の同居義務や協力・扶助義務に反することにもなりかねません。
相手の合意は得ないにしても、のちの離婚協議や調停などで不利にならないよう、置き手紙などの書面を残し、その状況を写メにとっておくなどの対策が必要です。
DV、虐待を受けている場合
次に、DV、虐待を受けている場合です。
この場合は別居合意書を作ることよりも、あなたやお子さんの身の安全を確保することが最優先です。暴力的な相手に話し合いや別居合意書の作成をもちかけても火に油を注ぐだけで、まったく効果がありません。なお、相手との話し合いは別居して、身の安全を確保してからです。弁護士などの第三者を介した方が安全です。
別居合意書(原案)を作るまでの手順
別居合意書を作るには、そもそも別居することが正しい選択なのか検討することからはじめる必要があります。また、仮に別居を選択するとしても、いきなり相手に別居を切り出すのではなく、別居の準備を整えてから切り出すべきです(ただし、DVを受けているなど避難の緊急性の高い場合を除きます)。別居の準備の最終段階で別居合意書(原案)を作っておくと、別居の話し合いがスムーズにいく可能性があります。
続きをお読みいただくには・・・
大変申し訳ありませんが、ここから先は有料コンテンツとなっています。お手数ではありますが、ご購読ご希望の方は以下の「購入」をタップしていただき、ご購入手続きをお願いいたします。
【コンテンツご購入のメリット】
・契約書面作成のプロである行政書士が別居合意書の書き方を直接執筆(解説)
・できる限りわかりやすい言葉で別居合意書の作り方を詳しく解説
・初めての方でも専門家に頼らず作成できる
・別居合意書のサンプルを無料でダウンロードできる
・公正証書にするまでの流れがわかる
【有料コンテンツの目次】
6 別居合意書に書くべき内容
6-1 全体像
6-2 標題、導入
6-3 別居の合意等
6-4 監護者
6-5 別居の経緯
6-6 婚姻費用の分担
6-7 面会交流
6-8 別居中の共有財産の処分
6-9 別居中の誓約事項
6-10 違反した場合の制裁
7 別居合意書のサンプル(無料ダウンロード)
8 別居合意書は公正証書にしよう
9 別居合意書に関する注意点
10 まとめ