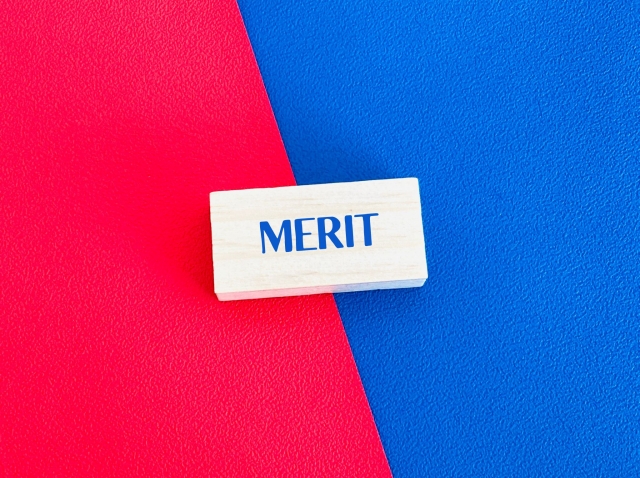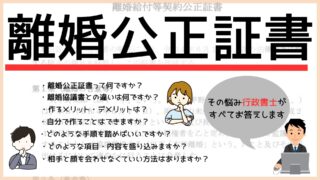
- 離婚公正証書ってどんな書面ですか?
- 離婚協議書とどう違いますか?
- 離婚公正証書を作るメリット・デメリットは何ですか?
- 離婚公正証書を作り方を教えてください
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
離婚するにあたって公正証書を作った方がいい、という話は耳にしたことがあるかもしれません。ただ、離婚公正証書という書面がどんな書面で、作ることにどんなメリット(デメリット)があるのかわからないという方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、離婚公正証書がどんな書面で、何のために作る書面なのか、離婚協議書とどう違うのか、作るメリット・デメリットは何か、作るまでにどんな手順を踏めばよいかなど、離婚公正証書に関する必要な情報をまとめて解説します。
この記事をお読みいただければ公正証書について詳しくなっていただけると思いますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。
この記事を書いた人

-
※ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しています。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025年11月30日示談書不倫慰謝料請求を内容証明でする方法
- 2025年11月28日示談書不倫慰謝料の時効は何年?
- 2025年11月28日示談書不倫相手の住所の調べ方
- 2025年11月27日示談書不倫相手との話し合いを進めるためのコツは?
離婚公正証書とは?
離婚公正証書とは離婚の条件などをまとめた公文書のことです。公証人という公証役場に勤める人が作ります。正確には「離婚給付等契約公正証書」といいます。
離婚公正証書の内容
離婚公正証書には、一般的には次の内容が盛り込まれます。
・離婚等の合意
・親権者の指定
・養育費
・財産分与
・慰謝料
・面会交流
・通知義務
・禁止事項
・清算条項
・強制執行の認諾文言
これらの内容のうち、あらかじめ夫婦で話し合って合意した内容を離婚公正証書に盛り込みます。法的に無効な内容や記載する意義が乏しい内容などは盛り込むことができません。離婚公正証書にどんな項目や内容を盛り込むかは、公正証書を作成する公証人の判断に委ねられます。
「強制執行の認諾文言」とは、「養育費などの金銭の支払いを怠った際に、強制執行の手続きをとられてもかまわない」という相手(養育費などの支払義務者)が承諾した文言のことです。この文言を離婚公正証書に盛り込むことで、裁判を経ずに強制執行などの法的手続きをとることが可能になります。
離婚公正証書と離婚協議書との違い
協議離婚で作成する書面としては離婚公正証書のほか離婚協議書があります。書面に盛り込む内容は大きな違いはありません。しかし、次のとおり、いくつかの点で違いがあります。
| 離婚公正証書 | 離婚協議書 | |
| 書面の種類 | 公文書 | 私文書 |
| 作成場所 | 公証役場(※1) | どこでも |
| 作成する人 | 公証人 | 離婚当事者 |
| 作成費用 | かかる | 基本はかからない(※2) |
| 書面の保管方法 | 公証役場に保管される | 離婚当事者が一部ずつ保管 |
| 証明力 | 高い | 離婚公正証書より低い |
| 強制力 | ある | ない |
※1 公正証書のデジタル制度(2025年10月1日~)を使うことができれば、公証役場にいかなくても公正証書を作成できるようになります。
※2 専門家に作成を依頼した場合は費用がかかります。
離婚公正証書のメリット
離婚公正証書のメリットは次のとおりです。
財産の差押えが簡単になる
まず、相手が養育費などのお金を払わなくなった場合に、相手の給与などの財産を差し押さえる手続きが簡単になることです。
通常、相手の財産を差し押さえるには次のステップを踏む必要があります。
①調停or裁判を起こす
↓
②債務名義(※)を取得する
↓
③裁判所に財産の差押え手続きを申し立てる
↓
➃裁判所から差押命令を取得する
※相手にお金の支払いを請求できる権利があることを公的に証明してくれる文書
相手の財産を差し押さえるには債務名義という書面を取得する必要があります。その債務名義を取得するには調停や裁判を起こす必要があります。しかし、離婚公正証書自体が債務名義となりますから、離婚公正証書を作っておけば調停や裁判を起こす必要がなくなるというわけです(①、②を省略できる)。
差押え手続きが1回で済む
次に、相手の財産を差し押さえる手続きが1回で済むことです(ただし、養育費の未払いがあった場合に限ります)。
通常、支払期限が過ぎたお金ごとに財産の差押え手続きをとらなければいけませんが、養育費の未払いがあった場合は、1回の差押えで、その後に支払期限がくる養育費についても差押えの効力を及ぼすことができます(※)。差押えの手続きが1回で済むということは、差押え手続きの申立費用の節約や申立ての手間・労力の負担軽減にもつながり、養育費を請求する側(権利者)にとって大きなメリットといえます。
※「毎月25日までに3万円の養育費を払う」との合意内容の場合
(通常)
例:6月26日以降(未払い)→差押え→7月26日以降→未払い→差押え・・・・・
(離婚公正証書)
例:6月26日以降(未払い)→差押え(7月26日以降分の未払いにも差押えの効力が及ぶ)
給与を多く差し押さえることができる
次に、これも養育費の未払いがあった場合に限っての話ですが、通常よりも給与を多く差し押さえることができることです。
給与は義務者の生活費の一部に充てられることから、通常、給与(源泉徴収額を差し引いた額)の4分の1までしか差し押さえることができないことになっています。しかし、養育費の未払いがあった場合は給与の2分の1まで差し押さえることが認められています。ただし、差し押さえることができる金額は養育費の未払額の範囲内の金額に限ります。
相手の財産を開示させる手続きが使える
次に、相手の財産を開示させる手続き(財産開示手続)が使えることです。
相手の財産を差し押さえるといっても、まずは相手が今現在どんな財産をもっているのかを明らかにしなければいけません。この点、相手が財産の開示請求に応じ、すべて開示してくれれば問題はないのですが、お金の未払いが続いている場合は期待できません。そこで、裁判所を通じて相手に財産を開示させる制度が用意されています。離婚公正証書を作っておけばこの制度の利用を申し立てることができます。

相手が正当な理由なく裁判所からの出頭要請に応じない場合は「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が科されることがあります。
参照:財産開示手続 | 裁判所
第三者から情報を取得する手続きが使える
次に、第三者から情報を取得する手続き(第三者からの情報取得手続)が使えることです。
たとえば、給与を差し押さえるにあたっては、今現在の相手の勤務先の情報を明らかにする必要があります。しかし、相手は正直に教えたりはしないでしょう.。そこで設けられた制度が第三者からの情報取得手続です。給与を差し押さえる場合は市区町村または日本年金機構など厚生年金を扱う団体(第三者)、あるいはその両者から相手の勤務先の情報を取得します。離婚公正証書を作っておけば、裁判所に第三者からの情報取得手続を申し立てることができます。
相手の任意の支払を期待できる
次に、相手の任意の支払を期待できることです。
これまでみてきておわかりいただけるように、離婚公正証書を作っておけば様々な強制手段をとることができます。仮に、給与が差押えられると、当然のことながら相手が使えるお金は減ります。差押えの通知は相手の勤務先にも届きますから、仕事にも何かしらの影響が出てくるかもしれません。こうした事態を避けるために、相手に「お金を払おう」という気にさせることができることが離婚公正証書を作っておく最大のメリットといえます。
公証役場で保管される
最後に、離婚公正証書の原本は公証役場で保管されることです。保管期間は原則20年です。
離婚協議書だと紛失の可能性があります。一方、離婚公正証書の場合、写しは、調印日(離婚公正証書にサインする日)当日に、公証人から夫婦に手渡され、原本は公証役場で保管されます。万が一、写しを紛失したとしても、原本が保存されている限り、申請して再発行してもらうことができます。
なお、公正証書のデジタル制度(2025年10月1日~)を使うと、離婚公正証書(原本)は電子データで作成、保管されます。一方、離婚公正証書の証明情報は電子データでも紙媒体のどちらでも受け取ることができます。
離婚公正証書のデメリット
一方、離婚公正証書のデメリットは次のとおりです。
夫婦間での話し合いが必要
まず、夫婦の話し合いが必要なことです。
離婚公正証書の作成にあたっては、夫婦で離婚と養育費などの離婚条件について話し合い、離婚公正証書に盛り込みたい内容を考えておく必要があります。調停での調停委員と違い、公証人が夫婦の間に入って話をまとめてくれるわけではありません。
相手の協力が必要
次に、離婚公正証書を作るには相手の協力が必要なことです。
そもそも相手の同意がなければ離婚公正証書を作成することはできません。強制執行認諾文言を盛り込むには相手の承諾も必要です。離婚公正証書の調印日には、お互い公証役場に出向いて調印しなければならないのが基本です(公証役場によっては代理人による手続きを認めるところもあります)。

なお、公正証書のデジタル化(2025年10月1日~)により、公証役場に出向かなくても離婚公正証書を作成できるようになります。この制度を使うには一定の条件をクリアする必要がありますが、使うことができれば公証役場で顔を合わさなければならないなどの、お互いの負担を減らすことができるでしょう。
費用がかかる
最後に、費用がかかることです。
離婚公正証書を作成するには公証役場に作成費用を支払う必要があります。離婚公正証書の作成費用は「基本手数料」+「データ・用紙代」+「送達手数料」+「送達証明書の発行費用」+「年金分割合意証書の作成費用」から成ります。
基本手数料
基本手数料は目的価額によって変動します。目的価額とは相手に何らかの請求をすることによって得られる利益(相手からすれば失われる不利益)のことです。
たとえば、離婚公正証書に350万円の慰謝料を請求する旨を記載すれば350万円が目的価額となり、(旧)基準では基本手数料は1万1000円、(新)基準では1万3000円となります。
※以下の表は左右にスクロールして見ることができます。
| 目的価額 | (旧)基本手数料 | (新)基本手数料(2025年10月1日~) |
| ~50万円まで | なし | 3000円 |
| ~100万円まで | 5000円 | 5000円 |
| ~200万円まで | 7000円 | 7000円 |
| ~500万円まで | 1万1000円 | 1万円3000円 |
| ~1000万円まで | 1万7000円 | 2万円 |
| ~3000万円まで | 2万3000円 | 2万6000円 |
| ~5000万円まで | 2万9000円 | 3万3000円 |
| ~1億円まで | 4万3000円 | 4万9000円 |
| ~3億円まで | 4万3000円に超過額5000万円ごとに1万3000円を加算 | 4万9000円+超過額5000万円ごとに1万5000円を加算 |
| ~10億円まで | 9万5000円に超過額5000万円ごとに1万1000円を加算 | 10万9000円+超過額5000万円ごとに1万3000円を加算 |
| 10億円超~ | 24万9000円に超過額5000万円ごとに8000円を加算 | 29万1000円+超過額5000万円ごとに9000円を加算 |
なお、養育費を分割で支払う旨の合意をした場合、(旧)基準では「月々の金額×12カ月(10年を超える場合は10年)×子どもの数」で目的価額を計算していました。
一方、(新)基準では「10年」の箇所が「5年」に短縮されます。たとえば、以下のケースで(新)基準に沿って計算すると、基本手数料は2万円となります。
【例】
慰謝料350万円
養育費360万円(月々3万円、10年間、子ども2人)
=3×60か月(=12カ月×5年)×2
↓
目的価額 :710万円
基本手数料:2万円
データ・用紙代
離婚公正証書を紙で作成した場合、「原本」、「正本」、「謄本」(※)の3種類が作成されます。(旧)基準では、原本は4ページ目まで無料です。正本と謄本は1ページ目から250円です。
一方、(新)基準では、正本と謄本は1ページ目から300円です。また、離婚公正証書を電子データで作成した場合、電子データ代として1件につき2500円がかかります。
※正本とは原本と同じ効力がある写し、謄本は原本と同じ効力がない原本の写しです。
送達手数料
送達手数料は公証役場が謄本を義務者に送るときにかかる事務手数料です。送達の方法には公証役場で義務者に直接手渡す「交付送達」と郵送で送達する「特別送達」があります。交付送達の場合は1,400円が特別送達の場合は1,400円に加えて1,110円~1,240円の郵便代がかかります。
送達証明書の発行費用
送達証明書とは、公証役場が離婚公正証書の謄本を義務者に送達したことを証明する書面です。送達証明書は、後日、強制執行の手続きをとる際に必要となる書面ですので、必ず交付を受けておきます。交付送達する場合は、当日申請すればその場で交付を受けることができます。この送達証明書の発行手数料として250円かかります。
年金分割合意証書の作成費用
離婚するにあたって年金分割について合意する場合は、離婚公正証書とは別に年金分割合意証書を作成します。年金分割合意証書の作成費用は5,500円です(離婚公正証書の中に年金分割の条項を盛り込んだ場合は11,000円かかってしまいます)。
費用の支払い方法
かつては現金での支払いしか対応してくれませんでしたが、今はインターネットバンキングやクレジットカード払いにも対応しています。離婚公正証書の作成費用の概算は公証人との面談時に、正確な金額は公証人が離婚公正証書の原案を作成した後に教えてもらえます。
なお、費用を誰が負担するかについては決まりがありません。話し合いによって折半、または、夫婦のいずれか一方が負担するとしてもかまいませんが、離婚公正証書の作成を希望する側(養育費などの金銭の請求権者)が負担するのが通常です。

お住いの自治体によっては一部公費で負担してくれるところもあります。
離婚公正証書を作成するまでの流れ
離婚公正証書を作成するまでの基本的な流れは次のとおりです。
①離婚の準備をする
・離婚協議書の原案(※)を作成する
※公証人が公正証書を作る際に参考にされます
・必要書類(証拠資料)を集める
↓
②話し合いをする →調停?
↓
③原案を完成させる
↓
➃必要書類を準備する
↓
⑤公証役場に作成を依頼する
・公証人との面談
・必要書類の提出
↓
⑥公証人が公正証書の原案を作成する
↓
⑦公証役場で公正証書にサインする
①離婚の準備をする
まず、離婚を思い立った段階で、相手に離婚を切り出す前に離婚の準備にとりかかります。離婚後の生活、お金の準備とともに離婚に必要な情報や証拠を収集し、相手と話し合う準備をします。
②話し合いをする
次に、離婚の準備が終わり、離婚後の生活の不安を取り除くことができ、離婚しても後悔しないと決心できた段階で相手に離婚を切り出します。その後は離婚や養育費など諸条件について話し合います。
③原案を完成させる
相手との話し合いで離婚と離婚条件について合意できたら、合意内容を紙にまとめます。ここで作成するものは離婚協議書のようなきちんとしたものがベストですが、難しい場合はメモ書き程度でもよいでしょう。
④必要書類を準備する
③と同時に公証役場に提出する必要書類を準備します。どんな書類を準備すべきなのかわからない場合は事前に公証役場に問い合わせて確認しておくと安心です。必要書類は公証人との面談のときにもっていくのが理想ですが、準備できない場合は面談後に追加で提出することもできます。
(共通)
・合意内容をまとめた書面(離婚協議書、公正証書の原案)
・印鑑証明書(※調印日からさかのぼって3か月以内に発行されたもの)
・顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
(親権関連)
・戸籍謄本(※調印日からさかのぼって3か月以内に発行されたもの)
(財産分与関連)
預貯金に関する書類
・通帳の写し
・残高証明書
【関連記事】
・財産分与と預貯金 | 隠し口座の調べ方
不動産に関する書類
・不動産登記簿謄本
・固定資産税納税通知または固定資産評価証明書
・金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書、住宅ローン約款)
・住宅ローンの償還表
【関連記事】
・家の財産分与 | 住宅ローン残債がある、ない場合にわけて解説
車に関する書類
・車検証
・車の査定証
・ローンの償還表
【関連記事】
・車の財産分与 | ローンがある場合の査定の方法、名義変更のやり方
生命保険、学資保険に関する書類
・保険証券または保険証書
・解約返戻金証明書
【関連記事】
・生命保険は財産分与の対象?契約者・受取人は変更できる?
・学資保険は財産分与の対象になる?
(年金分割関連)
・基礎年金番号がわかるもの(年金証書または基礎年金番号通知書)
・年金分割のための情報提供通知書
【関連記事】
・離婚の年金分割とは | しないとどうなる?
(手続きを代理人に任せる場合)
・委任する本人の印鑑証明書(※調印日からさかのぼって3か月以内に発行されたもの)
・本人から代理人への委任状(離婚公正証書原案用と年金分割合意書用(※年金分割する場合))
・代理人の身分を確認できるもの(印鑑証明書及び実印または顔写真付きの身分証明書)
【関連記事】
・公正証書と代理人
⑤公証役場に作成を依頼する
③、④が終わったら公証役場に公証人との面談の予約を入れます。デジタル制度を使うことができる場合はwebでの予約や本人確認も可能です。予約を入れる公証役場は、調印日に夫婦で公証役場に出向く必要がある場合はお互いにとって利便性が高い公証役場を選ぶことになります。一方、デジタル制度を使うことができる場合は、公証役場に足を運ぶ必要がないため、どの公証役場でもかまいません。
⑥公証人が離婚公正証書の原案を作成する
公証役場に離婚公正証書の作成を依頼後、公証人が③、④や面談時の聴取結果をもとに離婚公正証書の原案を作成します。依頼の申込みから原案の作成までにははやくて1週間以内、長くて1週間~2週間前後かかります。公証人が離婚公正証書の原案を作ると、メールまたはFAXで原案が送られてきますので内容を確認します(原案は相手にも送られています)。修正してもらいたい点がある場合は、公証人にその旨申し出ます。デジタル制度を使うことができる場合はパソコンを使って、公証人とやり取りできます。
関連記事
⑦公証役場で離婚公正証書にサインする
夫婦それぞれが離婚公正証書の原案を確認し内容に合意できる場合は、離婚公正証書にサインする手続きに移行します。デジタル制度を使うことができる場合は、公証人からメールで送られてきたPDFファイルに電子サイトします。一方、公証役場に出向く場合は調印日(離婚公正証書にサインする日)を公証人と調整し、調印日に公正証書に出向いてサインします。デジタル制度を使うことができる場合は、離婚公正証書の証明情報を電子データで受けることができます。もっとも、希望すれば紙で受けることもできます。
離婚公正証書に関するよくある疑問
最後に、離婚公正証書に関してよくある疑問にお答えします。
手続きを代理人に任せることはできますか?
代理人による手続きを認める公証役場であれば可能です。代理人に依頼する場合は行政書士や弁護士などの専門家に依頼しましょう。
関連記事
一度作った公正証書を変更することはできますか?
変更できますが、変更する項目によって手続きが異なります。養育費については、変更に合意できれば変更に関する新しい公正証書を作ります。一方、親権については、必ず調停を申し立てる必要があります。
離婚後でも公正証書を作ることはできますか?
可能です。ただし、離婚前と同じく相手の同意を得る必要があります。離婚してから間が空いていると相手の同意を得られない可能性があります。また、財産分与などの請求期限にも注意する必要があります。
行政書士と弁護士、どちらに依頼すべきですか?
書面(公正証書の原案)作成と作成手続きの代理のみ依頼するのであれば、行政書士、弁護士いずれにでも依頼できます。加えて相手との交渉も依頼した場合は、弁護士に依頼する必要があります。