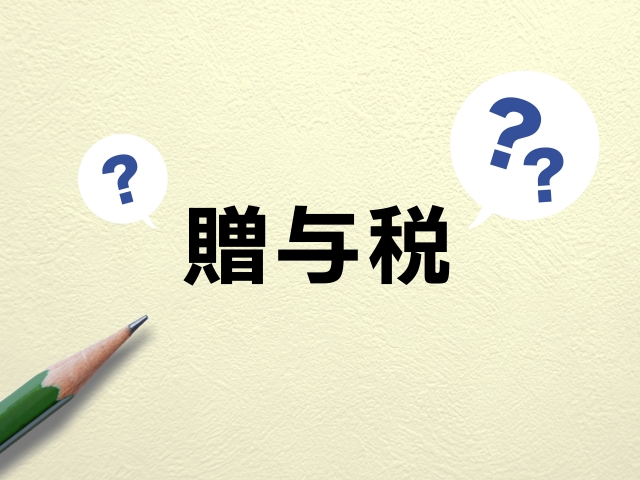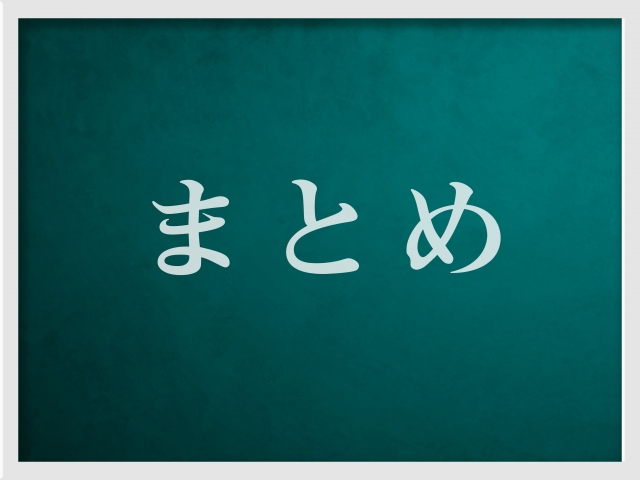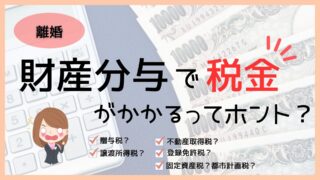
- 財産分与で税金がかかるって本当ですか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
財産を受け取るときに頭に入れておかなければならないことが税金です。財産分与でも例外ではありません。では、財産分与すると税金がかかることはあるのでしょうか?
今回は、財産分与される側、する側にわけて、税金がかかるのか、かかる場合はどんなケースでどんな税金がかかるのか、税金がかからないようにするにはどのような対策が必要か、詳しく解説していきたいと思います。
関連記事
この記事を書いた人

-
※ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しています。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025年11月30日示談書不倫慰謝料請求を内容証明でする方法
- 2025年11月28日示談書不倫慰謝料の時効は何年?
- 2025年11月28日示談書不倫相手の住所の調べ方
- 2025年11月27日示談書不倫相手との話し合いを進めるためのコツは?
【原則】財産分与される側には税金はかからない
まず、財産分与される側にかかる税金として考えられるのが「贈与税」ですが、原則として、財産分与される側には贈与税はかかりません。なぜなら、贈与税は相手からただで財産をもらったときにかかる税金ですが、財産分与で受けた財産は相手からただでもらった財産とはいえないからです。
参照:No.4414 離婚して財産をもらったとき | 国税庁
【例外】財産分与される側に税金がかかるケース
ただし、次の場合には税金がかかる可能性があります。
財産分与された財産の額が多すぎる場合:贈与税
まず、財産分与された財産の額が婚姻中に夫婦で築いた財産の額やその他すべての事情を考慮しても多すぎる場合です。
たとえば、婚姻期間が短く、夫婦で築いた財産があるとはいえないにもかかわらず、相手から受けた財産の額が多すぎる場合です。この場合、財産分与ではなく贈与によって財産を受け取ったと判断され、多すぎる部分について贈与税がかかる可能性があります。
脱税目的で離婚したと認められる場合:贈与税
次に、贈与税を免れるために離婚したと判断された場合です。
たとえば、離婚のときに財産分与で相手に財産を移転させたものの、その後すぐに同じ相手と再婚した、離婚した後も同居生活を続けていた、という場合は贈与税を免れる目的で離婚したと判断され、贈与税がかかる可能性があります。
慰謝料の代わりとして不動産を譲り受けた場合:不動産取得税
次に、慰謝料を金銭で受け取る代わりとして不動産を譲り受けた場合です。
不動産取得税は不動産を「取得」した場合にかかる税金ですが、上記の場合はまさに不動産を「取得」したといえるからです。一方、財産分与で不動産を譲り受ける場合は不動産取得税はかかりません。これは財産分与が夫婦の共有財産を「清算」するものであって「取得」とはいえないからです。
財産分与で不動産を譲り受けた場合:登録免許税、固定資産税
次に、財産分与で不動産を譲り受けた場合です。
先ほど述べたとおり、不動産取得税はかかりませんが、登録免許税、固定資産税がかかります。登録免許税とは不動産登記を行うときにかかる税金です。譲渡者と連帯して負担するのが原則です。固定資産税はその年の1月1日時点の不動産の所有者にかかる税金です。固定資産税は不動産を所有し続ける限り、払い続けていく必要があります。
財産分与する側に税金はかかる?
一方、財産分与する側にかかる税金として考えられるのが「譲渡所得税(及び住民税)」と「登録免許税」です。登録免許税は譲受人と連帯して負担するのが原則です。
譲渡所得税がかかる資産
譲渡所得税がかかる資産は
- 不動産
- 書画骨董
- 絵画
- 宝石
- 自動車
- 船舶
- 機械器具
- ゴルフ会員権
- 特許権
- 著作権
などです。金銭や貸付金、売掛金などの金銭債権には譲渡所得税はかかりません。したがって、税金対策の観点からみれば、現物で財産分与するより、金銭で財産分与した方がよいということになります。
譲渡所得税がかかる場合
財産分与で資産を譲渡した場合、財産分与した時(基準時※協議離婚の場合は協議離婚成立時)の価額(時価)により資産を譲渡したことになります(所得税基本通達33-1の4)。そして、財産分与時の時価が「資産の取得費と譲渡費用」(及び「特別控除額」の合計額)を上回る場合に税金がかかります(譲渡所得に税率をかけた金額が譲渡所得税となります)。
譲渡所得=財産分与時の時価-(資産の取得費+譲渡費用)-(特別控除額)
資産の取得費とは、資産の購入代金や取得のためにかかった付随費用(仲介手数料、登録免許税、印紙税など)です。取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができます。
譲渡費用とは、資産を譲渡するために直接かかった費用(賃借人への立退料、仲介手数料、印紙税、取り壊し費用など)です。
特別控除額とは、一定の要件(※)を満たす場合に最大3000万円の控除を受けることができる特例です。「譲渡先が配偶者でないこと」が要件の一つであるため、離婚前に配偶者へ譲渡してしまうとこの特例を受けることができません。
※居住用財産の3000万円の特別控除の要件
・譲渡先が配偶者や親子などの特別な関係者でないこと
・居住しなくなって売るときは、居住しなくなった日から3年経過後の12月31日までに譲渡していること
・前年、前々年に居住用財産の特例を受けていないこと
譲渡所得税の計算方法
譲渡取得税は
譲渡取得税=譲渡取得×税率
で計算します。
譲渡所得は先ほど解説した方法で求めます。税率は不動産の所有期間によって異なります。不動産を譲渡した年の1月1日時点において、不動産の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得の税率、5年を超えている場合は長期譲渡所得の税率が適用されます。
| 所得税 | 住民税 | 合計 | |
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% | 39%(※1) |
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% | 20%(※2) |
※1 別途、復興特別所得税0.63%が加算されます。
※2 別途、復興特別所得税0.315%が加算されます。
たとえば、財産分与時の時価「3000万円」、取得時の価額(取得費用)「2000万円」、譲渡費用「200万円」、不動産の所有期間10年の不動産の譲渡所得税は
162万5,200円=3000万円-(2000万円+200万円)×20.315
となります。もっとも、特例を適用することができ、控除額が譲渡所得以上だった場合には譲渡所得税はかかりません。
財産分与で税金がかからないようにするための対策
最後に、財産分与で税金がかからないようにするための対策について解説します。
現金、金銭で財産分与する
まず、現金、金銭で財産分与することです。
先ほど述べたとおり、不動産など現物で財産分与すると譲渡所得税がかかる可能性があります。
妥当な額、財産で合意する
次に、妥当な額、財産で合意することです。
この点もすでに述べたとおり、あまりにも過大な額、財産を受け取ると贈与税がかかる可能性があります。妥当な額、財産で財産分与したことを証明するために離婚協議書や公正証書を作っておくことも対策の一つです。
各種特例を活用する
最後に、各種特例を活用することです。
使える特例としては、「(贈与税の)基礎控除(①)」、「(贈与税の)配偶者控除(②)」、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例(③)」、「長期譲渡所得の軽減税率の特例(④)」があります。
| 対象税金 | 内容 | 主な条件等 | |
| ① | 贈与税 | 1年間の贈与額が110万円までは、贈与税が課されない | |
| ② | 贈与税 | ①とは別に2000万円までは贈与税が課されない | 居住用不動産の贈与/婚姻期間が20年以上/相手が配偶者であること/贈与税の申告が必要 |
| ③ | 譲渡所得税 | 譲渡所得の金額から最高3000万円までを控除できる | 居住用財産の譲渡/譲渡先が配偶者や親子等ではないこと/確定申告が必要/④との併用が可能 |
| ④ | 譲渡所得税 | 通常の長期譲渡所得の税率よりも低い税率となる(※) | 居住用財産を譲渡/譲渡先が配偶者や親子等ではないこと/譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること |
※③適用後の課税譲渡所得額が6000万円以下で所得税10%・住民税4%、6000万円超で所得税15%・住民税5%
※②の特例を受けるには、贈与された人が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、お住いの住所地を管轄する税務署に確定申告しなければいけません
※③・➃の特定を受けるには、譲渡する人が、譲渡した年の翌年の2月16日から3月15日までに、納税地の税務署に確定申告しなければいけません
まとめ
今回のまとめです。
- 財産分与される側には税金はかからないのが基本
- 譲渡する資産によっては財産分与する側に税金がかかる
- 不動産を財産分与する(した)ときは、分与される側、する側に税金がかかる