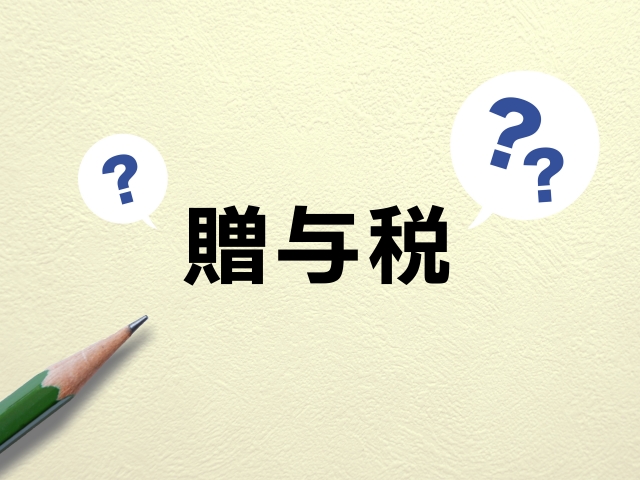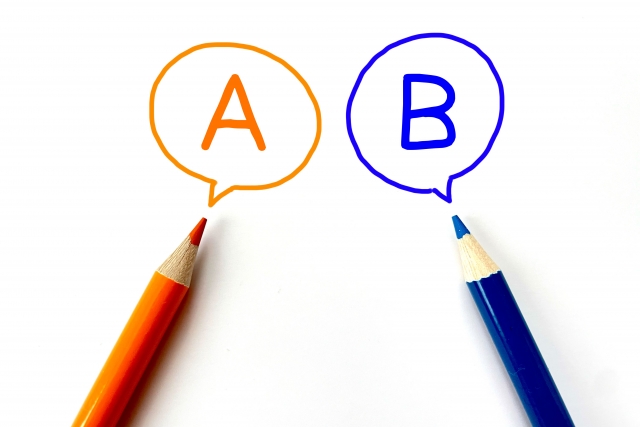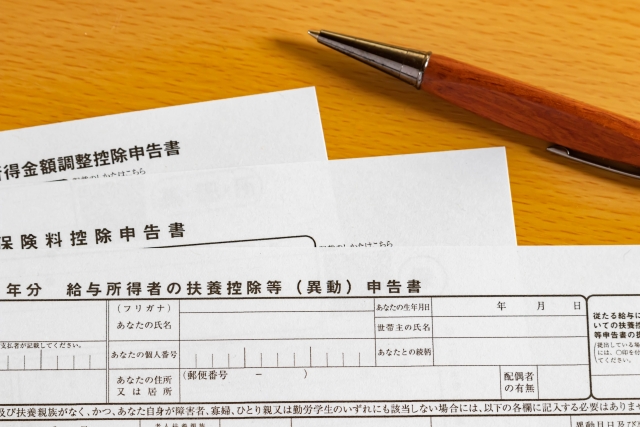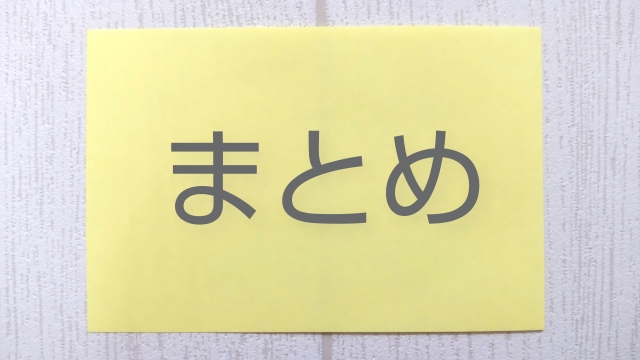- 養育費を受け取ると税金がかかりますか?
- 所得税はかかる?贈与税はかかる?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
養育費は離婚後の収入の一部となります。そのため、給与と同じく所得税などの税金がかからないか疑問に思われる方もいるのではないでしょうか?そこで、今回は、養育費に税金がかかるのか、かかる場合に税金はどのように計算されるのか、税金面で養育費を払う側に何か影響はないか、解説していきたいと思います。
この記事を書いた人

-
※ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しています。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025年11月30日示談書不倫慰謝料請求を内容証明でする方法
- 2025年11月28日示談書不倫慰謝料の時効は何年?
- 2025年11月28日示談書不倫相手の住所の調べ方
- 2025年11月27日示談書不倫相手との話し合いを進めるためのコツは?
養育費に税金はかかる?
まず、お金を受け取ったときにかかる税金として考えられるのは所得税と贈与税です。そこで、以下では、養育費を受け取った場合に所得税、あるいは贈与税がかかるのか解説していきたいと思います。
所得税はかからない
まず、所得税はかかりません(所得税法9条1項15号)。
所得税法
9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一~十四 (略)
十五 (略)及び扶養義務相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
離婚した後も、子どもと離れて暮らす親は子どもに対して扶養義務を負っています。そして、養育費はその「扶養義務を履行するため給付される金品」にあたるからです。
贈与税は原則かからない
また、原則、贈与税もかかりません(相続税法21条の3第1項第2号)。
相続税法
21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一 (略)
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
養育費は「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産」にあたるため、贈与税の課税価格には算入されず、贈与税はかからないのが原則です。
養育費に贈与税がかかる場合
もっとも、相続税法によると「通常必要と認められるもの」以外のものは贈与税の課税価格に算入され、贈与税がかかってしまうことになります。そこで、「通常必要と認められるもの」の範囲が問題となります。この点、国税庁は「通常必要と認められるもの」の範囲について次のように解釈しています。
法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする(相続税基本通達21-3)。
この国税庁の解釈によれば、
①養育費を一括で受け取って銀行口座に預金した場合
②養育費を株や家の購入代金に充てるなど、本来の養育費の使い方とは異なる使い方をした場合
などは贈与税がかかってしまうことになります。
贈与税の計算方法
それでは、仮に贈与税がかかる場合、贈与税はどのように計算されるのでしょうか?贈与税の計算式は次のとおりです。
贈与税=(課税価格ー110万円(基礎控除))×税率-(税率ごとの控除額)
贈与税の税率には特例税率の適用がない「一般贈与財産の税率」と適用がある「特例贈与財産の税率」がありますが、養育費は一般贈与財産にあたるため一般贈与財産の税率が適用されます。
【一般贈与財産の税率と控除額】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | ー |
| 200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1000万円超 1500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1500万円超 3000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3000万円超 | 55% | 400万円 |
仮に、600万円の養育費を一括で受け取り、贈与税がかかった場合の贈与税は
82万円=(600万円-110万円)×30%-65万円
となります。
養育費は一括で受け取っても非課税にする方法
このように、養育費を一括で受け取ると贈与税がかかる可能性があります。もっとも、次の方法をとれば、養育費を一括で受け取っても贈与税を非課税とすることができます。
教育資金贈与信託を活用する
教育資金贈与信託とは、父母などから30歳未満の子どもなどに対し、教育資金名目で金銭を一括贈与しても、1500万円までは非課税とする制度です。
たとえば、親が子どもに教育資金を贈与したい場合、親(委託者)が銀行等(受託者)と信託(親が銀行等にお金を託す)契約を結びます。子ども(未成年の場合は親権者)は必要書類を税務署に提出し、非課税措置を受けることができます。銀行等に預けたお金は、教育に関してお金を使ったことを証明する書類を銀行等に提出することによって、口座から引き出すことができます。
なお、以下の点に注意が必要です。
・教育資金と使途が限定されている
・教育資金とは、幼稚園、小中高、大学等に直接支払われる入学金、授業料、学用品の購入費用等に限られる(学習塾代、習い事代は含まれない)
・途中解約は不可
・契約期間中に委託者が死亡した場合は、教育資金として使うことができなかった金銭に相続税が課される可能性がある
・受益者(子どもなど)が30歳に達したときに契約が終了し、教育資金として使うことができなかった金銭には贈与税が課される可能性がある
・契約できるのは、受益者1人につき1つの銀行等まで
財産分与でお金を受け取る
次に、養育費として受け取るお金を財産分与の中に含ませて受け取るという方法も考えられます。
原則として、財産分与で受け取ったお金にも税金はかかりません。財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を二人で分け合うものにすぎないからです。もっとも、贈与税を免れるための財産分与だと税務署に判断された場合には贈与税を課される可能性がありますので注意が必要です。
養育費を払う側の税金(扶養控除)について
ここまで養育費を受け取る側の税金について解説してきましたが、最後に知っておいて欲しいのが、養育費を払う側に関係する税金の扶養控除のことです。
扶養控除とはある一定の人を扶養している人(今回の場合、養育費を払う相手)の所得税を安くする所得控除の一種です。所得税は「課税所得金額×税率ー控除額」の計算式で計算されますので、扶養(所得)控除が適用されることで「課税所得金額」が少なくなり、結果的に所得税が安くなります。扶養控除の金額は以下のとおりです。
| 年齢 | 控除額 |
| 16歳未満 | 対象外 |
| 16歳以上19歳未満 | 38万円 |
| 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 23歳以上70歳未満 | 38万円 |
扶養控除の適用を受けるには、子どもが相手から養育費の支払いを受けていること(相手と生計を一にしていること)のほか、子どもが16歳以上であること、子どもの年間の合計所得金額が48万円以下であることが必要です。子どもと相手とが同居している必要はありません。
扶養控除の適用を受けるための手続きは、相手が会社員の場合、11月末ごろから行われる年末調整のときに相手が必要書類に記入して会社の担当者に提出します。相手が自営業者の場合は、相手が確定申告書に必要事項を記入して税務署に提出します。
もし、今まで扶養控除の適用を受けてきたにもかかわらず、離婚を機に相手が養育費の支払いを渋るような場合は、扶養控除が適用されなくなる結果、今までよりも所得税が高くなる可能性があることを指摘し、養育費を払うよう促してみるのも一つの方法です。
まとめ
今回のまとめです。
- 養育費を受け取ると所得税はかからないが、贈与税はかかることがある
- 一括、分割のメリット、デメリットを踏まえてベストな選択を