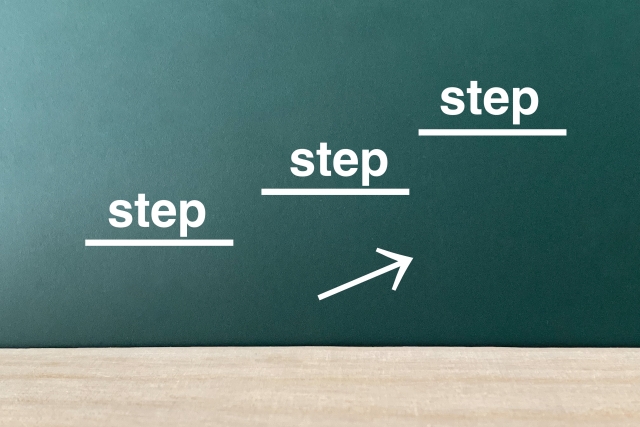離婚後でも親権者を変更することはできます。
もっとも、親権者を変更するには一定の手続きが必要です。また、親権は子どものためにある権利ですから、親権者を変更することが子どもの利益のために必要があると認められる場合でなければいけません。
なお、2024年(令和6年)5月に成立した改正民法により、離婚後でも共同親権を選択できるようになります(※)。そのため、あとで述べるように、親権者変更のパターンに新たなパターンが追加されます。
そこで、今回は、はじめに親権者変更のパターンについて解説した上で、親権者変更の手続き、単独親権・共同親権への親権者変更が認められるケースなどについて詳しく解説していきたいと思います。
※改正民法は2026年(令和8年)5月までに施行されます。
この記事を書いた人

-
※ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しています。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025年11月30日示談書不倫慰謝料請求を内容証明でする方法
- 2025年11月28日示談書不倫慰謝料の時効は何年?
- 2025年11月28日示談書不倫相手の住所の調べ方
- 2025年11月27日示談書不倫相手との話し合いを進めるためのコツは?
親権者変更は3パターン
改正民法が施行される前(現段階)の離婚後の親権者変更のパターンは、
①【変更前】単独親権→【変更後】単独親権
のみですが、改正民法が施行された後は①のパターンに加えて
②【変更前】共同親権→【変更後】単独親権
③【変更前】単独親権→【変更後】共同親権
のパターンも可能になります。
②は、改正民法施行後の共同親権で離婚したものの、その後、単独親権に変更したというパターンです。
③は2つのケースにわかれます。1つは、改正民法施行後に単独親権で離婚したものの、その後、共同親権に変更したというケースです。もう1つは、改正民法施行前に単独親権で離婚したものの、その後、共同親権に変更したというケースです。
③の後者のケースでは、改正民法施行前に単独親権で離婚しているため、その後は共同親権に変更できないのではないか?と思われる方もおられるかもしれません。しかし、このケースでも共同親権に変更できることになっています。
親権者変更の手続き
親権者変更の手続きは次のとおりです。
①調停の申し立て
まず、家庭裁判所に対して親権者変更調停の申立てを行う必要があります(※)。
一部の例外を除き、親同士の話し合いだけで親権者を変更することはできません。先ほど述べたいずれのパターンでも、調停の手続きを経る必要があります。
家庭裁判所への申し立ては書面で行います。申立先の家庭裁判所は相手の住所地を管轄する裁判所が基本ですが、もし相手と合意している裁判所があればその裁判所が申立先の裁判所となります。
申立書面には戸籍謄本などの書類を添付しなければなりませんので、あらかじめどんな書類が必要となるのか、裁判所に問い合わせるなどして確認しておきましょう。また、収入印紙や連絡用の郵便切手代も必要です。あわせて確認しておきましょう。
※申立てできる人(申立人)
子どもの親族です。子どもの父・母のほか、祖父母やおじ・おばなどの親族も申立てできます。元配偶者が有責配偶者でも申し立てできます。なお、改正民法施行後は、子ども自身も申立てすることが可能となります。
②調停
申立書が裁判所に受理されると裁判所に行く期日(日時)を調整します。調整した後、期日が書かれた書面が裁判所から住所宛に郵送で送られてきます。期日には、指定された場所、時間に出席します。
期日では、申立人、相手それぞれ別々に、調停委員から話を聴かれます。また、家庭裁判所調査官の調査が行われ、調査の結果が裁判所に提出されることがありますから、調停委員のほか調査官への対応も大事になります。
調停では
・現在の親権者の子どもに対する愛情の度合い
・現在の親権者の意向
・これまでの養育状況、環境
・子どもの年齢、性別、性格、就学状況、生活環境、親との関係性
などが調査され、親権者を変更することが子どもの利益のために必要かどうかが見極められます。子どもが15歳以上の場合は子どもの意思が尊重される傾向にあります。
期日は、親権者変更について合意できるまで、おおよそ1か月に1回のペースで入ります。
③調停成立or審判
話し合いの結果、申立人、相手双方が親権者変更に合意し、裁判所が親権者を変更することが相当だと認めた場合は調停が成立します。
一方、調停での話し合いが見込めない場合や調停で親権者変更に合意できなかった場合は自動的に審判という手続に移行します。審判では、調停での話し合いの内容や調査官の調査結果などを踏まえて、裁判官が親権者の変更について判断します。
なお、裁判官の判断に不服がある場合は不服を申し立てる(即時抗告する)ことができます。即時抗告した場合は審理は高等裁判所に引き継がれ、高等裁判所で親権者を変更するかどうかが判断されます。
単独親権への親権者変更が認められやすいケース
家庭裁判所は、親権者変更を行うことが子どもの利益のために必要があると認めるときに、親権者の変更を認めます。では、子どもの利益のために必要があると認めるとき、とは具体的にどんなケースのでしょうか?まず、単独親権(一方の親)から単独親権(他方の親)へ変更されやすいケース(パターン①)、共同親権から単独親権へ変更されやすいケース(パターン②)についてみていきましょう。
子どもが虐待を受けている場合
まず、子どもが親権者から虐待を受けている場合です。
「虐待」とは次の4種類に分類されます。
・身体的虐待・・・殴る、蹴る など
・性的虐待 ・・・子どもへの性的行為 など
・ネグレクト・・・家事、育児の放棄 など
・心理的虐待・・・言葉による脅し、兄弟姉妹間の差別 など
なお、改正民法では、父母の双方を親権者と定めることにより子どもの利益を害すると認められるときは、裁判所は父母のいずれかの単独親権と定めなければならないとされています。
父母の双方を親権者と定めることにより子どもの利益を害すると認められるときとは、①父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき、あるいは②父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき、とされています。
上記②の判断にあたっては、㋐父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動のおそれの有無、㋑話し合いによって合意ができなかった理由等といった事情を考慮するとされています。
子どもが親権者の変更を望んでいる場合
次に、子どもが親権者の変更を望んでいる場合です。
親権は子どものためにありますから、親権者を変更するにあたっては子どもの意思も考慮されます。
子どもが小さいうち(0歳~10歳前後が目安。ただし、個人差はあります)は、まだ子どもに適切な親権者を選ぶほどの判断能力が備わっているとは言い難く、子どもの意思はそれほど重要視されません。
一方、子どもが10歳を超えてくると子どもの意思が尊重にされやすくなります。なお、子どもが15歳以上の場合、裁判所は子どもの意見を聴かなければならないとされています。
子どもの養育環境が変化する場合
次に、子どもの養育環境が変化する場合です。
たとえば、親権者が海外赴任することになった、国内でも転勤することになったなど、これまでと同様の子育てができなくなるおそれがある場合です。もっとも、単に海外赴任することになった、転勤することになったというだけで親権者変更が認められるわけではありません。
海外赴任や転勤などの事実に加えて、赴任(転勤)先の養育環境や子どもの意思などの事情も総合的に勘案して、親権者を変更することが子どもの利益のために必要と認められる場合に親権者を変更することが認められます。
親権者が大病・障害を患った、死亡した
次に、親権者が大きな病気や障害(精神障害も含む)を患った場合、死亡した場合です。
子育てには体力、精神力が必要です。子育てしていく上では親権者自身が健康である必要があります。大きな病気や障害を患った状態だと子どもを健やかに育てていくことは難しく、親権者を変更することを検討すべきでしょう。
親権者が死亡した場合は未成年者後見人の選任か親権者の変更を申し立て、未成年の子どもの世話をしてくれる人を選んでもらう必要があります。親権者が死亡したからといって、元配偶者に自動的に親権が移るわけではない点に注意が必要です。
共同親権への親権者変更が認められやすいケース
次に、単独親権から共同親権に変更されやすいケース(パターン③)としては、
・父母間の関係と子育ての際の協力関係を切り分けることができる
・調停等の過程で感情的な対立が緩和され、共同親権を行使することができる
などのケースが考えられます。
古くから「子は鎹(かすがい)」というように、親同士は関係が悪くても、子どもがいることで関係が保たれるというケースは多いのではないでしょうか?
そうしたケースでは、子どもの養育の面では協力関係を築いていくことが期待できるため、共同親権へと変更されることも考えられます。
なお、改正民法では、親権者を変更するかどうかの判断ににあたり、裁判所は①父母と子どもとの関係、②父と母との関係、③離婚の際の話し合いの経過、④その後の事情の変更などの事情を考慮するとされています。
親権者変更が難しいケース
ここまで見てきたように、親権者の変更は、裁判所に子どもの利益のために必要があると認められた場合でなければ難しいといえます。そのため、次のようなケースでは、 親権者変更は難しいといえます。
子どもを手放したい
まず、
- 子どもの面倒をみることが難しくなった
- 子育てが面倒くさくなった
- 再婚相手との生活を優先させたくなった
- 再婚相手が子どもを疎ましく思っている
といった理由で親権者変更の申し立てをする場合です。いずれも親権者の身勝手な理由だからです。
もっとも、子どもと親権者との関係が悪化している場合、子どもが再婚相手から虐待を受けている場合、子どもが親権者の変更を望んでいる場合などは、他方の親から親権者変更の調停等を申し立てることで親権者を変更できる可能性があります。
面会交流ができない
次に、面会交流ができないという場合です。
相手が面会交流を認めてくれない、約束どおり面会交流を実施できないという場合、親権者を変更したいと考える方も多いと思います。しかし、あなたの思い通りに面会交流できないからといって、直ちに相手が親権者として不適格者であるということはできません。
面会交流ができなくて困っている場合は、まずは相手が面会交流を拒んでいる理由を特定し、その理由を除去した上で実施に向けた働きかけを行っていくことが先決です。話し合いでも埒が明かない場合は面会交流調停を申し立てることも検討しましょう。
その他
そのほか、
- 相手の子育ての仕方、教育方針が間違っている
- 離婚時に適当に親権者を決めたため変更したい
といった理由でも親権者変更が認められる可能性は低いといえます。親の身勝手な理由や都合、考え方の違いだけで親権者を変更することは難しいでしょう。
親権者変更が認められた後は届出が必要
調停成立、または審判の確定(※)によって親権者変更が認められた場合は、調停成立、または審判確定日から10日以内に、役所の戸籍係に親権者変更の届出をする必要があります。
※裁判所から自宅に送られてくる審判書の謄本を受け取った日(相手と日にちが異なる場合は遅い日)の翌日から起算して14日間の不服申立て期間を経過した日が確定日です。
届出をする人
届出をする人(届出人)は新たに親権者となった人です。
届出をする役所
届出をする役所は、届出人の住所地の役所、子どもの本籍地がある役所、のいずれかで行うことが通常です。前者の役所で行う場合は子どもの戸籍謄本が、後者の役所で行う場合は届出人の戸籍謄本が必要です。
必要なもの
届出の際に必要なものは、
□ 親権者変更の届出書
□ 調停調書の謄本(調停成立の場合)
□ 審判書の謄本と確定証明書(審判確定の場合)
□ 印鑑
□ 戸籍謄本
です。詳細は届出をする役所の戸籍係に問い合わせた方が確実です。なお、調停調書の謄本と確定証明書は裁判所から取り寄せる必要があります(審判書の謄本は裁判所から自宅に送られてきます)。
子どもの戸籍を親権者の戸籍に入れるには入籍届が必要
親権者変更の届出のほか、ご自身の戸籍に子どもの戸籍が入っていない場合に必要な届出が入籍届です。親権者が変更されたからといって、子どもの戸籍があなたの戸籍に自動的に移ってくるわけではない点に注意が必要です。
なお、入籍届をする前に、まずは、子どもの苗字を変更する手続きが必要です。異なる苗字の者同士を同じ戸籍に入れることができないためです。子どもの苗字を変更するには家庭裁判所に対して変更許可の申し立てを行い、変更の許可を得る必要があります。
親権者変更が認められなかった場合の対応
親権者変更の調停等を申し立てたとしても、必ずしも親権者の変更を認めてもらえるとは限りません。そこで、最後に、万が一親権者変更を認めてもらえなかった場合のとりうる対応について解説します。
面会交流を実施する、条件を見直す
まず、面会交流を実施していない場合は実施する、実施している場合は面会交流の条件を見直してみることです。
実施の有無やルールについて相手と話し合ってみましょう。話がまとまった場合は後で言った・言わないのトラブルになることを防止するため書面を作成しておきます。一方、相手が話し合いに応じない、話がまとまらないという場合は面会交流調停を申し立てることを検討します。
再度調停を申し立てる
次に、再度調停を申し立てることです。
親権者変更が認められなかったからといって、再度調停を申し立ててはいけないという決まりはありません。前回の調停で主張できなかった事情が見つかり、子どものために親権者を変更すべきと考えるのであれば、再度調停を申し立ててもよいでしょう。
もっとも、前回の調停から間なく調停を申し立てても、裁判所が申し立てそのものを受理してくれない可能性があります。再度調停を申し立てるとしても、申立ての前に、申立ての内容等を十分に検討しておく必要があります。
まとめ
今回のまとめです。
- 原則、親の合意だけで親権者を変更することはできない
- 親権者を変更するには家庭裁判所に調停(または審判)を申し立てる必要がある
- 裁判所が親権者を変更することが子どもの利益のために必要と認めた場合に親権者を変更できる
- 親権者の変更が認められたら役所に届出が必要
- 子どもの戸籍を自分の戸籍に入れる場合も諸手続きが必要