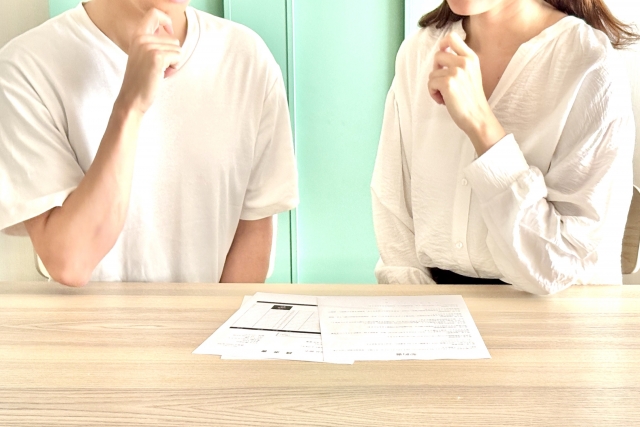現在は、離婚後は単独親権ですが、今後は、「離婚後も共同親権を選択できるようになる」ということは、テレビやネットなどで見聞きした方も多いと思います。
しかし、いつからこの制度が始まるのか、離婚後の親権について今後はどのように決めていく必要があるのかなど、わからないことも多いと思います。
そこで、今回は、共同親権のこうした疑問に関する記事を書いてみました。ぜひ最後までお読みいただき、今後の参考にしていただけると幸いです。
この記事を書いた人

-
※ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しています。
→プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025年11月30日示談書不倫慰謝料請求を内容証明でする方法
- 2025年11月28日示談書不倫慰謝料の時効は何年?
- 2025年11月28日示談書不倫相手の住所の調べ方
- 2025年11月27日示談書不倫相手との話し合いを進めるためのコツは?
共同親権とは?
共同親権とは、父親、母親の双方が共同で行使できる親権のことをいいます。一方、単独親権とは、父親または母親のどちらかが行使できる親権のことをいいます。
親権を行使するとは、子どもに関することを決めるという意味ととらえておけばいいでしょう。単独親権では親権をもった親が子どもに関することを一人で決めることができますが、共同親権では一人で決めることができません。
現在は、婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権としなければいけません。しかし、今後(改正民法施行後)は、離婚後でも共同親権を選択できるようになります。
改正民法の施行日は、令和6年(2024年)5月24日から2年以内の政府が定める日とされています。
共同親権のメリット
離婚後に共同親権を選択できるメリットは次のとおりです。
親権を奪い合うケースが減る
まず、親権を奪い合うケースが減ることです。
これまでは、離婚するには、父親または母親のどちらかを親権者と決めなければいけませんでした。そのため、親権を失いたくないと、双方が親権を譲らず争いとなるケースが多くありました。また、親権者を定めなければ離婚できず、親権を巡って争いになると離婚までに時間がかかるという状況でした。しかし、今後は、離婚後でも共同親権を選択できるため、親権を奪い合うケース、親権争いで離婚までに時間がかかるケースが減るのではないかと思われます。
養育費の確実な履行が期待できる
次に、養育費の確実な履行が期待できることです。
現在のところ、同居親(子どもと一緒に生活する親)に養育費をきちんと払ってない別居親(通常は親権をもたない親)が多いのが現状です。しかし、今後は、別居親も親権をもつことで、子どもを養育していく自覚と責任が維持・継続され、それが養育費の確実な履行につながるのではないかと思われます。
面会交流が実施されやすくなる
次に、面会交流が実施されやすくなることです。
先ほど述べたとおり、別居親も親権をもつことで、子どもの養育への関心が維持・継続されることが期待できます。養育費の支払いが確実に履行されれば、同居親の面会交流に対する心理的なハードルも低くなり、これまで以上に、円滑に面会交流が実施されていくのではないかと思われます。
子どものためになる
最後に、何より子どものためになることです。
今回の改正で離婚後も共同親権を選択できるようになった理由の一つに、離婚後も双方の親が子どもの養育に関与することが子どもの成長にとってよいのではないか、との考えがあります。
共同親権のデメリット
一方、離婚後に共同親権を選択できるデメリットは次のとおりです。
相手と意見が対立してしまう
まず、子どもの教育方針などをめぐって意見が食い違い、子どもの利益を害してしまう可能性があることです。
あとで述べるとおり、離婚後も共同親権を選択した場合、教育方針など子どもに関する重要な事項については、親同士が話し合って決めることが原則です。そのため、相手と意見が食い違うばかりに、物事を決めることが遅くなったり、あるいは何も決めることができない状態が続いたりして子どもの利益を害してしまうおそれがあります。
虐待・DVを受けるおそれがある
次に、虐待やDVを受ける(続ける)おそれがあることです。
離婚後も共同親権を選択した場合、別居親との交流は継続されると思われます。別居親との交流を継続するためには、ある程度、同居親や子どもの情報を公開せざるをえず、そのことが虐待やDVにつながる可能性があります。もちろん、離婚前から虐待やDVを受けているなどの場合は、裁判所に共同親権か単独親権かを決めてもらうよう申し立てることもできます。しかし、それでも共同親権とされてしまう可能性がまったくないとはいえません。
同居親や子どもの負担が増える
次に、同居親や子どもの負担が増える可能性があることです。
離婚後も共同親権を選択するということは、別居親が子どもとの交流に積極的であることが多いと思われます。こうしたケースでは、面会交流などを通じて、別居親と子どもとの交流が密になることが想定されます。そうすると、同居親にとっては面会交流などが負担に感じるでしょう。また、別居親が積極的でも子どもが消極的な場合は、子どもにとっても負担に感じることがでてくるでしょう。
共同親権が原則だが、単独親権となることも
改正民法では、「親権は父母が共同して行う。」として共同親権を原則としています。もっとも、先ほど述べたとおり、離婚後の親権については、共同親権か単独親権かを選べることができるようになっています。また、仮に共同親権を選択したとしても、次のケースでは、父親または母親のいずれか一方が単独で親権(単独親権)を行使することができることになっています。
【(共同親権を選択したとしても)単独親権が可能なケース】
①他の一方が親権を行使できないとき
②子の利益のため急迫の事情があるとき
③監護及び教育に関する日常の行為をするとき
④特定の事項にかかる親権の行使について、親権の行使を単独ですることができると裁判所が認めたとき
①の場合とは、親権者の一方が事実上または法律上親権を行使することができない場合です。親権を事実上行使できない場合とは、たとえば、父親または母親が行方不明になった場合、刑務所に服役している場合などが考えられます。親権を法律上行使できない場合とは、父親または母親が後見開始の審判を受けて行為能力を失った場合などが考えられます。
②の場合とは、たとえば、期限のある入学手続きをする場合、緊急に医療行為を受けるため病院との間の診療契約を締結する必要がある場合、DV・虐待から避難が必要な場合などが考えられます。
③の監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生じる身上監護に関する行為で、子どもに対して重大な影響を与えないものをいいます。たとえば、子どもに食事を与える、子どもが着る服を選ぶなどの身の回りの世話、重大な影響のない治療行為の決定、薬の服用、短期間の観光目的での旅行、子どもの習い事の選択などをあげることができます。
④については、ある「特定の事項」に関する親権の行使について、父母間の話し合いで決着がつかないときに、父親または母親からの請求によって、裁判所が単独親権を認めることができるということです。ただし、子どもの利益のために必要があると認められる場合でなければなりません。なお、「特定の事項」とは、③にあげた行為以外の身上監護に関する行為や子どもの財産管理、身分行為に関する事項のことをいいます。
離婚後の親権の決め方
改正民法前は、離婚するにあたって未成年の子どもいるときは、離婚後の親権者を父親か母親のいずれかにするかを話し合い、合意できればいずれか一方を親権者と定めて離婚を成立させることができ(※)、話し合いができない、あるいは話し合いはできたけれども親権者について合意できなければ離婚を成立させることができませんでした。
一方、改正民法施行後は、次のいずれかをすることによって離婚を成立させることができるようになりました(※)。
①離婚後の親権者を決めること
②離婚後の親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申し立てをすること
①は、要は、離婚後、共同親権とするか、単独親権とするかを夫婦で話し合って決めてください、ということです。
②は、夫婦で話し合って離婚後の親権者を決めることができない事情がある場合であっても、裁判所に親権者の指定を求める審判または調停を申し立てれば、それで離婚を成立させることができる、ということです。離婚後の親権者を定めなくても離婚を成立させることができる点が大きな改正点といえます。
なお、①または②の事項は離婚届に書かなければいけません。離婚届に書かなければ離婚届は受理されません。
※ただし、他に話し合うべきことがない場合に限ります。
共同親権に関するQ&A
最後に、離婚後の共同親権に関してよくある疑問についてお答えします。
離婚後でも共同親権を選択できる制度はいるからはじまりますか?
先ほど述べましたとおり、令和6年(2024年)5月24日から2年以内の政府が定める日とされています。具体的な日にちについては、今後、政府から発表されます。
家事審判や調停、裁判でも共同親権とされることはありますか?
改正民法によると、裁判所は、子どもの利益、父母と子どもとの関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮した上で、共同親権か単独親権かを決めることができるとされています。もっとも、次の場合には、裁判所は単独親権としなければならないとされています。
①共同親権とすることが子どもの利益を害すると認めるとき
②父親または母親が子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
③父親または母親の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に重大な影響を及ぼす言動の有無などを考慮して、父母が共同親権を行うことが困難であると認められるとき
以上より、夫婦の話し合いで共同親権とすることに合意できず、裁判所によって共同親権とされる場合とは、少なくとも、虐待やDVなどのおそれがない場合ということができます。
すでに離婚していますが、共同親権に変更することはできますか?
子どもまたはその親族が家庭裁判所に親権者変更の請求をし、家庭裁判所が、単独親権から共同親権に変更することが子どもの利益になると認めるときは、共同親権に変更することができます。
子どもの教育方針などで相手と意見が対立した場合、どうすればいいですか?
家庭裁判所に対して、単独での親権行使を認める審判の申立てを行う必要があります。申立てを受け、家庭裁判所が単独での親権行使を認めるか否かを判断します。